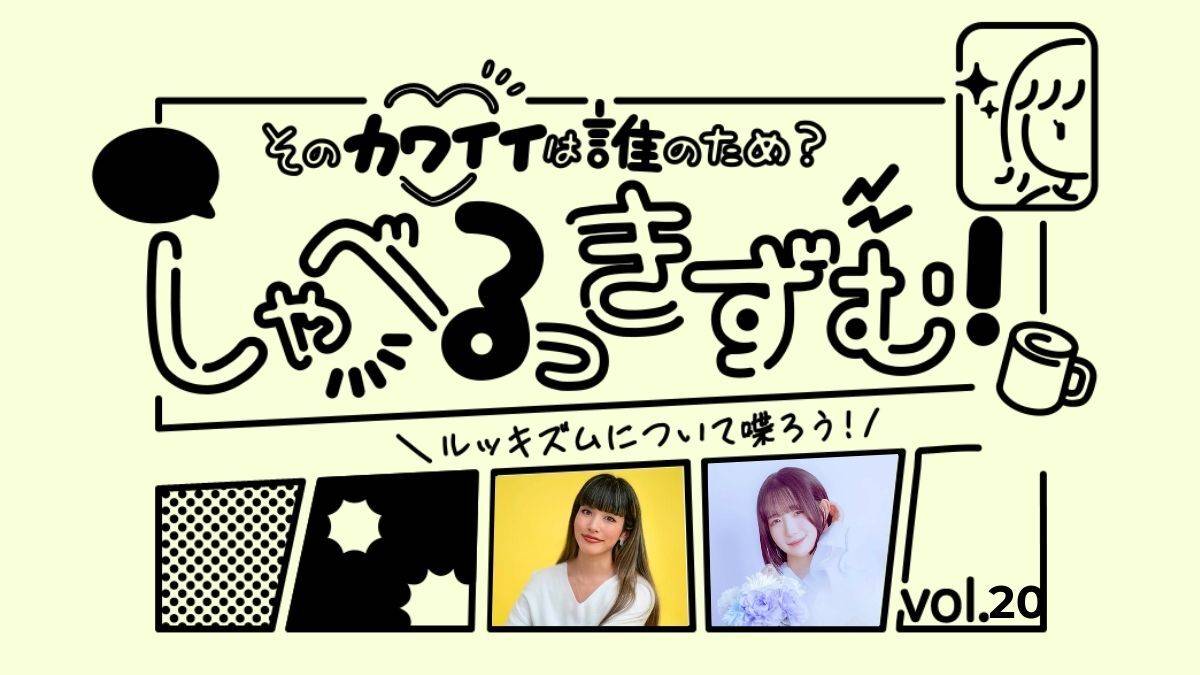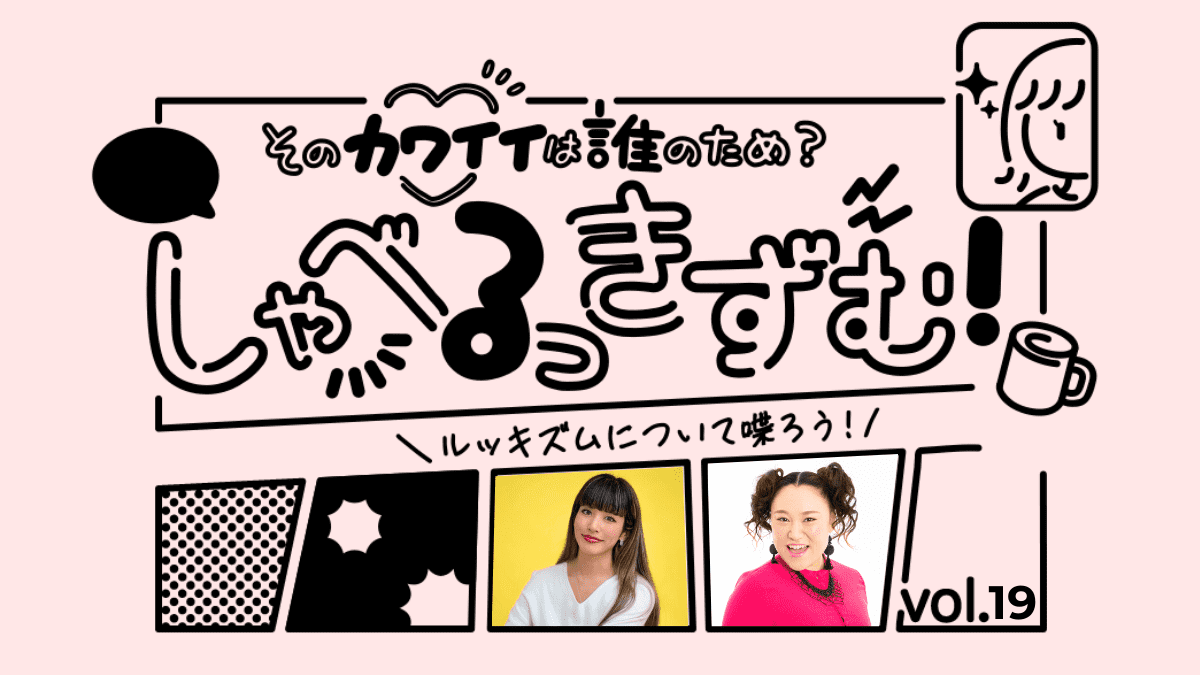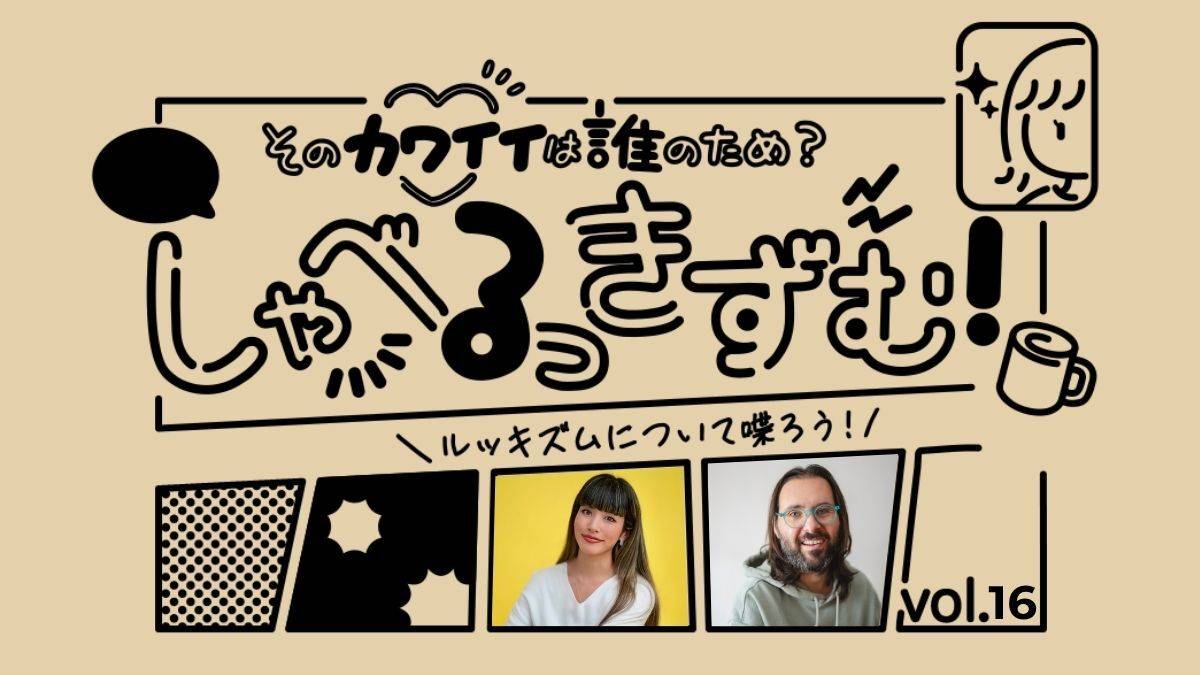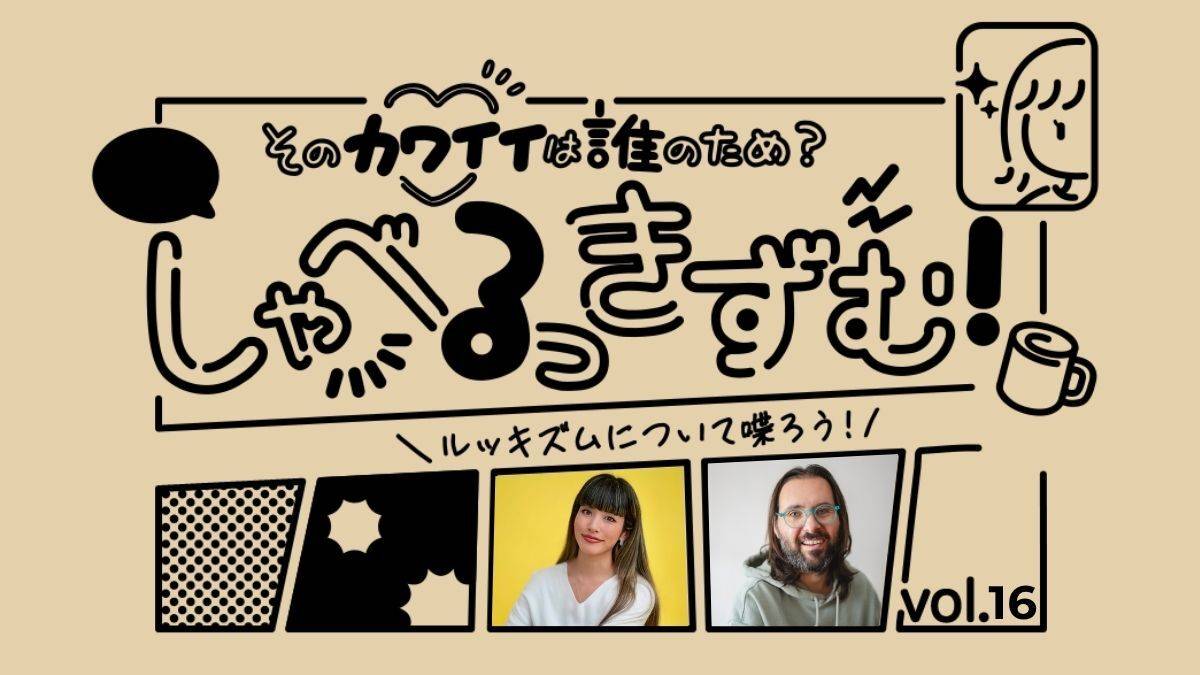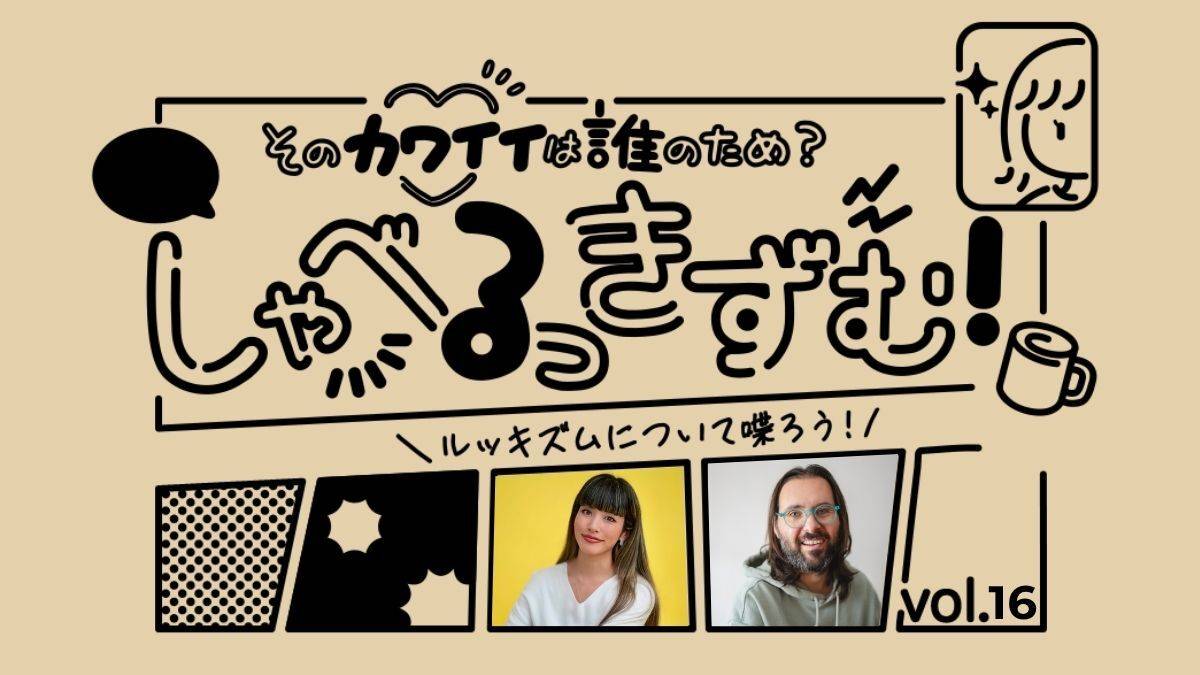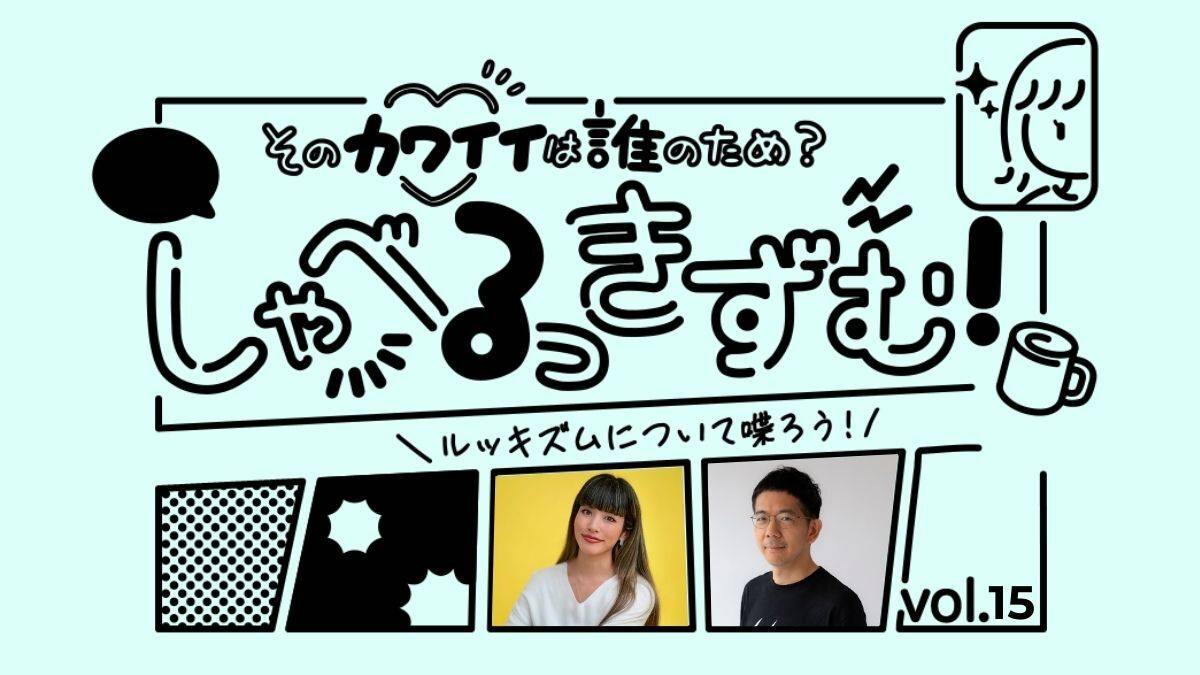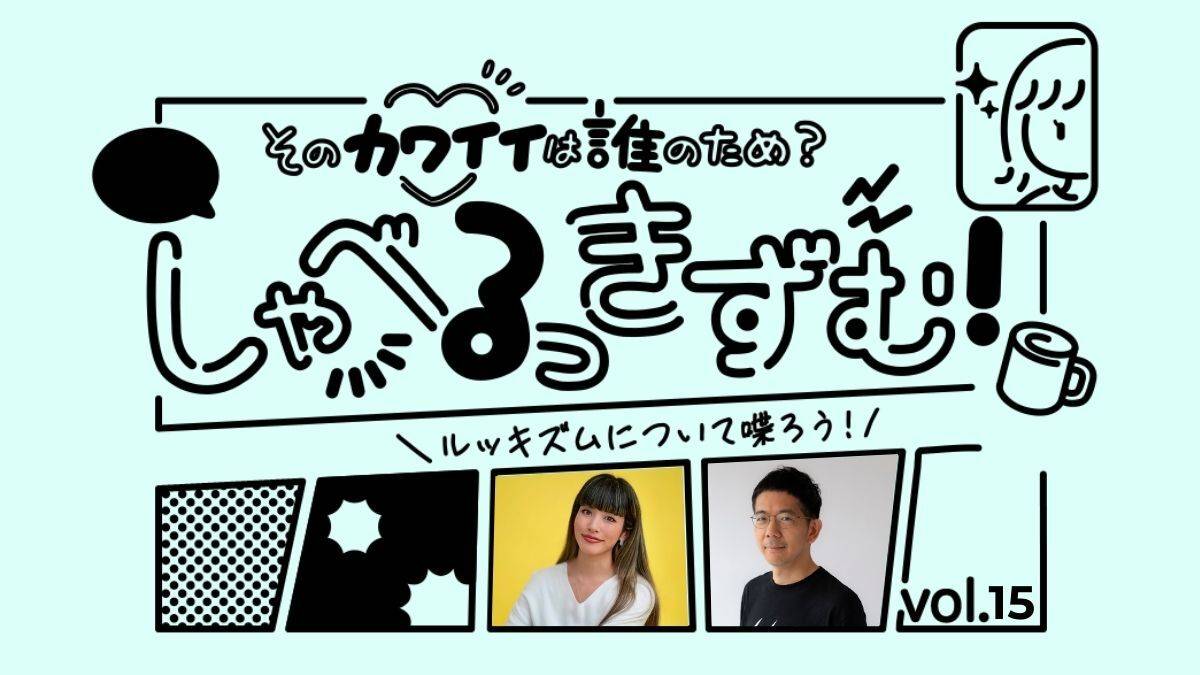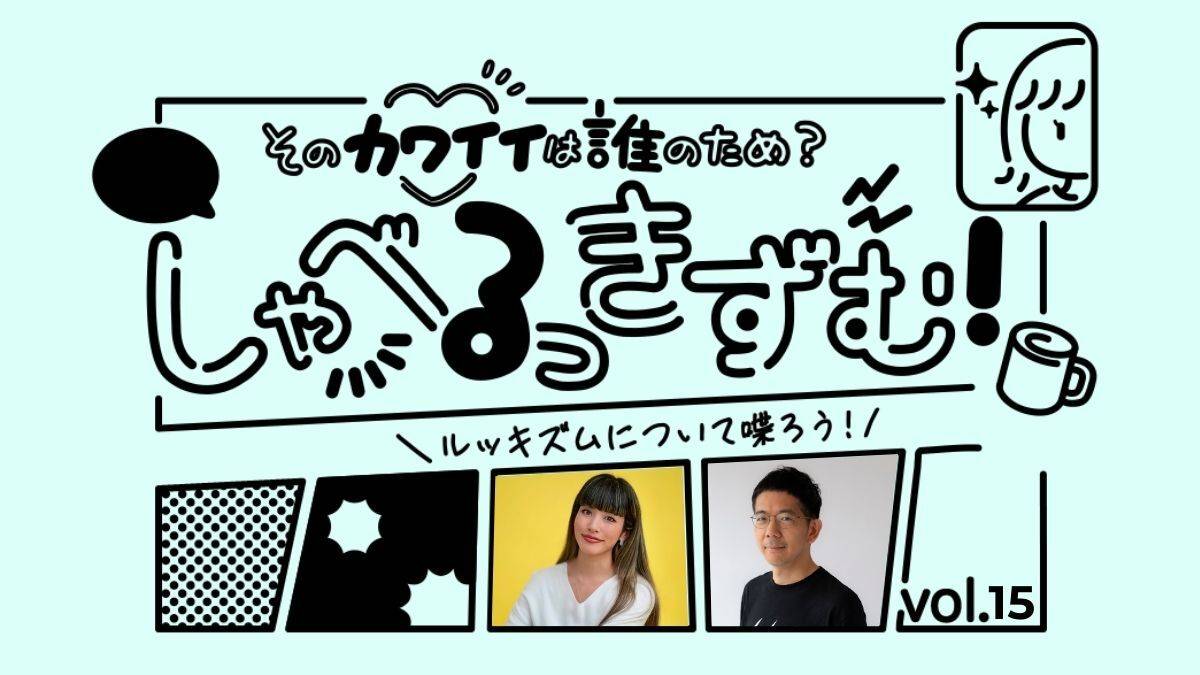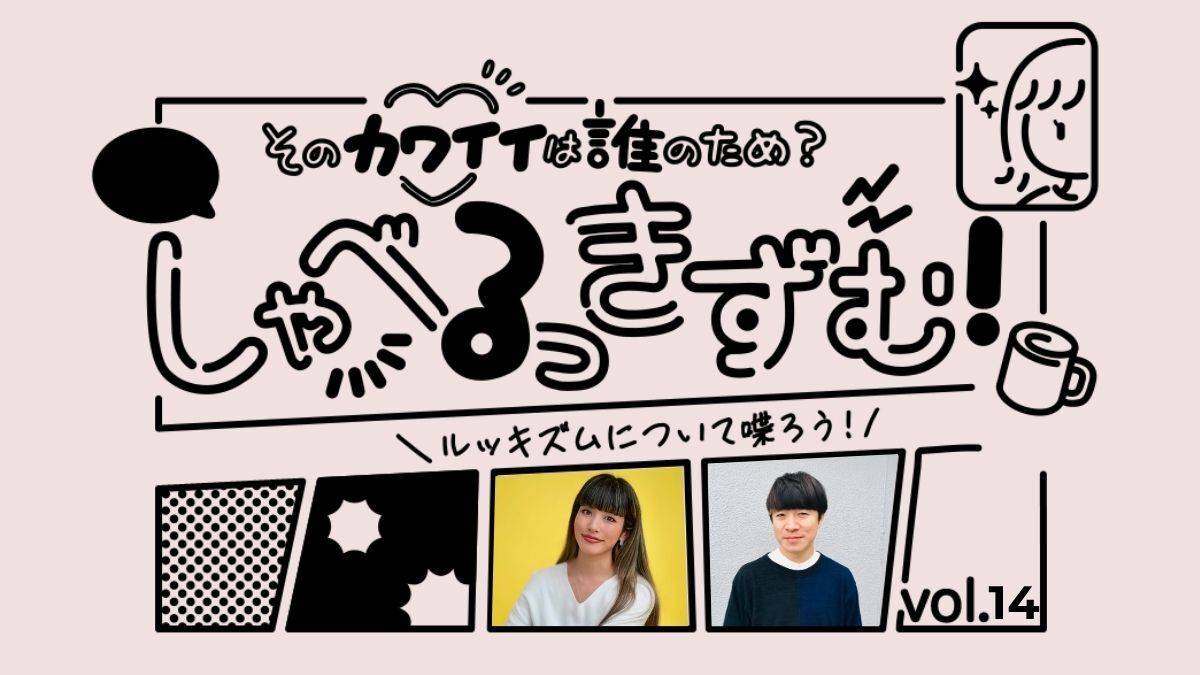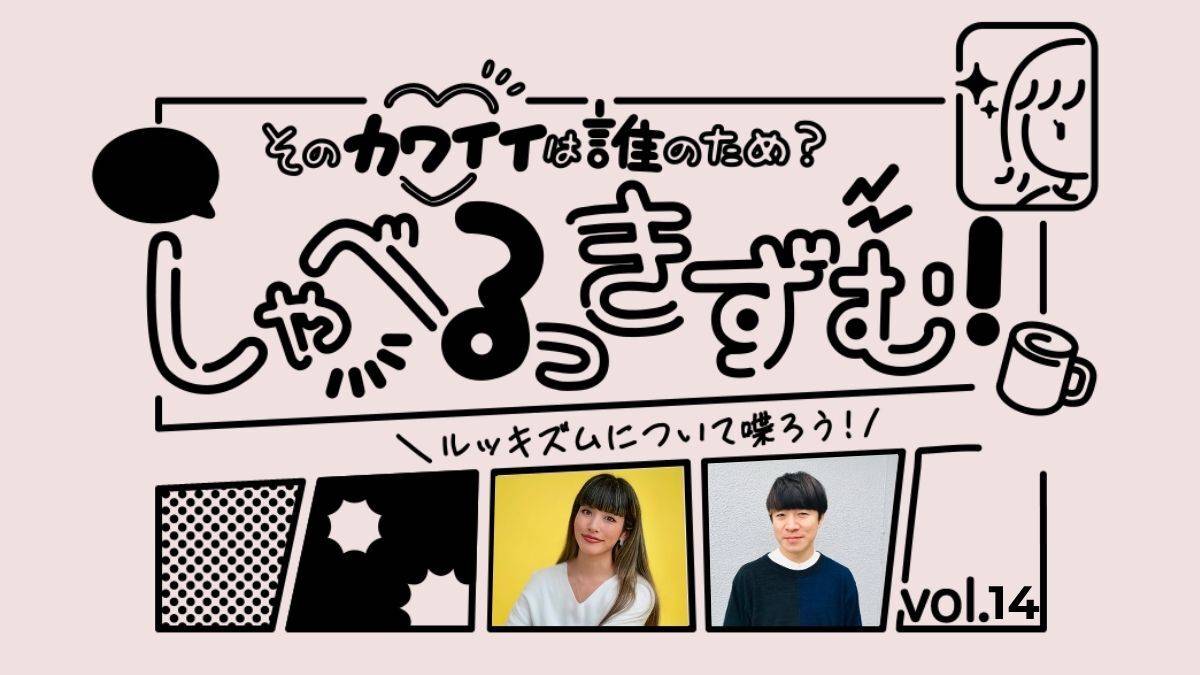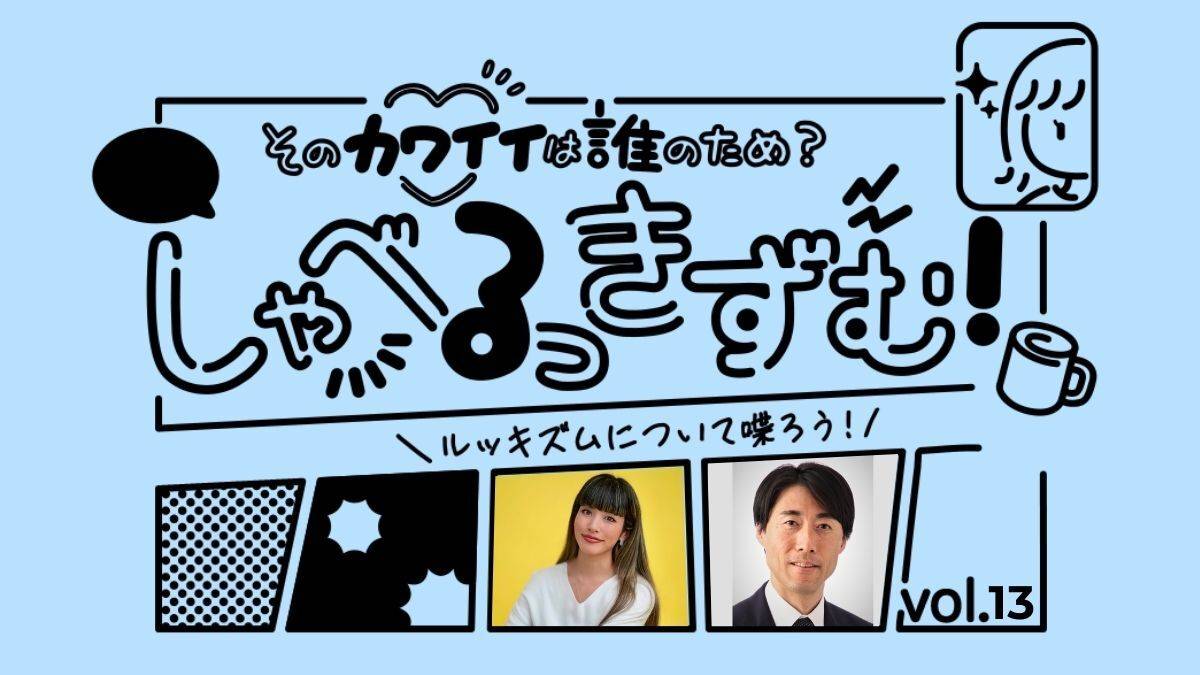しゃべるっきずむ! ビジュについて現役高校生と話す、15年の変化 前川裕奈さん×廣瀬凜さん(1)

容姿で人を判断したり、揶揄したりする「ルッキズム(外見至上主義)」。言葉の認知が進む一方で、まだまだ理解されていないルッキズムについて、おしゃべりしてみよう!自身もルッキズムに苦しめられた経験を持ち、Yoga Journal Onlineで「ルッキズムひとり語り」を執筆する前川裕奈さんとゲストが語り合う連載が「しゃべるっきずむ!」です。 第11回目は、ルッキズムと向き合う高校生にゲストとして来ていただきました!15歳差のふたりの対談から、いまだ世にはびこるルッキズムの「変わったところ」と「変わらないところ」、両方が見えてきました。多世代で一緒にルッキズムの現状と未来について語ります。
外見で判断されることへの違和感
——今回、現役高校生のりんさんにゲストに来ていただきました。「イマドキの高校生はこうだ」「Z世代はこうなんだ」とは一概には言えないなかで、あくまでもりんさんのお話として伺っていきたいと思います。最初に、りんさんがルッキズムという概念に出会ったきっかけから聞かせてもらってもいいですか?
りん:もともと人を外見で判断することに違和感というか、苛立ちみたいなものがあったんです。それで高校1年生のときに授業で「なぜ人を見た目で判断してしまうのか」という苛立ちをエッセイにしたら、優秀賞が取れて……。
前川:すごいですね!その違和感や苛立ちを持った原点は、りんさんが外見でジャッジされた経験があったとか、ですか?
りん:そうですね。当時は“地雷系”と呼ばれるファッションが好きで、暗めのメイクやシールタトゥーなどをセーラー服と合わせてコーディネートするのにハマっていたんです。自分なりに信念があったんですが、周りからそれでジャッジされることも多くて……。人の価値を外見だけで測るような発言もあって、それってどうなんだろうって。
前川:なるほど。
りん:その後、通っていた塾でも世の中への疑問を書く機会があったので、もう少し考えを深掘りして書いてみようと。大学生のチューターの方に「見た目で判断されるっておかしいと思ってて」と相談したら、「それは“外見至上主義”という言葉が合ってるんじゃないか」と教えてもらったんです。
前川:まず、大学生から当たり前のように「外見至上主義」という言葉が出てくることがすごいです。私たちが大学生のときは、まだ浸透していない言葉だったから。
りん:それで「外見至上主義」という言葉を追いかけるなかで「ルッキズム」という言葉にも出会い、本やニュース記事を探して読んだりしていましたね。前川さんに出会ったのは、高校2年生の夏ですね。
前川:そう、りんさんの塾の授業の特別講師として呼ばれて。授業のあとに「もっとお話したいです」と個人的にメールをくれたんですよね。
りん:ルッキズムに専門的に取り組んでいる方にお会いしたことはなかったので、実際に起業という形でルッキズムに向き合う前川さんのことを知って「いた!!!」と思って。学校の授業で前川さんのことを引用させてもらったりしています。

周りの人は「ルッキズム」知ってる?
前川:ちなみに確認ですが、りんさんの「見た目で判断するなよ」という怒りは、服装やメイクなどのファッションがメインという感じですかね?
りん:そうですね。SNSで体型や顔などのルッキズムに触れて考えることも増えましたが、原点はファッションのほうがメインです。
前川:正直、私のなかでファッションとルッキズムの塩梅ってすごいトリッキーだなと思っているんです。なぜなら、顔や体型などの遺伝的なものに比べてファッションの方が自分の意志ですぐに変えられるものだから。とはいえ、ファッションも自己表現のひとつでもあるのも確かで、それでバイアスがかかるのは理不尽。たとえば金髪というだけで「生活派手そう」とか思われるのもおかしいし。
りん:たしかに。最近では「ルッキズム」という単語の感じ方や扱い方も人や世代によって違うように感じています。
前川:言葉が広まるにつれて、良くも悪くも定義がぐちゃぐちゃになっているところはありますね。私もこんなに発信しているけれど、「出たよ、なんとかイズム〜」と言われたり、フェミニズムやエイジズムと一緒にされてしまうこともあります。りんさんの周りの大人や友達の間では、ルッキズムという言葉はどのくらい浸透していますか?
りん:両親は私がルッキズムに興味を持ち始めたのがきっかけで、理解度を高めてきてくれた気がします。「ニュースで見たよ」と言ってくれたりして。
前川:ふむふむ、友達はどうですか?
りん:人によってまちまちですけど、話をすれば「ああ、LookとIsmでルッキズムね」「見た目で判断されることあるよね」みたいな感じで、割と浸透しやすい感じ。TikTokなどのSNSやコメント欄を見ていても、同世代にはルッキズムという言葉を知っている人が多い印象です。
前川:たしかに私も講演をする際、起業・スリランカ・ルッキズムなど様々なエッセンスが入ってくるのですが、世代によって心に刺さっているパートや感想をもらう部分が結構変わってきます。10代〜20代の子は過半数がルッキズムのパートに対してご自身の経験談や感想をくれることが圧倒的に多いですね。自分自身もそうだったけれど、10代後半から20代はまさにルッキズムの渦中にいる世代なんだろうと感じますね。
「みんなかわいい」、そこから自分なりに「盛れてる」か
前川:私がルッキズム沼に陥っていた大学生のときは「ルッキズム」という単語自体、全然知られていなかったので、りんさんの話は希望があるなあ。テレビ番組や漫画でもルッキズムが取り上げられるようになったのは、この15年での最たる変化ですね。あの頃は痩せているのが正義だと思っている子が大半でしたし……。
りん:もちろん口癖みたいに「痩せなきゃ」と言っちゃうのは今でも全然あって、きっとそこについては15年前とあまり変わっていないかもしれません。ただ、最近はアイドルでも筋肉質な子がかっこいいと言われていたり、インフルエンサーもいろいろな体型の人が人気になったりして、そのあたりの多様性はあるかもしれません。
前川:人気な子が出てくると「そういう見た目もいいな」となったりしますよね。価値観の広がりやすさは、良くも悪くもSNSの特徴ですね。時代ごとの流行はあれど、たしかにみんなの言う「かわいい」は流動的になっているのかもしれない。

りん:ちなみに、前川さんの本『そのカワイイは誰のため?ルッキズムをやっつたくてスリランカで起業した話』のタイトルにも本文にも、自分のテンションが上がる容姿を「かわいい」と表現していますよね。今回の対談に向けて何人かの友達と話したんですけど、私の周りでは、それは「盛れる/盛れてない」で表現されるんじゃないかって。
前川:たしかに日常用語だと「盛れる」「盛れてない」かもしれないですね。みんなの「盛れる」の定義はなんですか?
りん:私たちの解釈では、前提としてみんな当たり前に「かわいい」。そのなかで自分が納得できる見た目になっている状態が「盛れる」。写真写りやメイクがうまくいった日に「今日は盛れた」みたいに使っていると思います。
前川:みんな当たり前に「かわいい」が前提にある、と言えるのは素敵です!もちろん全ての高校生が同じ環境下じゃなくても、少なくともりんさんの周りではそれがデフォルトになっているのは希望的。
環境によって差が出るルッキズムの状況
前川:りんさんの周りには「みんな当たり前にかわいい」という価値観があると聞いて、すごく理想的だと思いました。とはいえ、ルッキズムがなくなったわけではないですよね。実際にりんちゃん自身も違和感を覚えたわけだし。
りん:そうですよね。
前川:「見た目で判断するのはよくない」という認知が広まる一方で、それでもルッキズムがなくならない現状を、りんさんはどう考えていますか?
りん:所属する場所や周りの人たちによって、すごく差があるんだろうなって。実は私、高校1年生のときに私立の学校から、服装も髪型も自由な都立高校へ転校しているんです。この2校だけでもルッキズムに関する捉え方や雰囲気が違っているので、かなり環境に左右されることなんだろうなと思っています。個人的には、均一に整えられている私立よりも、みんな好きな格好をしている都立のほうが、友人間でのルッキズムが少ない気がします。その学校によると思うんですけど。
前川:自由な校風のほうが容姿のイメージで判断されるのかと思っていたけれど、そういう側面もあるんですね。とはいえ、オシャレな子や流行に乗れている子と自分を比べて、「自分はあんなふうになれない」と感じてしまう子はまだいるかもしれませんね。
りん:私からは、それぞれが好きな服装やメイクで輝いていると見えているんですけど、実際はどうなんだろう。
前川:同じ高校、同じクラスの中でも人によって見える世界は確実に違ってくるでしょうね。クラスのなかで「モテる見た目」みたいなものはあります?
りん:そうですねえ〜。
*次回、15年で変わったSNSや整形のこと。変わらない構造のこと。 2本目「SNS、整形、メディア……変化していく社会で手を取り合って」は、こちらから。

廣瀬凜さん
2006年生まれ、東京都在住。趣味は、ドラマ鑑賞、アイドルのライブに行くこと。春から慶應義塾大学環境情報学部にて、より記憶に残る広告の背景音(BGM)について公共広告を対象に研究予定。高校時代は、広告の他、若者を対象にジェンダーや外見における価値観や意識についても研究してきた。
前川裕奈さん
慶應義塾大学法学部卒。民間企業に勤務後、早稲田大学大学院にて国際関係学の修士号を取得。独立行政法人JICAでの仕事を通してスリランカに出会う。後に外務省の専門調査員としてスリランカに駐在。2019年8月にセルフラブをテーマとした、フィットネスウェアブランド「kelluna.」を起業し代表に就任。ブランドを通して、日本のルッキズム問題を発信。現在は、日本とスリランカを行き来しながらkelluna.を運営するほか、「ジェンダー」「ルッキズム」などについて企業や学校などで講演を行う。著書に『そのカワイイは誰のため?ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話』(イカロス出版)。yoga jouranal onlineコラム「ルッキズムひとり語り」。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く