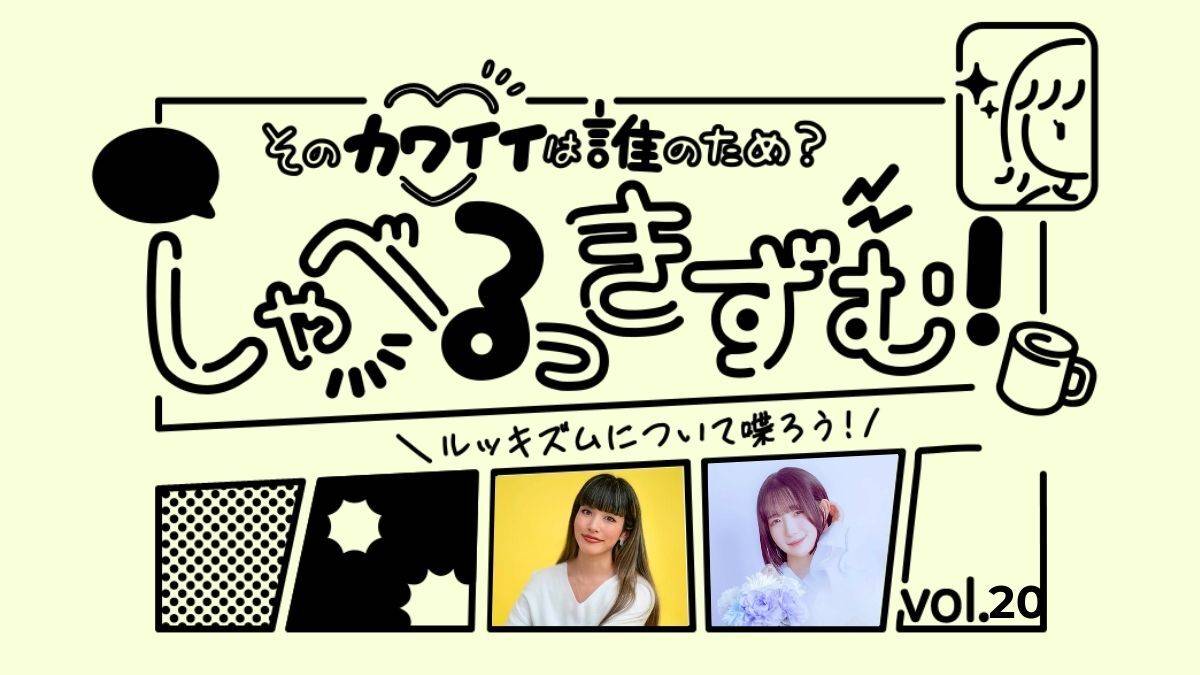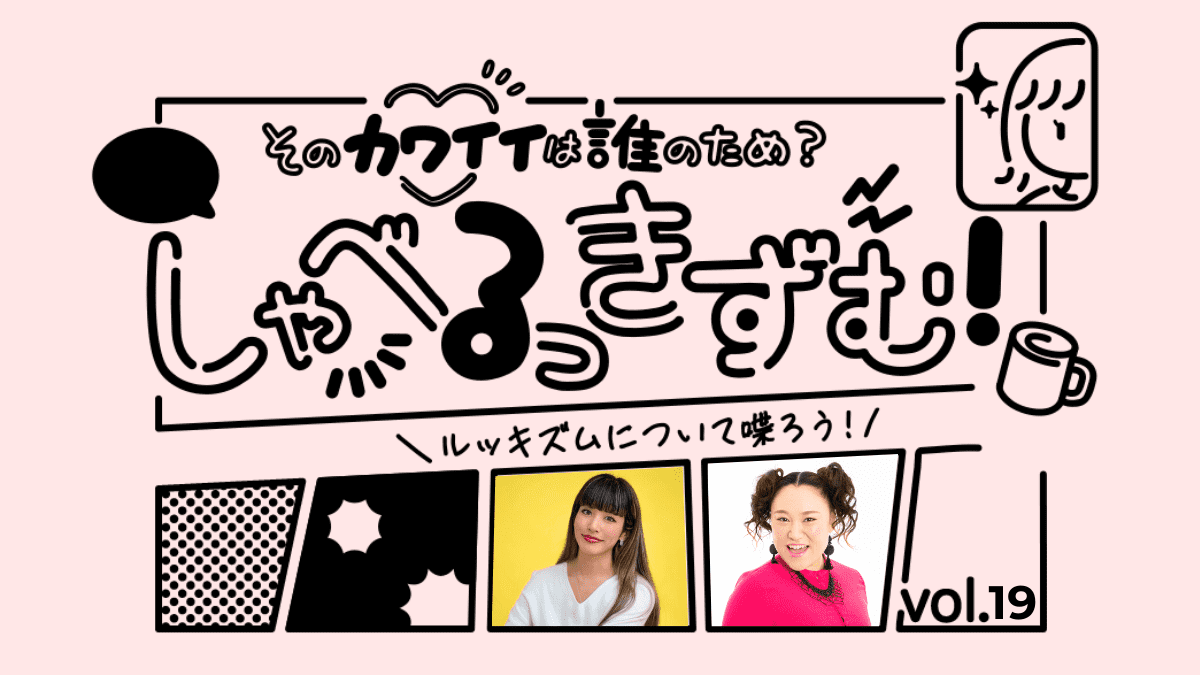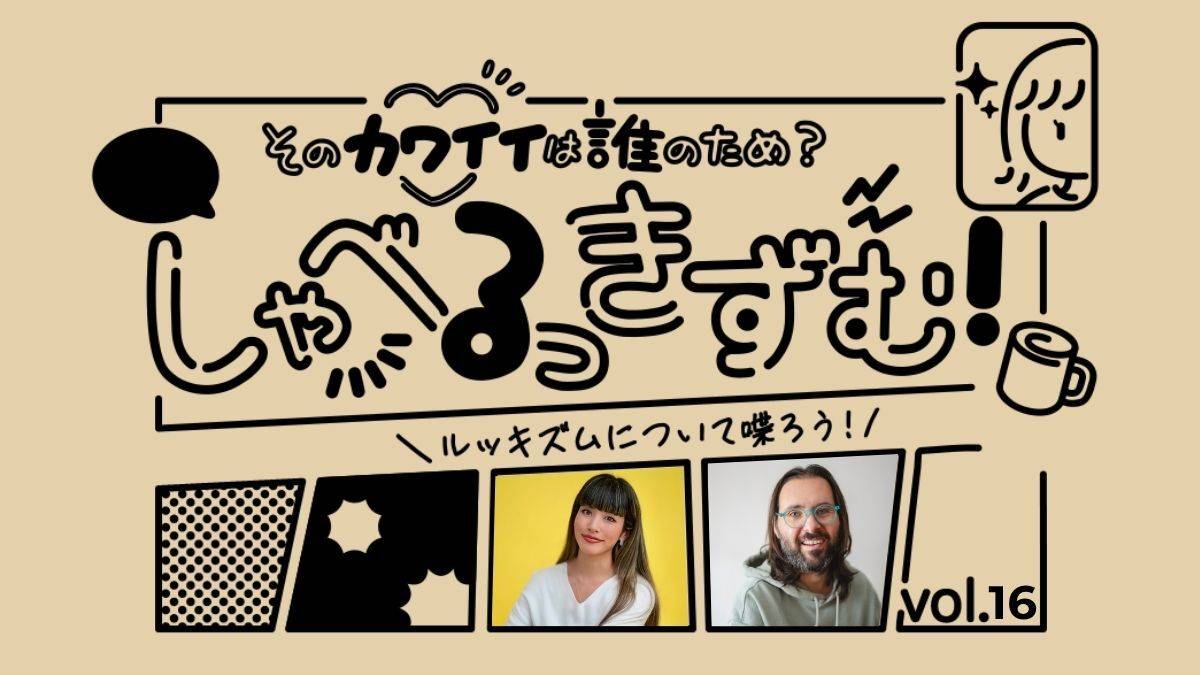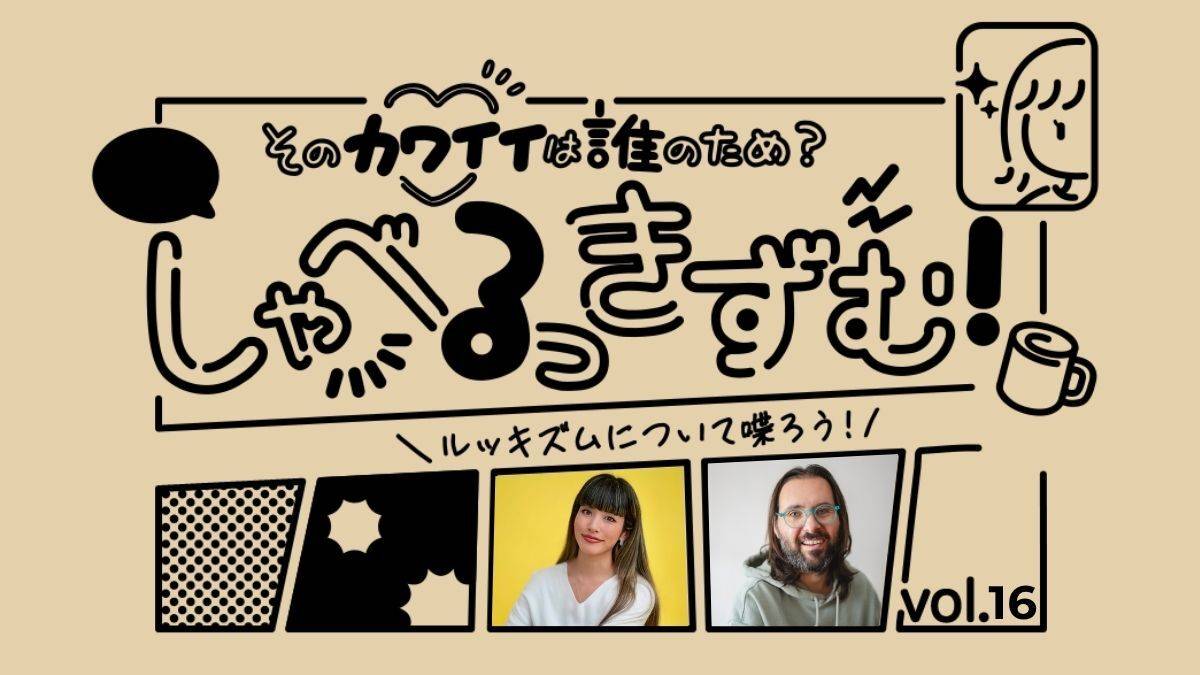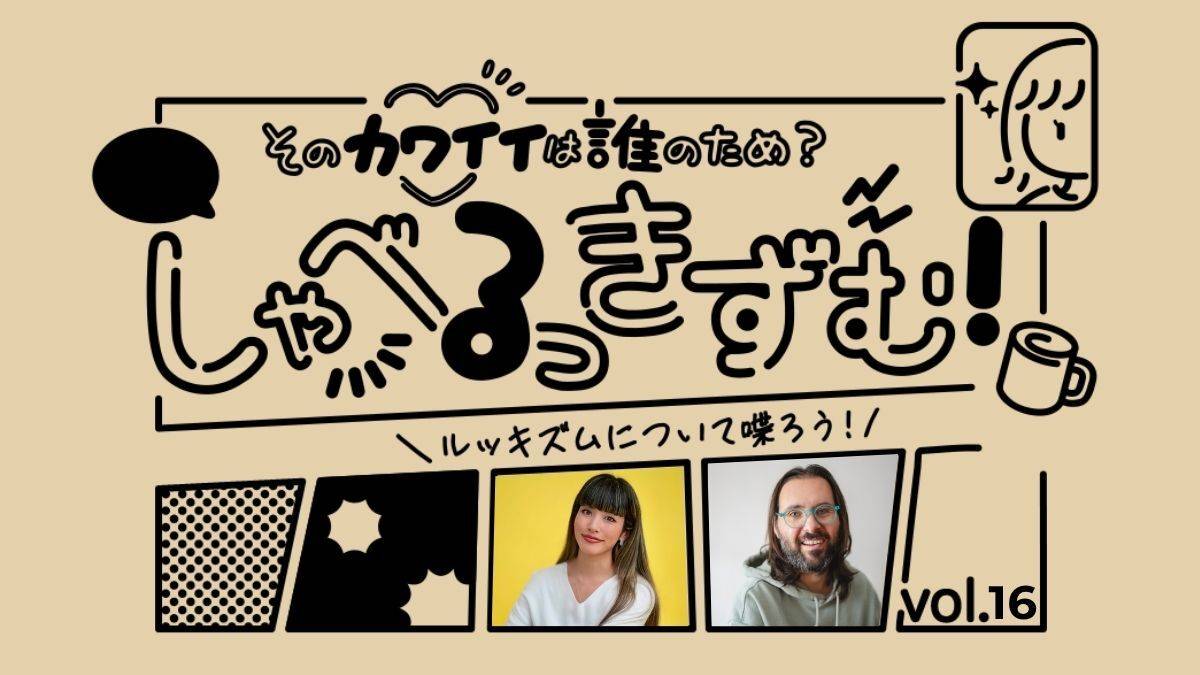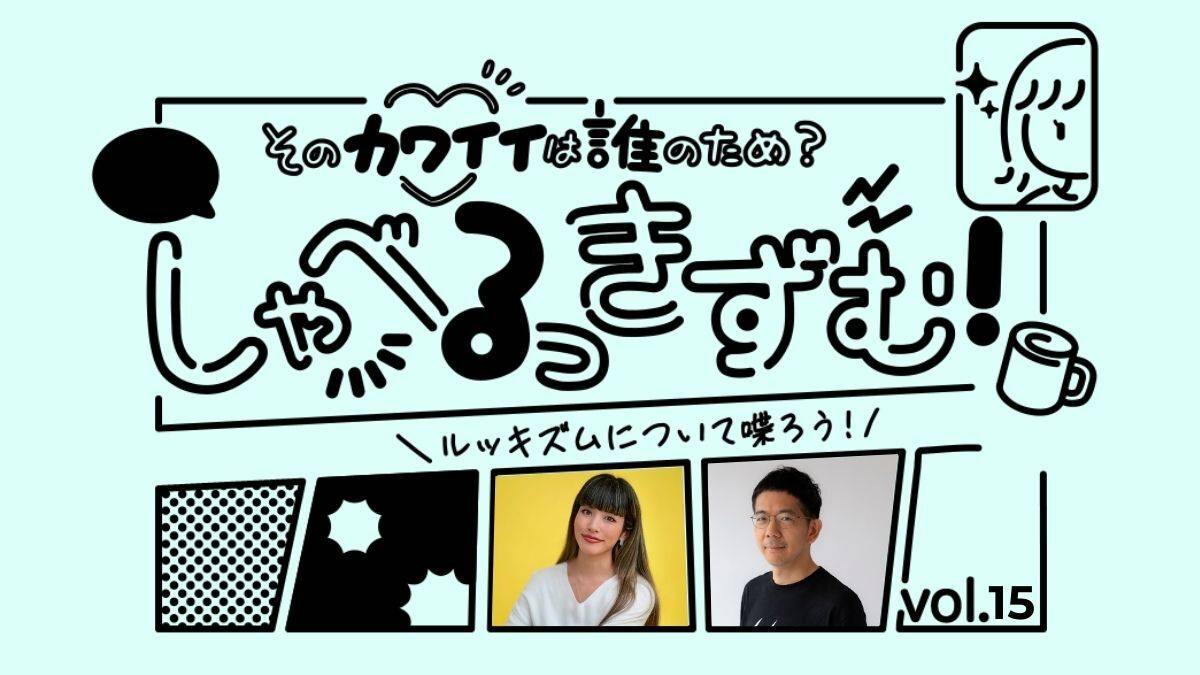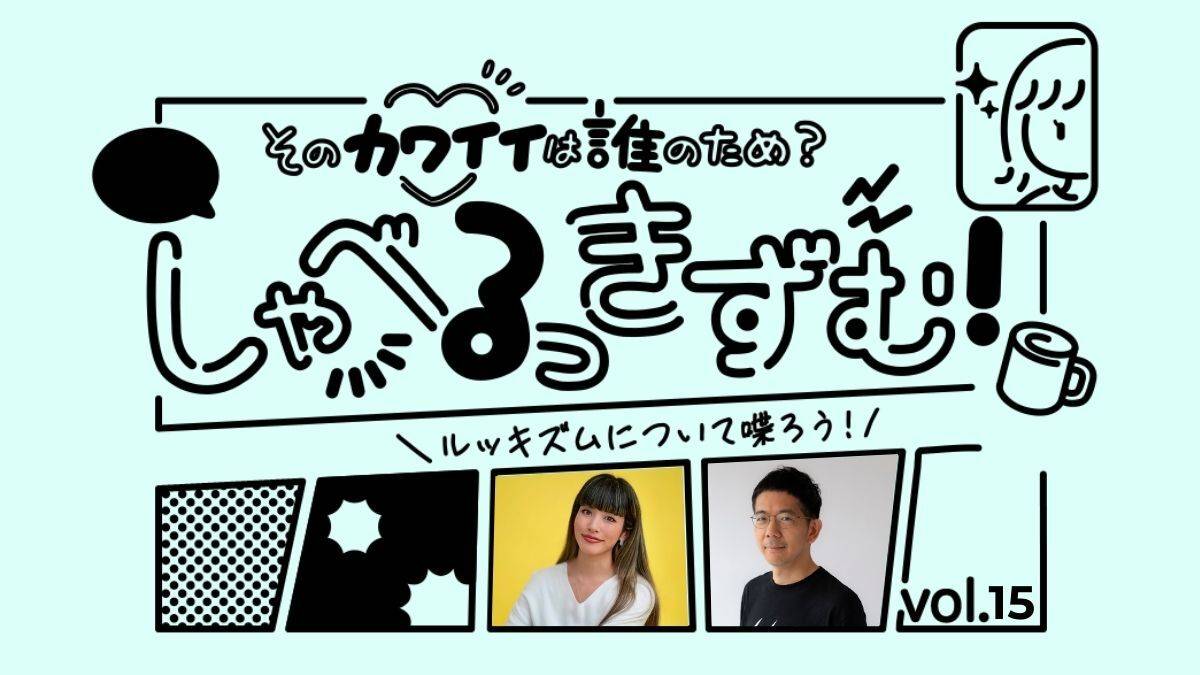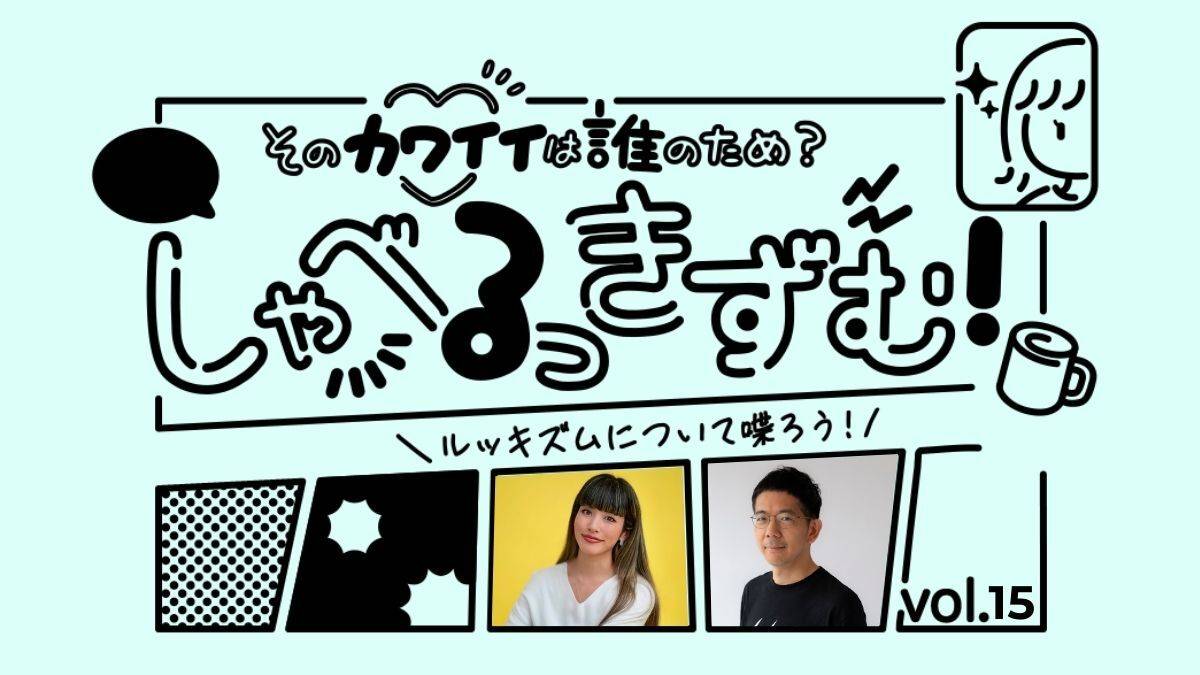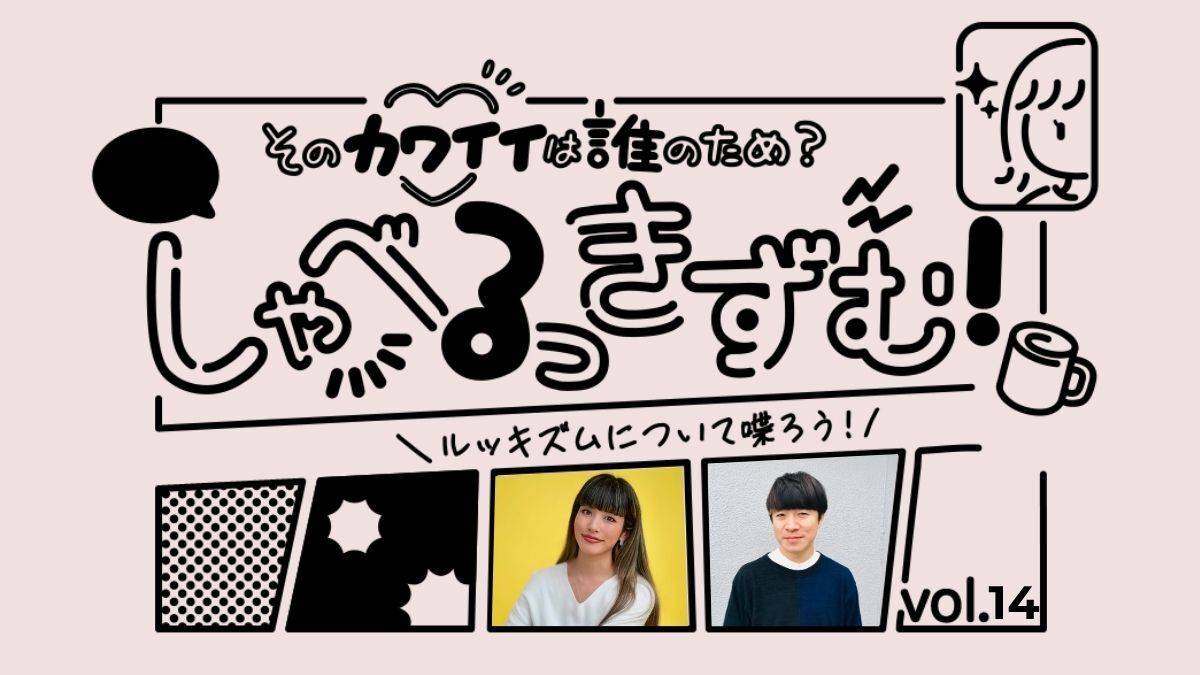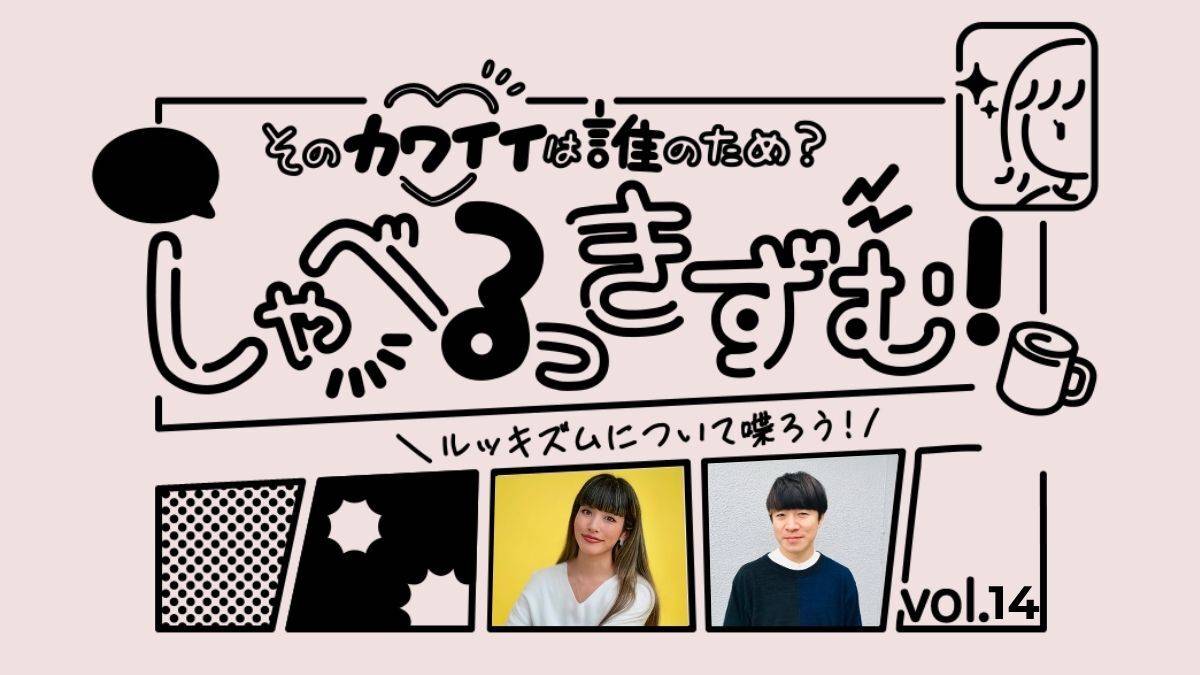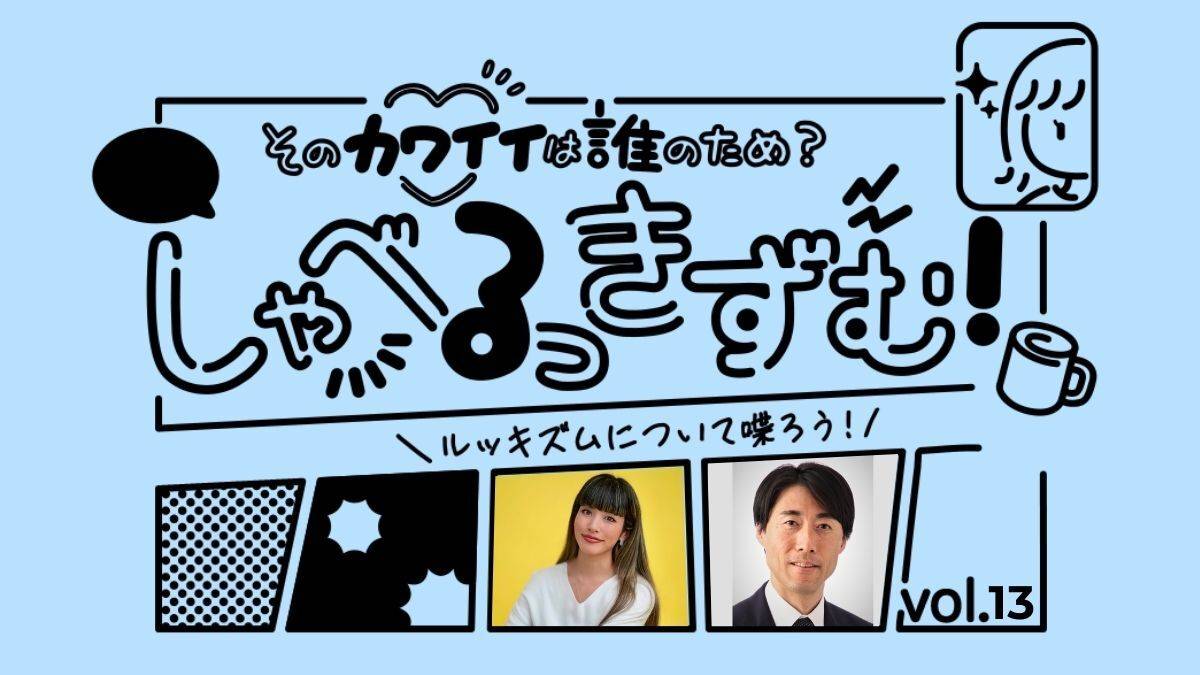しゃべるっきずむ! いろんな「かわいさ」は、まだ描ける 前川裕奈さん×トミヤマユキコさん(2)

容姿で人を判断したり、揶揄したりする「ルッキズム(外見至上主義)」。言葉の認知が進む一方で、まだまだ理解されていないルッキズムについて、おしゃべりしてみよう!自身もルッキズムに苦しめられた経験を持ち、Yoga Journal Onlineで「ルッキズムひとり語り」を執筆する前川裕奈さんとゲストが語り合う連載が「しゃべるっきずむ!」です。
第10回目は、マンガ研究者のトミヤマユキコさんと語る「マンガ×ルッキズム」について。マンガ好きのおふたりの会話から見えてくるのは、「今までそんなふうにマンガを読んだことなかった…!」という分析の嵐!どうしても容姿を描かざるを得ないマンガをとおして、ルッキズムについて考えます。
作画技術の向上で生まれたヒロインたち
前川:かつて、少女マンガのキラキラな主人公と自分を比べていた私としては、ビジュアルがよくも悪くもない普通の子が主人公のマンガって難しいのかな?と思っていたんです。前回の「やりようはある」のお話、トミヤマさんのお考えをぜひ聞かせてください!
トミヤマ:難しさはあります。ただ、「ヒロインが美人じゃないと読む気がしないし、不美人が出てくるマンガは売れない」みたいな言説には「本当に?」と言いたいです。というのも、やはり日本はマンガ大国なだけあって作画技術の向上がすごいんですよ。美しさの表現で言えば、昔はおばあちゃんキャラって“ザ・おばあちゃん”というビジュアルでしたよね。しわやほうれい線がガッツリ入ってて、50代ってこんなにお年寄り感あったっけ……みたいな。
前川:たしかに。一昔前の作画技術だと、年齢の描き方も画一的になってしまってましたもんね。そういえば、『名探偵コナン』の阿笠博士も実は50代前半なんですよね(笑)
トミヤマ:それは、当時はそういう描き方しか知らなかったからなんですよね。今、実は高齢女性がヒロインのマンガが結構あるんですよ。おばあちゃんがBLマンガに出会う『メタモルフォーゼの縁側』や、おばあちゃんが美大に入って映画監督を目指す『海が走るエンドロール』など。これらのヒロインは、ちゃんと加齢こそすれ、過剰なおばあちゃん感がなくてヒロインとしての魅力もちゃんと伝わってきます。
前川:ああ、読みました!『海が走るエンドロール』は、エイジズムをテーマにしてコラムにも書いたのですが、たしかに主人公がおばあちゃんにもかかわらず、共感や応援したくなる素敵な作品でした。

『メタモルフォーゼの縁側』(著:鶴谷 香央理)、『海が走るエンドロール』(著:たらちねジョン)
マンガには、まだまだ期待していいはず
トミヤマ:学園ものでは、やっぱり『スキップとローファー』! 主人公の美津未ちゃんは、美人でもなければ不細工でもない、普通の女の子のビジュアルで描かれていますよね。いわゆる美女じゃないけれど、美津未ちゃんを愛される最高のヒロインたらしめているのも、作家さんのすばらしい作画技術があってこそです。
裕奈:あの作品は、私も本当にすばらしいなと思いました。友達にもいろいろなビジュアルの子がいて、いわゆる美人と言われる子が自分の容姿に悩む描写もありますよね。立場や容姿の違う子たち、それぞれに悩みがあると教えてくれる天才的な作品だなと思いました!アニメの二期も決まって楽しみです。
トミヤマ:しかも、作者は「ルッキズムや社会課題のことを描こうと思いました」と声高に言っているわけじゃないんですよ。地方から東京に出てきた女の子ががんばっている話が描かれているだけなはずなのに、私たちは「美人にも美人の地獄があるわな」とか、そこにルッキズムの問題を見ることができる。

前川:まさに、前回の“読み筋”の話ですね。読み手によって感じ取る内容が変わる……。
トミヤマ:そう。だから、やっぱりまだまだマンガに期待していいと思うんですよね。“魅力的に描く”ことが必ずしも“美しく描く”じゃないことを、提供する側もわかってきていると思うので。私たち読み手も「別にヒロインが王道のビジュアルじゃなくても面白ければ課金しますよ」と言っていくことで、いい感じの共犯関係みたいなものを作れれば、市場が変わっていくと思います。
前川:実際に『海が走るエンドロール』や『スキップとローファー』などが人気になって賞をとったりアニメ化したりしていますもんね。描く側も読む側も、少しずつ変化しているということですね。
トミヤマ:そうそう、ああいう作品が成功例として業界に広まっていくほど、『ビジュアルがすべてじゃないかも』と、後に続く作家さんや作品が増えていくと思います。
ドラクエとアナ雪は、構造がまず違う
前川:すごく希望が持てるお話です。私は少年マンガも大好きなんですけど、今のお話だと少女マンガ・女子マンガのほうが変化が早いかもしれないと思いました。少年マンガだと、「主人公はこんなにかっこいいのに俺は……」とはあんまりならない気がするんですが、どうなんでしょうか?
トミヤマ:少女マンガ・女子マンガは「共感」を大事にしているからこそ、読んでいる人が「それに引き換え私は……」みたいに考えちゃうのかな。そういう読者がいることを想定しながら、比較して落ち込むんじゃなく、むしろ「私みたいな人がいる!」と前向きに共感してもらえる作品にしていけるといいですよね。少年マンガは、まず作品の設計自体が違う部分があるかもしれない。
前川:たしかに、『ブスなんて言わないで』のなかでも、男性と女性で同じ恋愛マンガを読んでも楽しみ方の違いがあると言及されていました。恋愛マンガ以外でも、そもそもの構成が違うのかもしれない。
トミヤマ:大学の授業でお話しすることもあるのが、古今東西の物語の分析から見える基本的な型「男性神話・女性神話」。簡単に言えば、男性神話はドラクエ型で自分を鍛えて何かを成し遂げて帰還するストーリーですね。一方で女性神話は、自分の本当の居場所を探して葛藤する型で、『アナと雪の女王』なんかはまさにその典型です。
前川:へえ!そんなふうに作品を見たことなかったからおもしろいです!もちろん、私みたいに女性で少年マンガが好きな人もたくさんいるわけなので、必ずしも「女性だからドラクエ型は理解できない」というわけではなく、単純にカテゴリーの違いですね。
トミヤマ:そうそう。もちろん、男性を主人公にした女性的な話もあるし、女の子が冒険して何かを成し遂げて帰ってくる話を描いてもいい。ただ、そういった傾向と、少女マンガと少年マンガで「読者が自分と比較しがちかどうか」は関係があるのかもと思います。
裕奈:なるほど。現実社会も似ているところがありますよね。男性は離職率が低くて常に『上を目指すべき』という圧がある。女性のほうが自分と妻や母といった別の顔のなかで内なる葛藤に向き合う人が多いのかなと思ったりしました。共感したり比べたりしやすい点では、少女マンガが与える影響はやはり大きいんだろうなと感じます。
『りぼん』のかわいさ、『なかよし』のかわいさ

トミヤマ:女性が女性向けのマンガを読むとシンクロ率が高すぎるので、比べて凹んじゃうとか、呪いになっちゃう人もいるんだろうなと思います。だからこそ、私は『少女マンガのブサイク女子考』で、作家さんたちがその呪いに抗おうとした形跡を残しておきたかったんですね。
前川:「ブサイクヒロイン」たちを集めたマンガ批評本ですよね。私も読んだことがない過去の作品なども収録してあって興味深かったです!紹介されている『イグアナの娘』は、実写ドラマを見ていたのですが、当時はまだ7歳とかだったので「ブサイク」やルッキズムの呪いに紐づいた見方は全くできていなかったな、と。この本に収録されているのを見て、改めてその視点でマンガを読み直しました。
トミヤマ:マンガを売らなきゃいけないと考えると、いきなり王道からは外れるのは難しい。けれど、「このままでいいんだろうか」と考えている人もすごく多いと思うんです。作家のみなさんも自由に描ける人は少なくて、媒体によって特定の絵柄を求められることもありますからね。
前川:そうですよね。マンガを描く側のみなさんにも、葛藤があるんだろうな……。
トミヤマ:以前、子育てメディアでも伝えたのは「いろいろな少女マンガを読ませてほしい」ということ。『りぼん』だけ読ませるんじゃなくて『なかよし』や『ちゃお』やそれ以外のいろんな作風のマンガを読ませてあげてほしい。そうすると、美しさの描かれ方ひとつとっても、一概には言えないんだなと感じることができるんじゃないかなと思います。
前川:それこそ、『少女マンガのブサイク女子考』に載っているようなブサイクヒロインのマンガが、他のマンガと一緒に置いてあるだけで視野が広がるのかもしれないですね。
トミヤマ:そうそう、偶然の出会いが重要だったりもしますからね。少女マンガすべてが害だというよりは、いろんな少女マンガを本棚に置いておいておくだけでもマンガから受け取るものは全然違うのかなと思いますね。
前川:なるほど。もともと幅広く読んできましたが、もっとたくさんの種類のマンガを読みたくなってきました。
トミヤマ:あ、あと美男美女が出てくるマンガの話をすると……。

*次回、あの作品にも、この作品にも……実は多様性が隠れていた。 3本目「多様性や配慮のあるマンガは“おもしろくない”?」は、こちらから。
トミヤマユキコさん
1979年生まれ。早稲田大学法学部を卒業後、同大大学院文学研究科に進みマンガ研究で博士(文学)を取得。2019年4月から東北芸術工科大学教員に。ライターとして日本の文学、マンガ、フードカルチャーなどについて書く一方、大学では現代文学・マンガについての講義や創作指導も担当。2021年より手塚治虫文化章賞選考委員。著書に『10代の悩みに効くマンガ、あります!』(岩波ジュニア新書)、『文庫版 大学1年生の歩き方』(集英社文庫)、『少女マンガのブサイク女子考』(左右社)、『40歳までにオシャレになりたい!』(扶桑社)、『パンケーキ・ノート』(リトルモア)などがある。
前川裕奈さん
慶應義塾大学法学部卒。民間企業に勤務後、早稲田大学大学院にて国際関係学の修士号を取得。独立行政法人JICAでの仕事を通してスリランカに出会う。後に外務省の専門調査員としてスリランカに駐在。2019年8月にセルフラブをテーマとした、フィットネスウェアブランド「kelluna.」を起業し代表に就任。ブランドを通して、日本のルッキズム問題を発信。現在は、日本とスリランカを行き来しながらkelluna.を運営するほか、「ジェンダー」「ルッキズム」などについて企業や学校などで講演を行う。著書に『そのカワイイは誰のため?ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話』(イカロス出版)。yoga jouranal onlineコラム「ルッキズムひとり語り」。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く