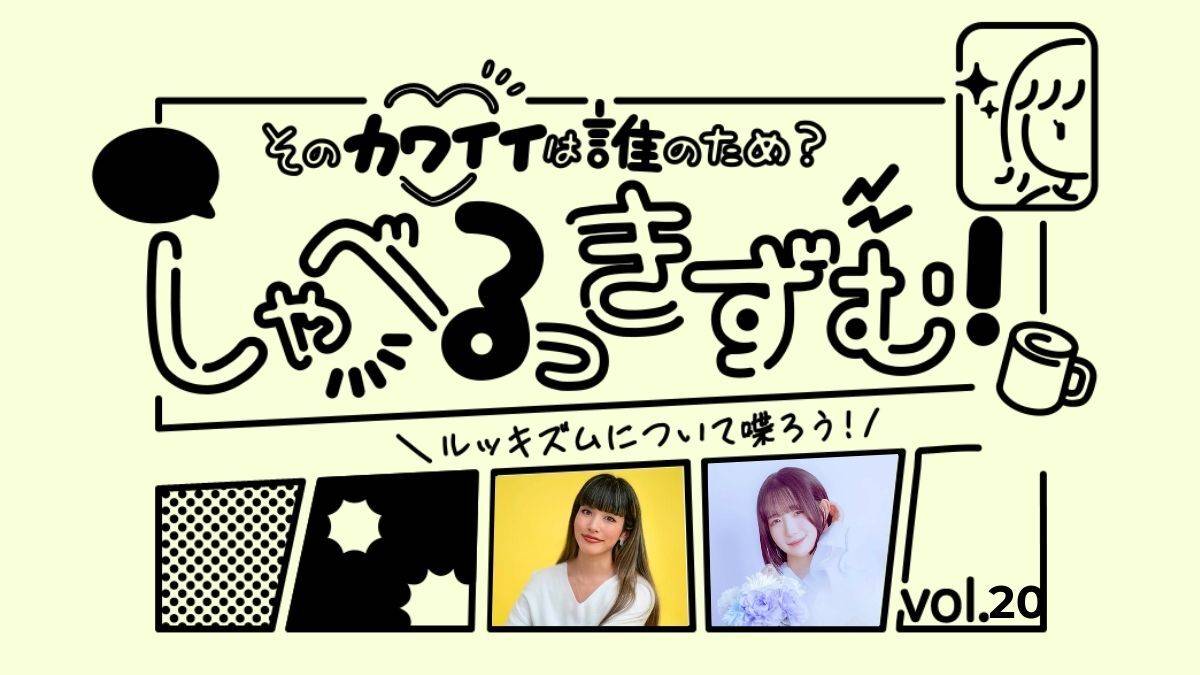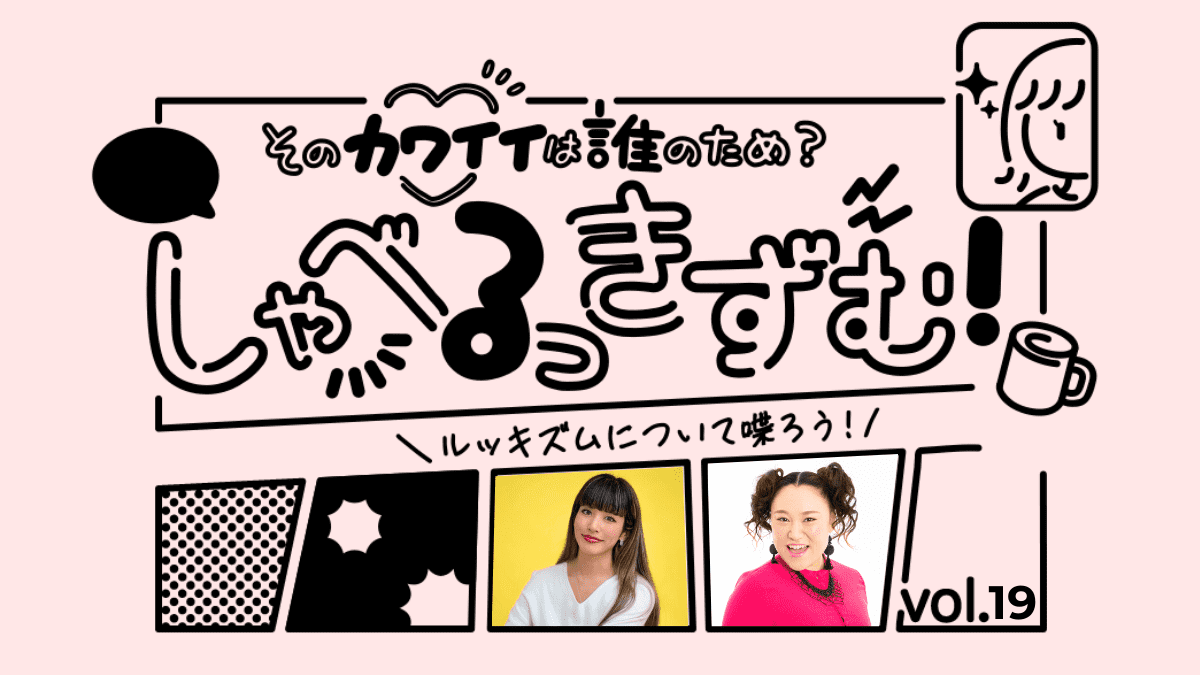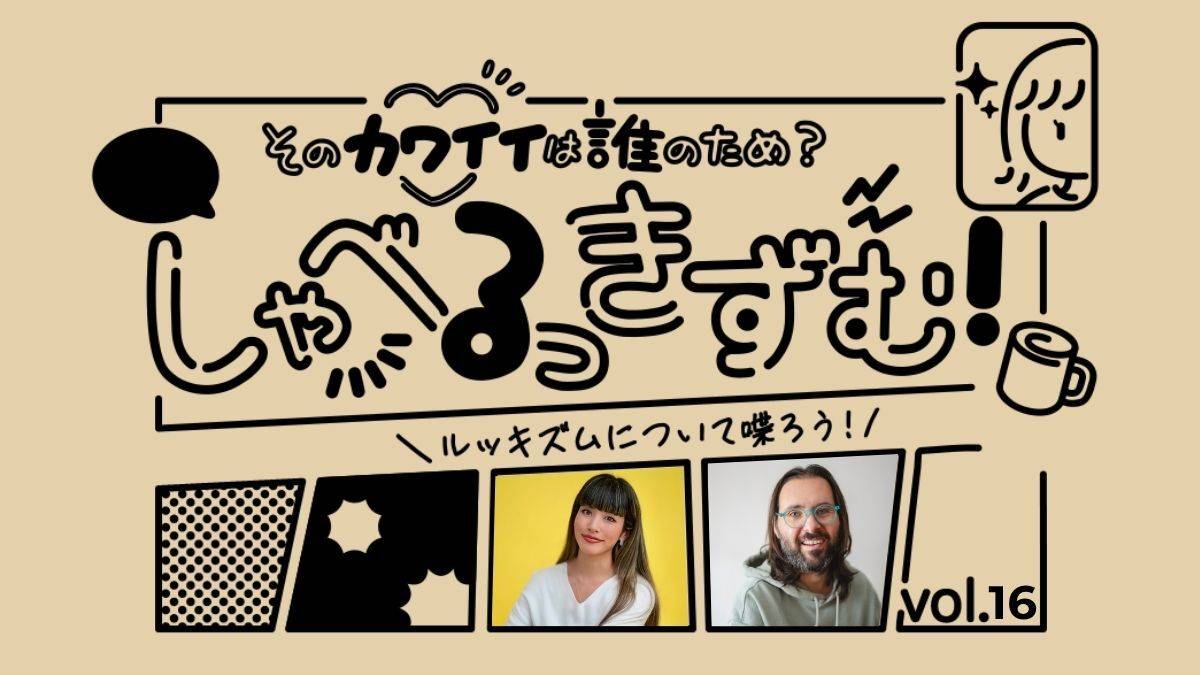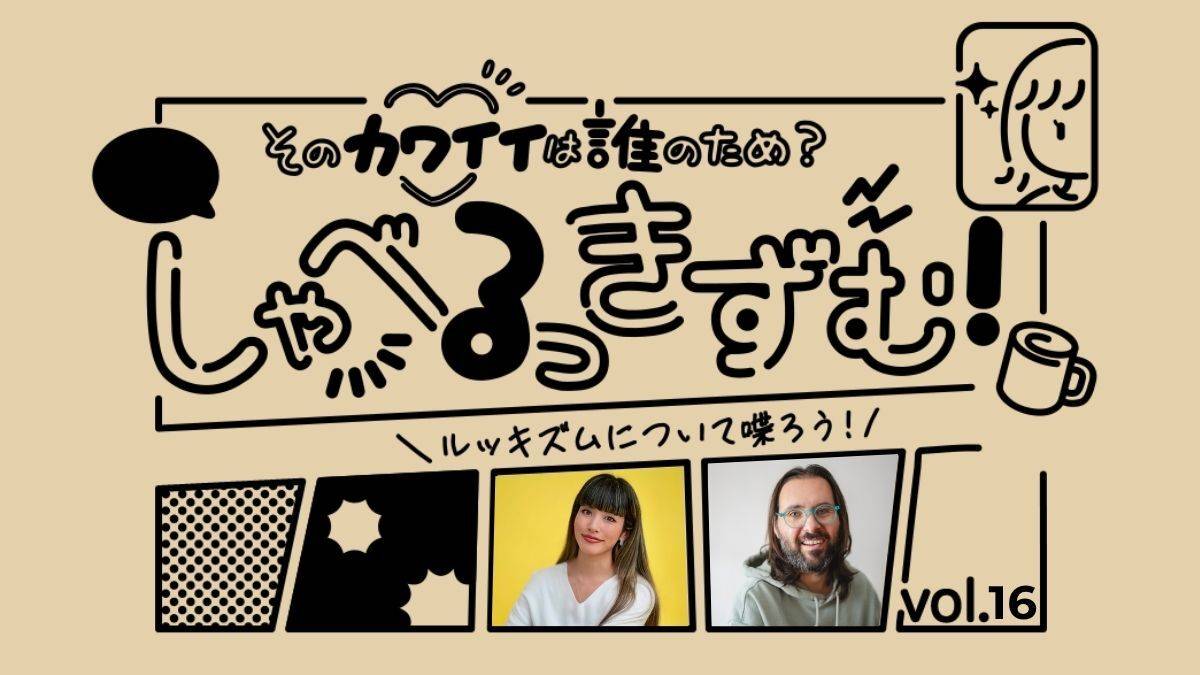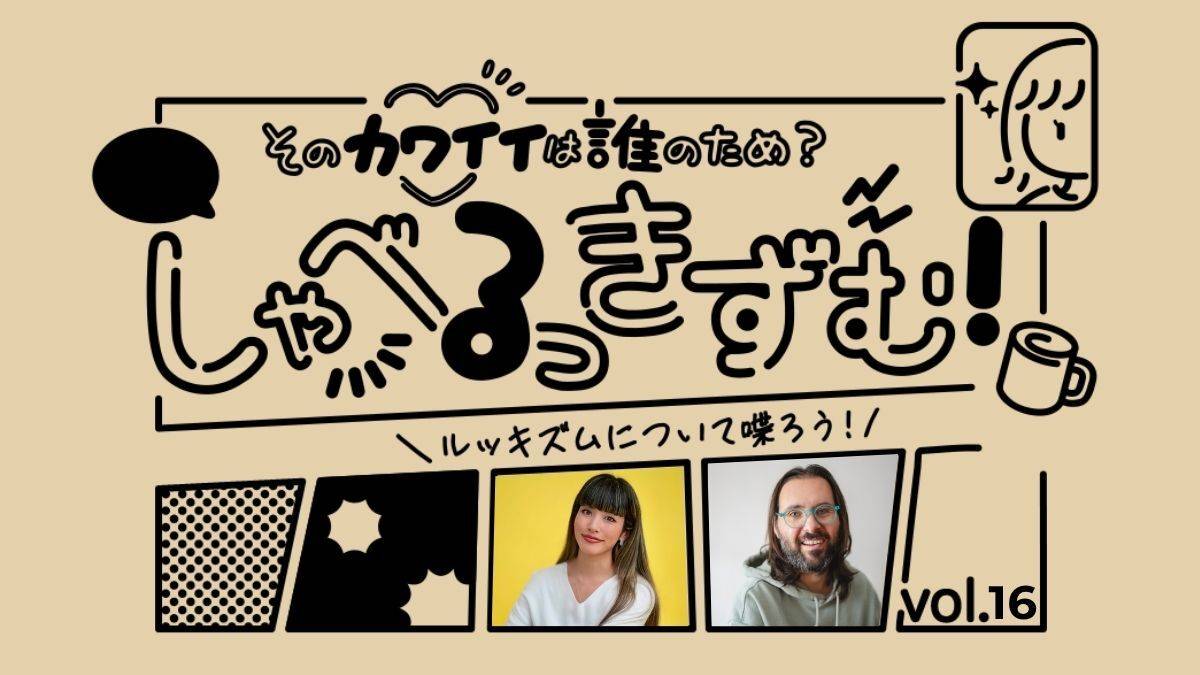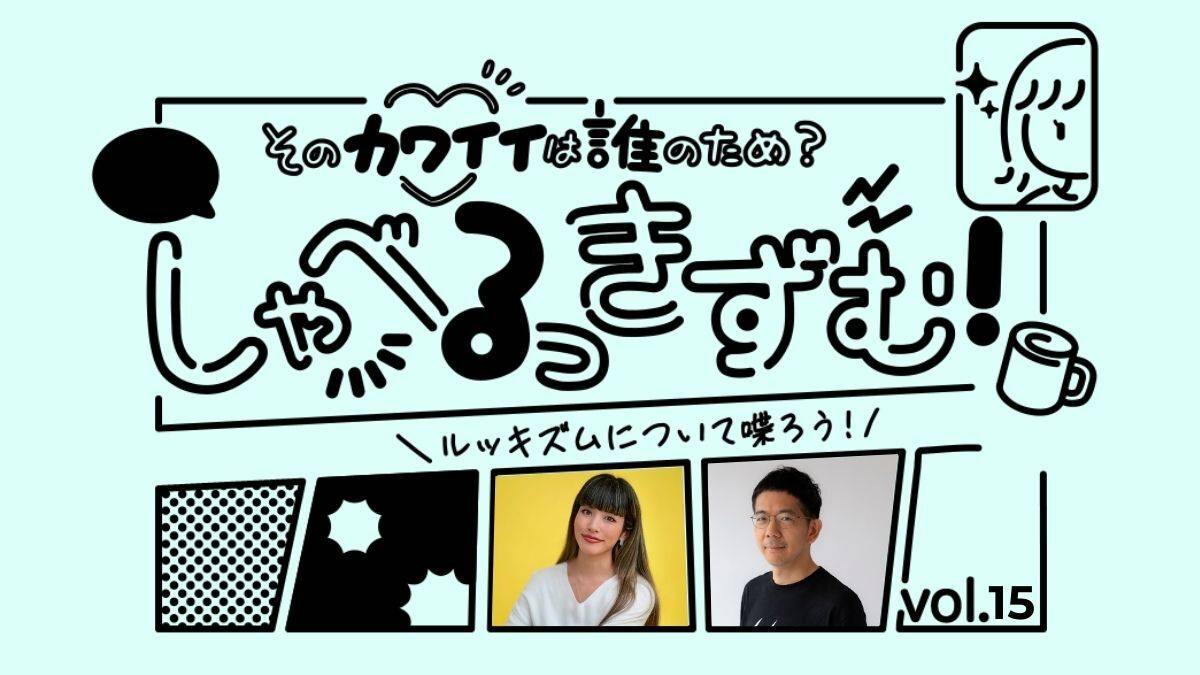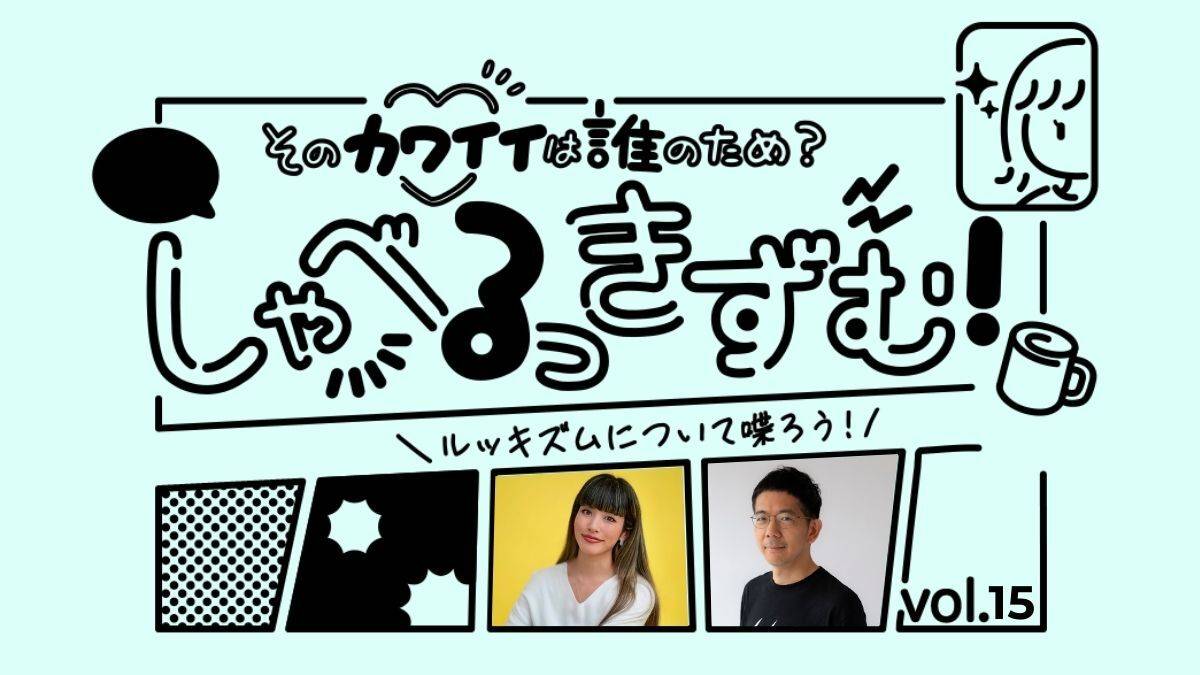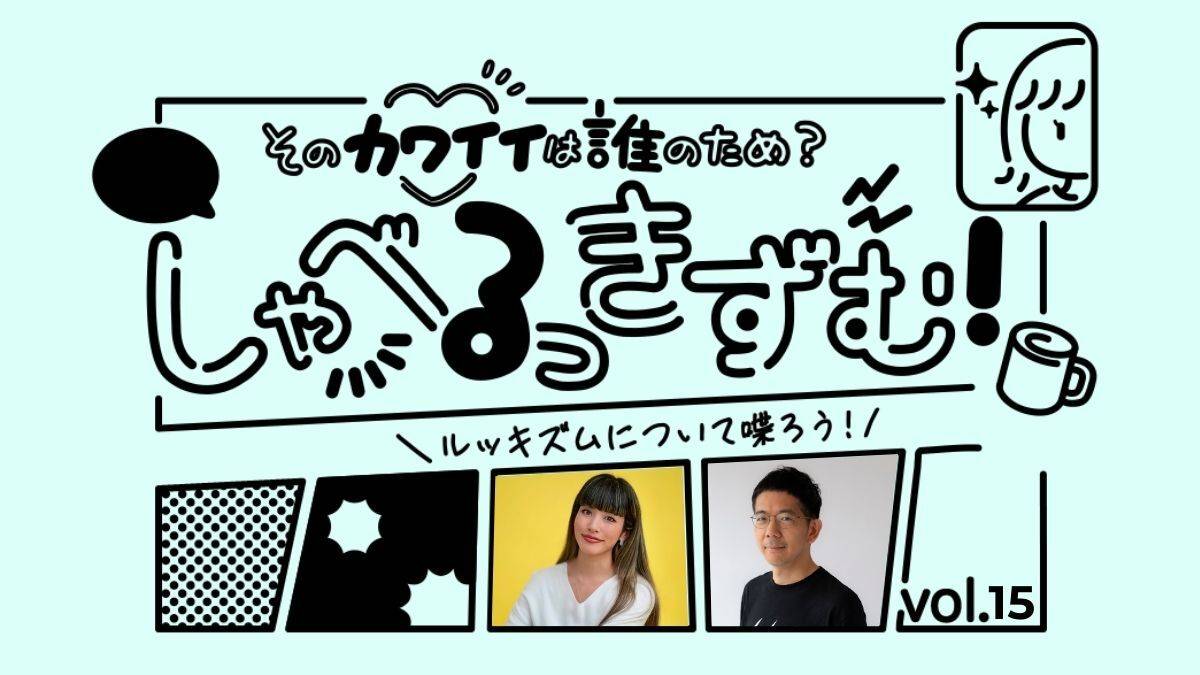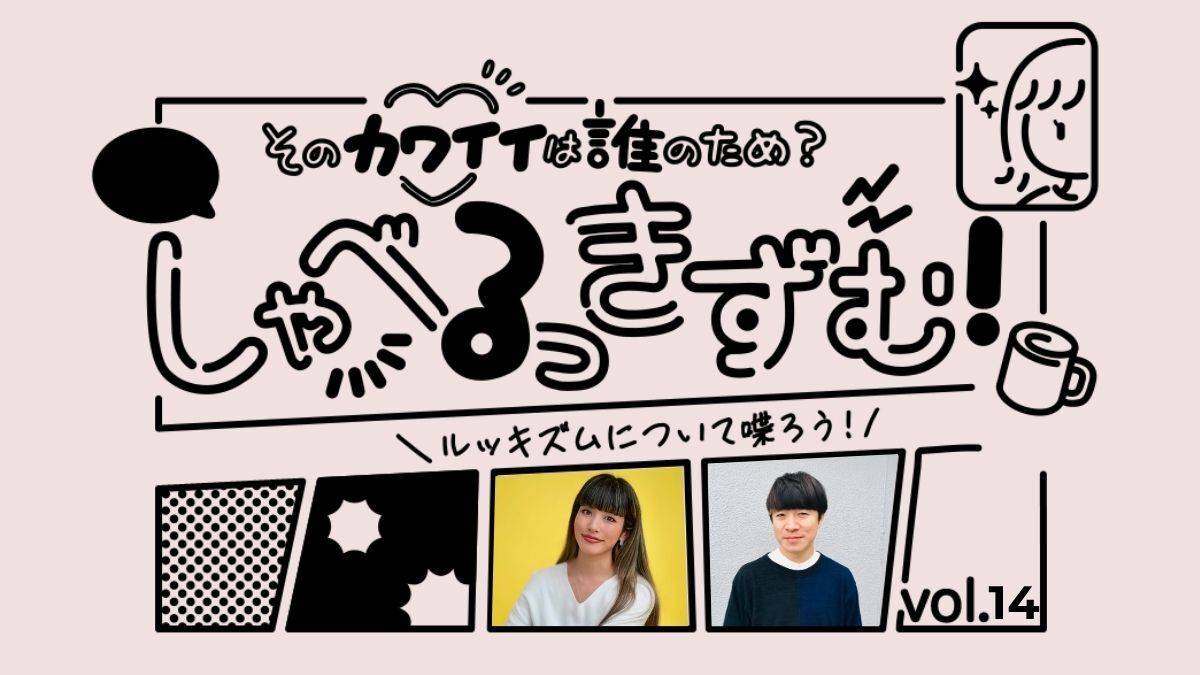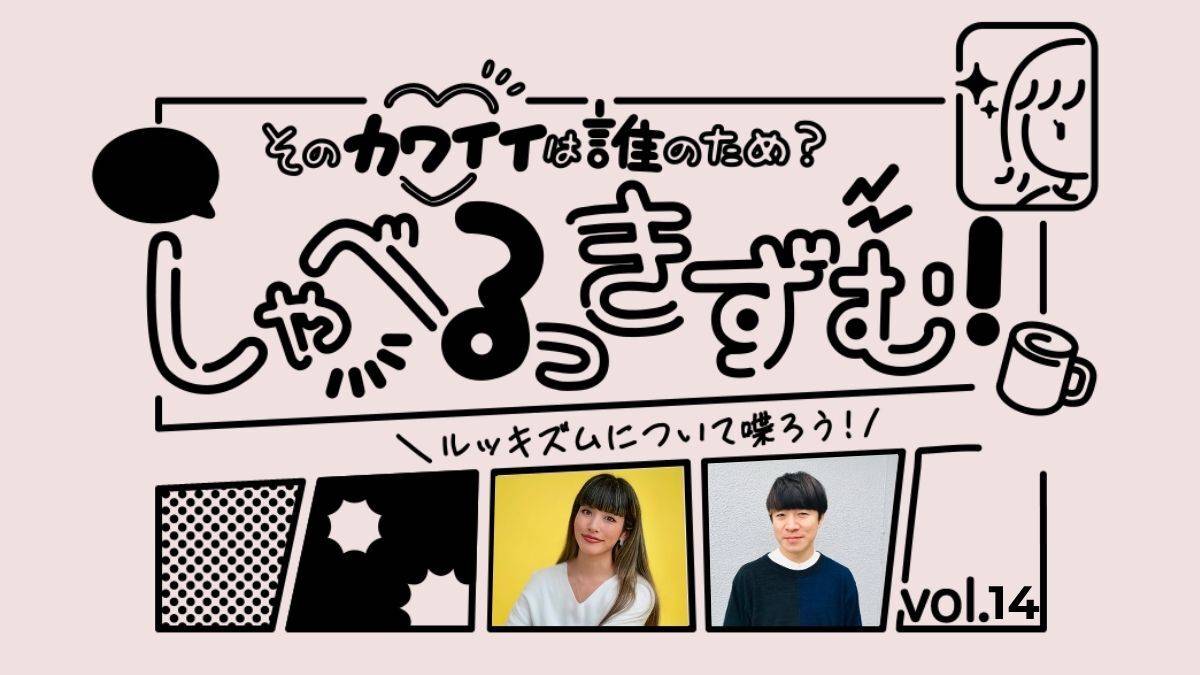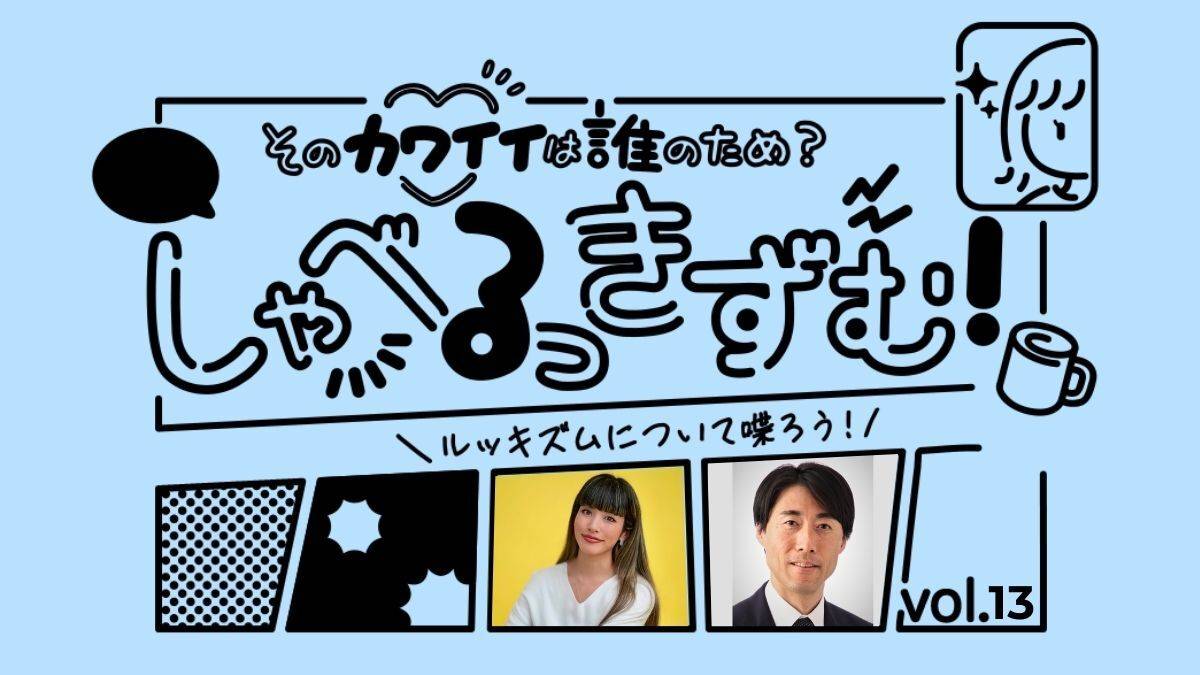しゃべるっきずむ! “文章”で社会課題を伝える挑戦と葛藤と希望 前川裕奈さん×宇井彩野さん(1)

容姿で人を判断したり、揶揄したりする「ルッキズム(外見至上主義)」。言葉の認知が進む一方で、まだまだ理解されていないルッキズムについて、おしゃべりしてみよう!自身もルッキズムに苦しめられた経験を持ち、Yoga Journal Onlineで「ルッキズムひとり語り」を執筆する前川裕奈さんとゲストが語り合う連載が「しゃべるっきずむ!」です。
第12回目は、第5回氷室冴子青春文学賞大賞を受賞した『愛ちゃんのモテる人生』(河出書房新社)著者の宇井彩野さんをゲストにお迎えしました。シスジェンダーでゲイの男の子、愛ちゃんの恋愛模様を追いかけながら社会全体が見えてくる本書。前編は、文章という形で社会問題を扱う難しさや意義について話します。
社会課題×フィクションの可能性
前川:宇井さんが書かれた『愛ちゃんのモテる人生』、本屋で惹かれて拝読しました。愛ちゃんを始めとしたセクシャルマイノリティのさまざまな日常の場面が描かれているだけでなく、性的搾取やネグレクトを含む社会課題をフィクションに盛り込んでいるところが、とても興味深かったです。
宇井:ありがとうございます。
前川:ルッキズムに関しても、主題ではないものの書き方に配慮を感じる部分が多くて、宇井さんに思わずDMで感想を送らせていただいたんですよね。第5回氷室冴子青春文学賞大賞を受賞されていると知ったのは拝読した後でしたが、納得の内容でした。
宇井:そう言っていただけると嬉しいです。もともと小説はずっと書いていたのですが、受賞という形での出版は今回が初めてでした。主人公・愛ちゃんにはモデルとなった海外の俳優さんがいまして、フェミニンな雰囲気でクィア(性的マイノリティの総称・連帯を表す言葉)な表現をする男性が素敵だなと思って、そういう子が主人公の本を書きたいと構想が膨らみました。

毎日好きな恰好をして通学してたら、わざわざゲイだと言わなくてもなんとなく「LGBTの人」として受け入れられるようになっていて、(中略)僕の場合は、男子にしてはちょっとフェミニンだったり、気に入ったアイテムならレディース服も取り入れたりとか、その程度のものだ。(『愛ちゃんのモテる人生』P22より)
前川:読んでいて、自分と属性の違う子の話を書くのってすごく難しそうだなと思いました。
宇井:私自身が当事者でもあるので、割とジェンダーやクィアの話は身近な体験も含まれていたりします。ただ、ゲイコミュニティのことは私も知らない部分があったので、調べて執筆していましたね。
文章で伝えることの難しさと葛藤
前川:ジェンダーやセクシャルマイノリティの話、特に『愛ちゃんのモテる人生』で取り上げられているものの中にはデリケートなものもあると思うんですが、文章として表すときの難しさはありましたか。私が『そのカワイイは誰のため? ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話』(イカロス出版)を書いたとき、初めての著書だったこともあってすごく大変だった記憶があるんです。同じ「伝える手法」でも、文字、絵、喋り言葉、それぞれの役割があると思っていて。その中で、文字(文章)は会話や喋り言葉と違って、最終的には受け手の解釈がこちらには見えないというか。発している単語の強弱や温度感も文字では表現しづらい分、意図せず誰かを傷つけないか、いろいろ考えながら言葉を選ぶ経験になったんですよね。
宇井:難しさはありますよね。おっしゃるとおり、自分の意図とは別の解釈で受け取られてしまうこともありますし。例えば、愛ちゃんはシスジェンダー(生まれたときに診断された性と、自身のアイデンティティの性別が一致していること)で、ゲイ(同性に対して性的に惹かれたり恋愛感情を抱く指向)であると書いても、「トランスジェンダー」と言い間違えられた感想もありました。文脈や前提がしっかり伝わるように試行錯誤して書く必要性を感じましたね。
前川:ですよね。私も著書のなかで最大限わかりやすくルッキズムについて書いたつもりです。幸いにも大半の人には意図した通り、もしくはそれ以上で届いたと実感していますが、一定数の誤解したコメントを目にすることもあります。文章を生業にしている宇井さんでも、そこの難しさはあるんですね……。
宇井:なかには、私からするとセクシャルマイノリティに対する誤解や差別的な表現が無自覚で含まれる感想もあって。作品がそういった言葉が出るきっかけになってしまっている葛藤はありますね。ただ、そこを切り拓いていかないと、広まっていかないとも思うので……。
前川:わかります。思っていた反応ではなくても「考えるきっかけや時間」には必ずなっているとは思うんですよね。ジェンダーやルッキズムなどの社会課題を文章や作品にする難しさも感じつつ、やはり意義があることだと信じています。

「かわいい」と言いながらも違和感のない、ルッキズムへの配慮
前川:『愛ちゃんのモテる人生』は、なるべく解釈違いを起こさないような書き方がされていてわかりやすいと感じました。特に、ルッキズムへの配慮を感じたのが「かわいい」や「モテる」などという表現。私たちの本の題名には、それぞれ「かわいい」「モテる」という、ある意味ルッキズムに一番直結しそうな単語を使ってますよね。文中にもそれらが出てきたときも、違和感なく読めたんです。
宇井:ありがとうございます。「かわいい」と言う場面では、世間一般の美の基準では書いていないつもりです。登場人物それぞれの主観で「かわいい」と言っているだけ、という。
前川:そう!「流行りの髪型をしてるからかわいい」みたいな言葉ではないんですよね。例えば、愛ちゃんが個性的なTシャツを着ている人を「おしゃれ」と言うシーンでは、その服装ではなくてそれを着ている人の態度が「おしゃれ」なんだよ、という彼の価値観を感じました。
〈ファッショナブル〉
シンプルな白いTシャツに、黒く太い創英角ポップ体で、そう書かれている(中略)
「……ファッショナブルだ……」思わず声が漏れた。彼は、なんて堂々と、ファッショナブルなんだろう。僕はどうしていつの間にか、自分を見失っていたんだろう。(『愛ちゃんのモテる人生』P42より)
宇井:ルッキズムに関しては、表紙の絵にもこだわっていて。ご自身もノンバイナリーである漫画家の山内尚さんに「世間の美醜の基準で捉えられないようなものにしてほしい」とお願いして、いただいた絵を見たときにこれなら!というものを採用しました。
前川:ルッキズムの話をするときって、「美しい/不細工」の二元論になりがちなので、そのグラデーションをイラストで表現するのは難しかったのではと感じていました。この表紙、すごくいいですよね!この表紙も本屋で手に取りたくなった要素のひとつだと思います。
宇井:そうですよね。イラストは基本的に美化して描くことが多いので、一般的な美形じゃない人を描くのは難しいと思うのですが、山内さんの絵柄がとてもよく合ったんだと思います。『そのカワ』の表紙は、スリランカを背景にした前川さん自身の写真ですよね。
前川:実は、『そのカワ』もイラストにするか、文字だけにするか、写真をいれるか結構悩みました。私自身のエッセイであることや、写真をいれることで、「この人がルッキズムを問題視している本人なんだ」「いっけん悩みはなさそうだけど、どれどれ?」「“見た目問題”のある人やプラスサイズではないのにルッキズム!?」といろいろと解釈を広げることができるかな、と思ったのです。

脇役でも道化でもない、ハッピーエンドが書きたかった
前川:「モテる」という言葉も印象的ですよね。タイトルの『愛ちゃんのモテる人生』は、どういう経緯で決まったんですか?
宇井:最初に作品のアイディアがひらめいたときから、このタイトルは結構バシッと決まっていましたね。愛ちゃんのようなフェミニンな個性を前面に出しているゲイの子って、オネエキャラでいじられたり、色物的な立ち位置にさせられることが多いんです。そういう扱いをされがちな子を、ちゃんと好きだと言ってくれる人が現れる話を書きたかった。脇役の悲しい役や道化役ではなく、ちゃんと主役でハッピーになれる物語を、と考えたときにこのタイトルが浮かんできたんです。
「……なんかね。僕もそうだけど、マイノリティの子たちって、焦っちゃうとこあるじゃん。ほんとに自分のこと好きになってくれる人なんて現れるのかな、とかって。」(『愛ちゃんのモテる人生』P21より)

宇井:『そのカワイイは誰のため? ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話』のタイトルも、最初から決まっていたんですか?
前川:いえ、こちらは編集者さんと相談して最後に決めました。私と編集者さんとのやりとりで、いつも結局行き着くのが「それって誰のためになんだっけ?」という軸の部分だったので、それがそのままタイトルになりましたね。
宇井:なるほど、そうだったんですね。
前川:ただ、文章で伝える難しさもあって、例えば本文中で「色白の〇〇ちゃんが人気だ」「華奢なXXさんは何を着ても似合う」とか書いてしまうと、逆に一般的な美の基準を認識させてしまうことにもなるんじゃないかと思うんです。今まで色黒で悩んでいなかった誰かが、その文章を見ることで「あれ、色白の方が“正解”ってこと?」と悩み始めてしまうかもしれないですよね。
宇井:それで言うと、愛ちゃんはファッションのことはたくさん書いたんですが、具体的な容姿については書かないというのを徹底していたかもしれません。
前川:やっぱりそうですよね、それは本を読んでいてもとても感じました。それが文章や小説の良いところですよね。現実世界でも形容詞を使うときは気をつけないといけないけれど、反射的に出てしまうものもあるので。そして、たしかにファッションについてはかなり具体的にコーデが書いてありました。ファッションに関して、宇井さんに聞いてみたいことがあって……。
*次回、ファッションで判断されるのはルッキズム?「自分らしさ」の範囲はどこまで? 2本目「愛ちゃんから学ぶ、自分を大切にする言葉たち」は、こちらから。

Profile
宇井彩野さん
1985年、千葉県生まれ。学習院大学文学部卒。大学時代から文芸サークルにて詩や小説を書き始める。カトリック系団体の記者として就職後、適応障害を発症し退職。一年半の闘病生活の後、パートタイムの事務職をしながらフリーライターや作詞家修行、個人出版業などを経て、2023年、『愛ちゃんのモテる人生』で第5回氷室冴子青春文学賞大賞を受賞。本書がデビュー作となる。
前川裕奈さん
慶應義塾大学法学部卒。民間企業に勤務後、早稲田大学大学院にて国際関係学の修士号を取得。独立行政法人JICAでの仕事を通してスリランカに出会う。後に外務省の専門調査員としてスリランカに駐在。2019年8月にセルフラブをテーマとした、フィットネスウェアブランド「kelluna.」を起業し代表に就任。ブランドを通して、日本のルッキズム問題を発信。現在は、日本とスリランカを行き来しながらkelluna.を運営するほか、「ジェンダー」「ルッキズム」などについて企業や学校などで講演を行う。著書に『そのカワイイは誰のため?ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話』(イカロス出版)。yoga jouranal onlineコラム「ルッキズムひとり語り」。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く