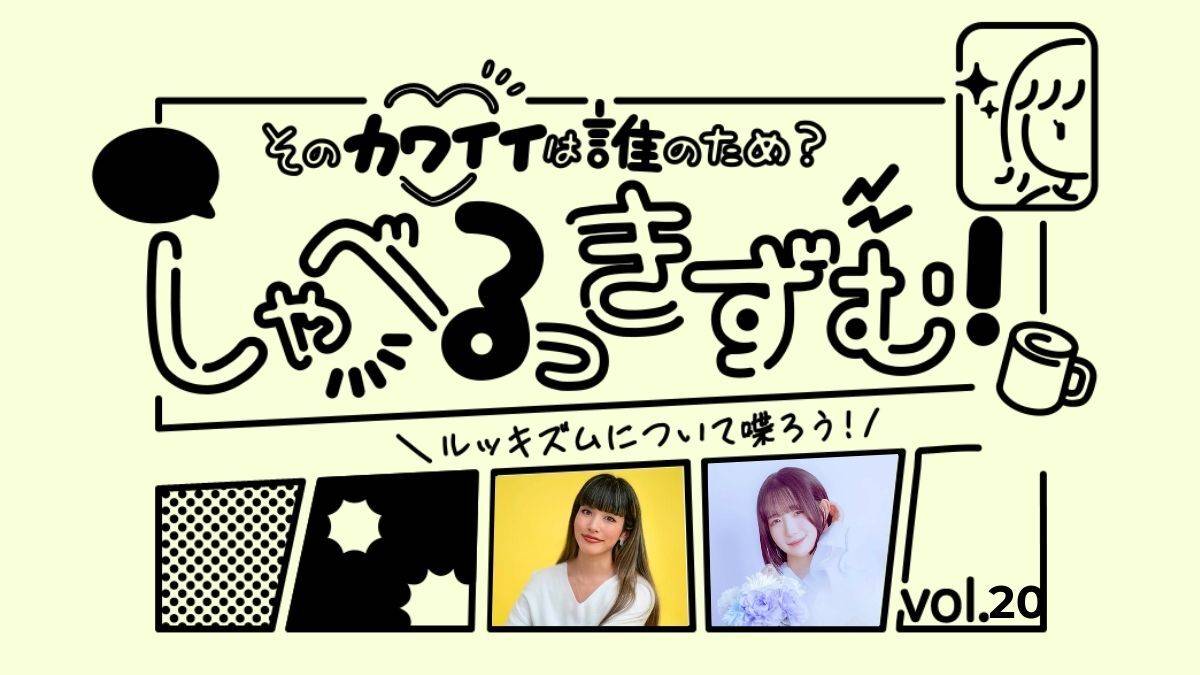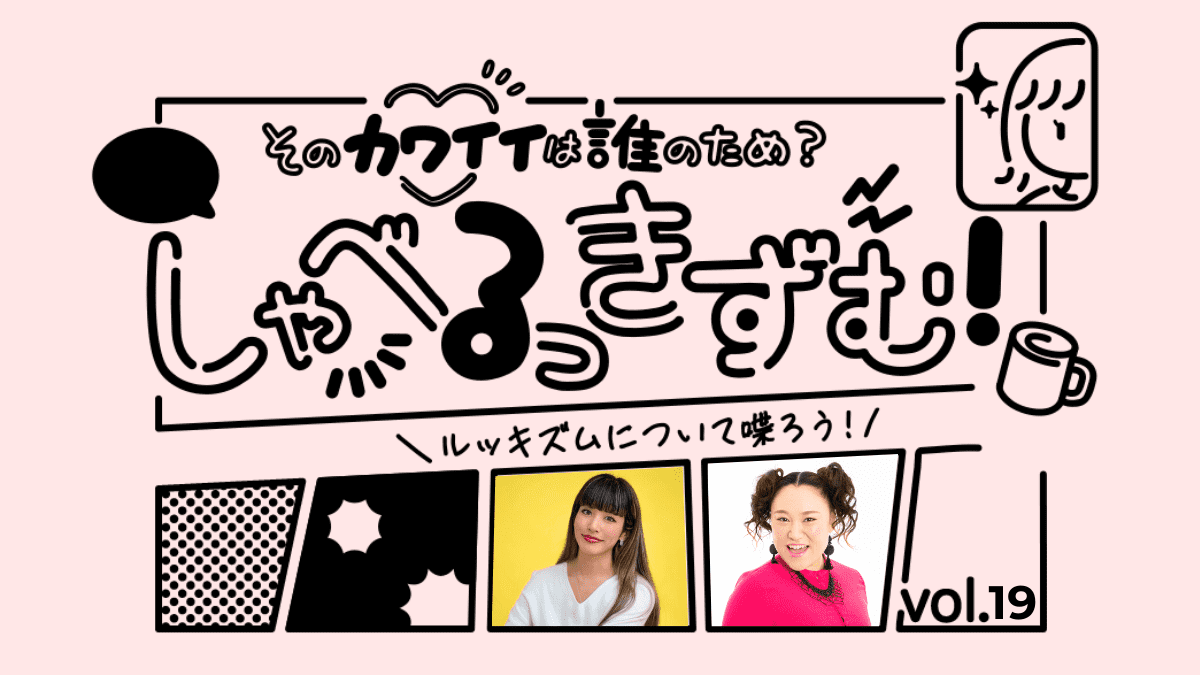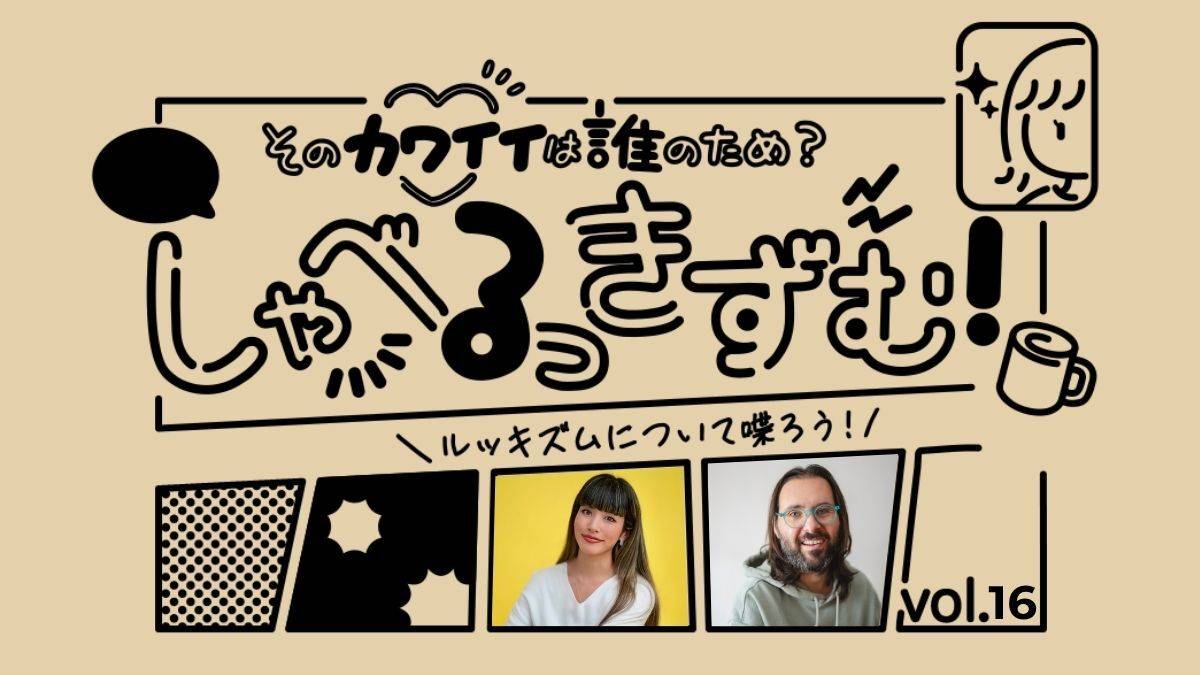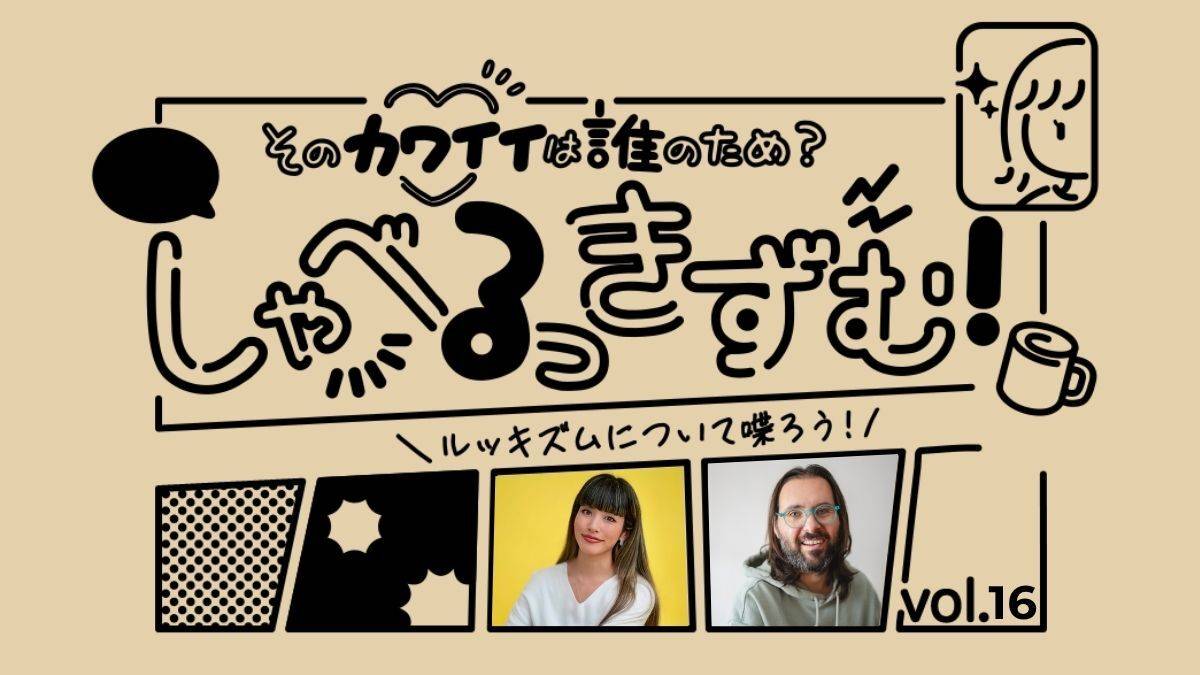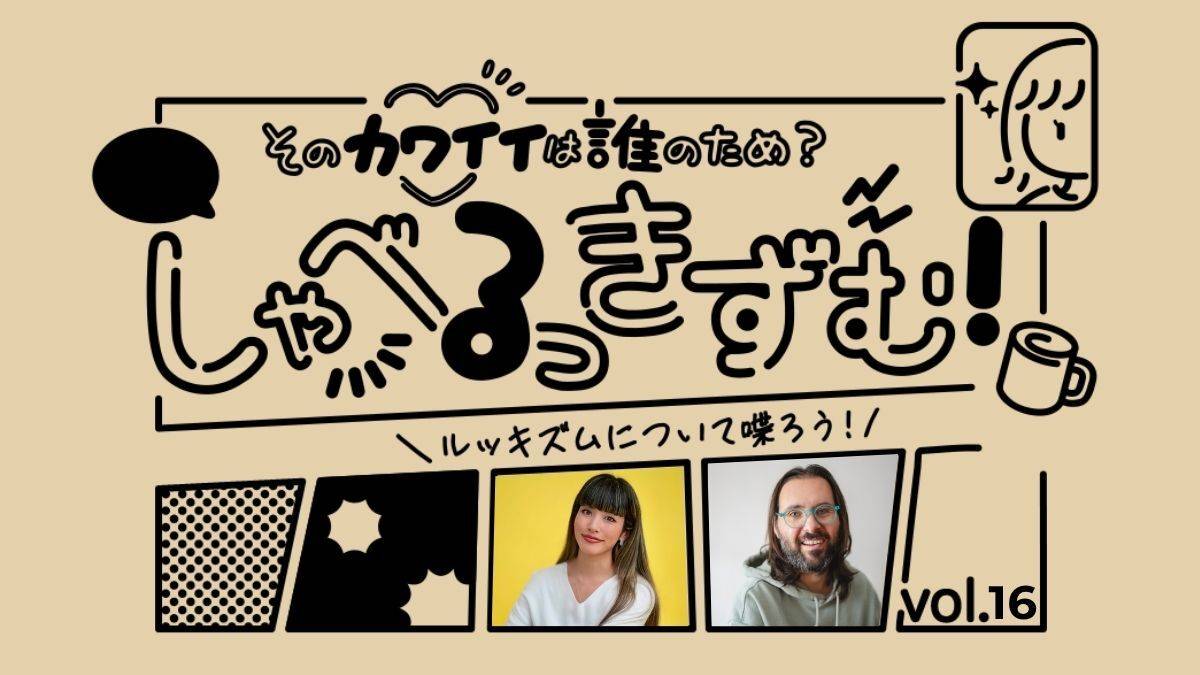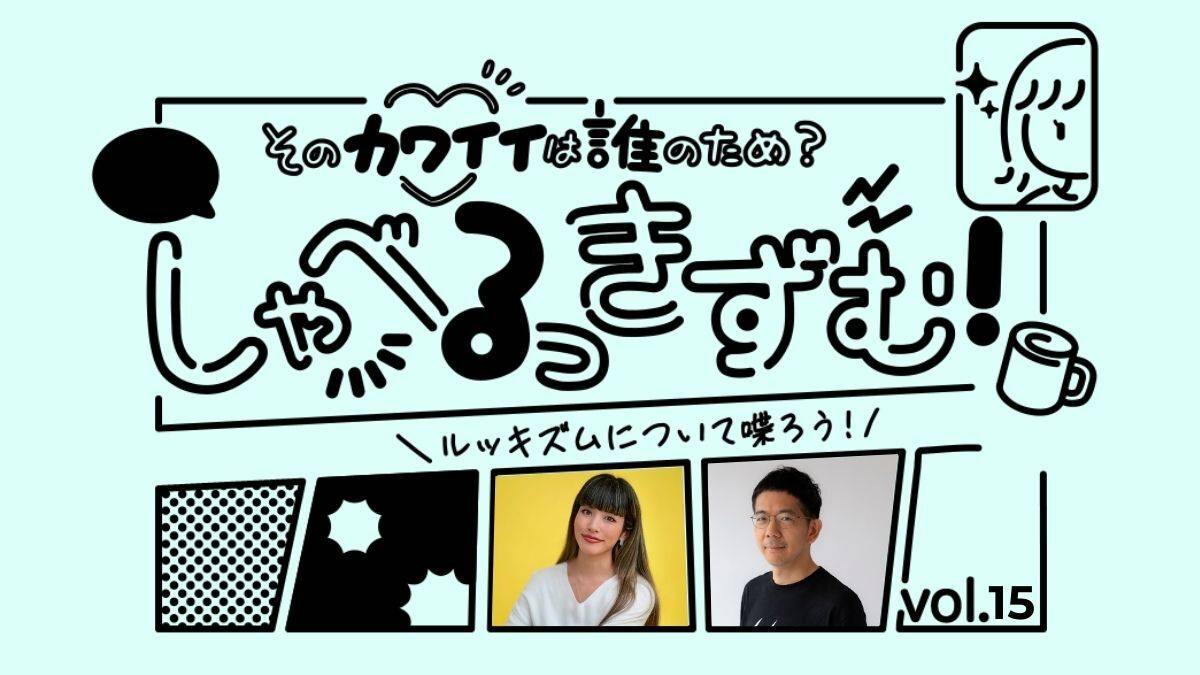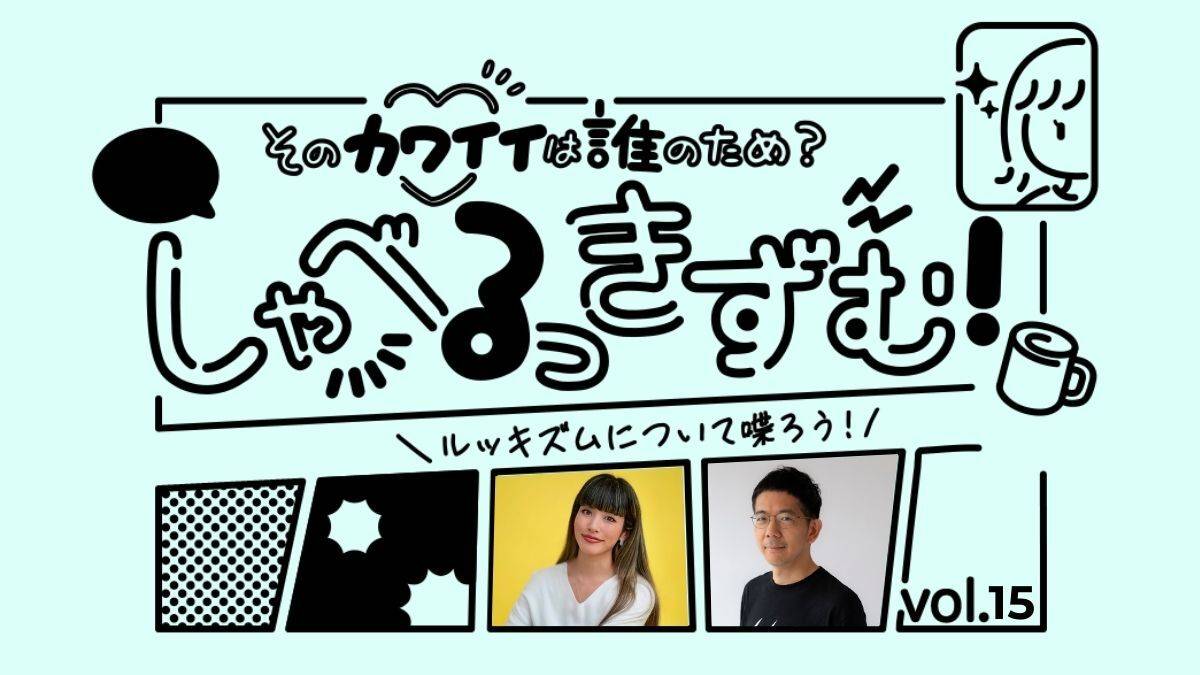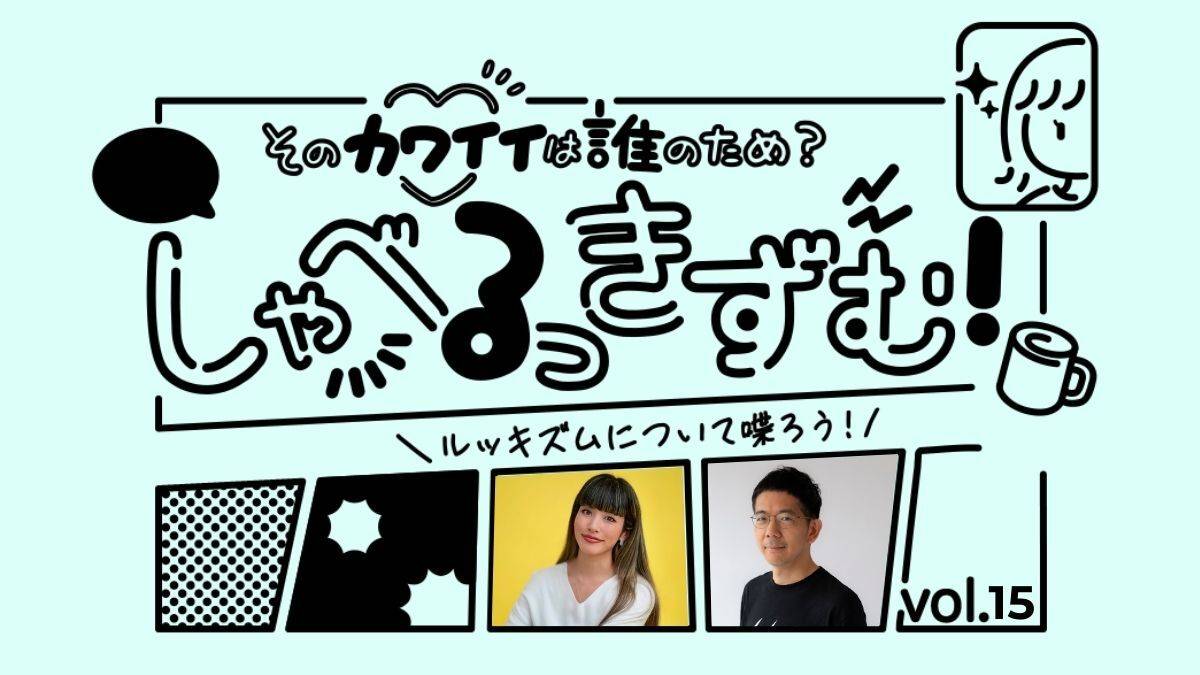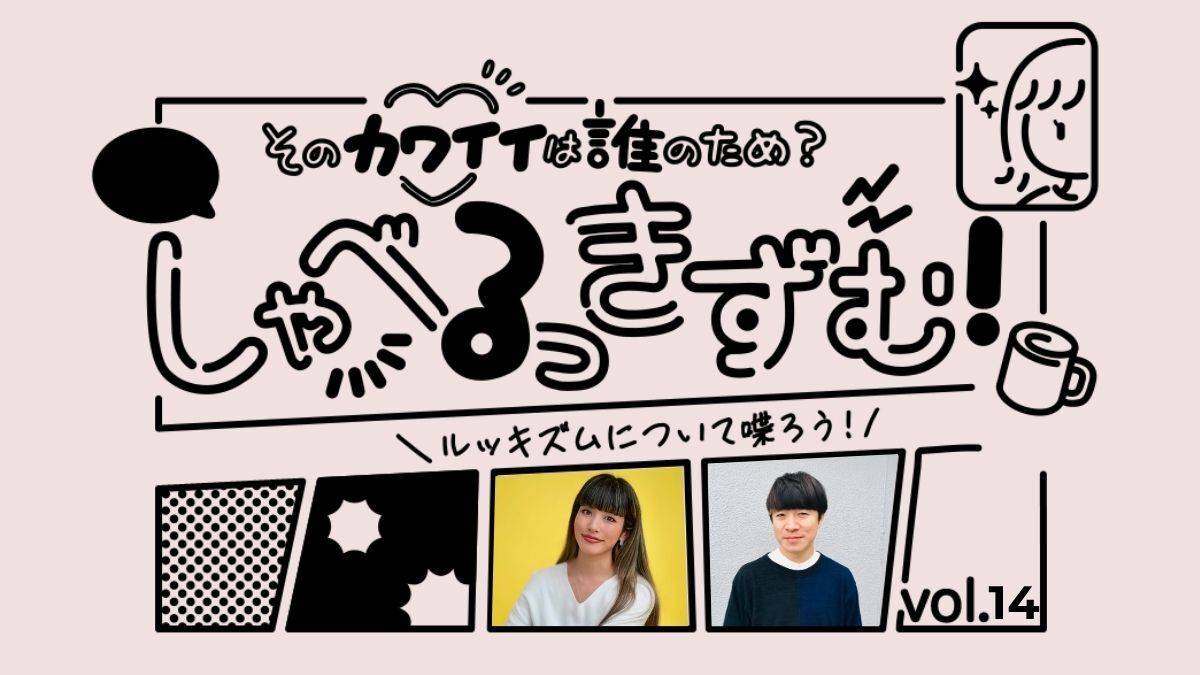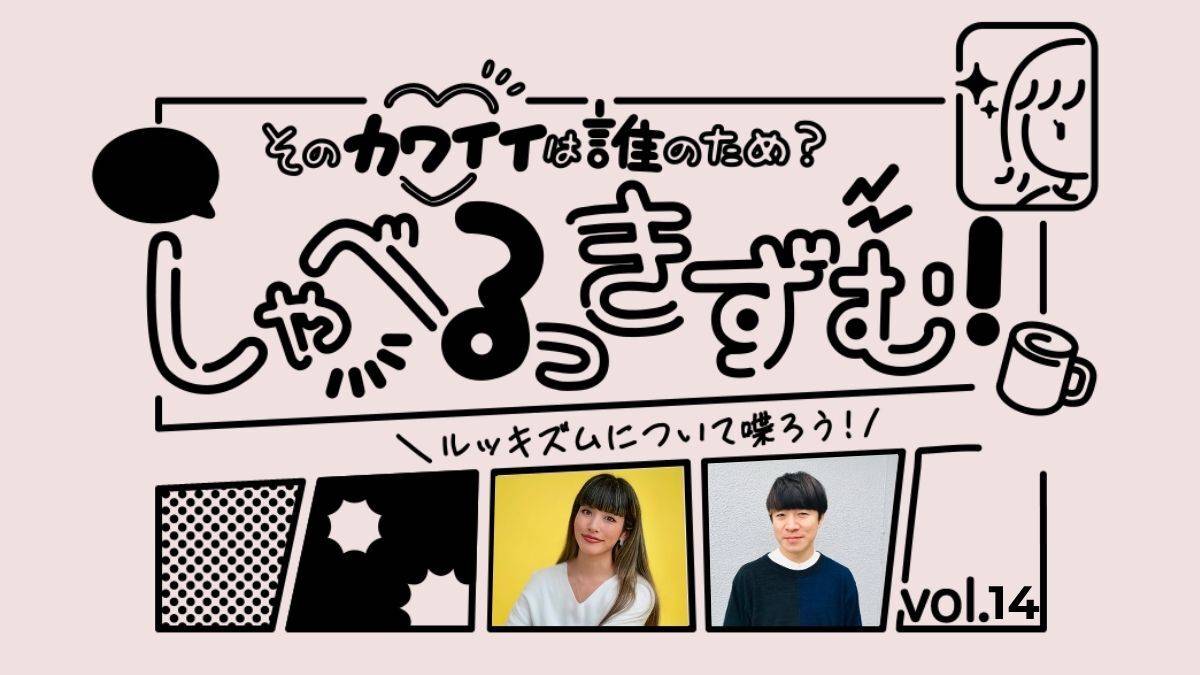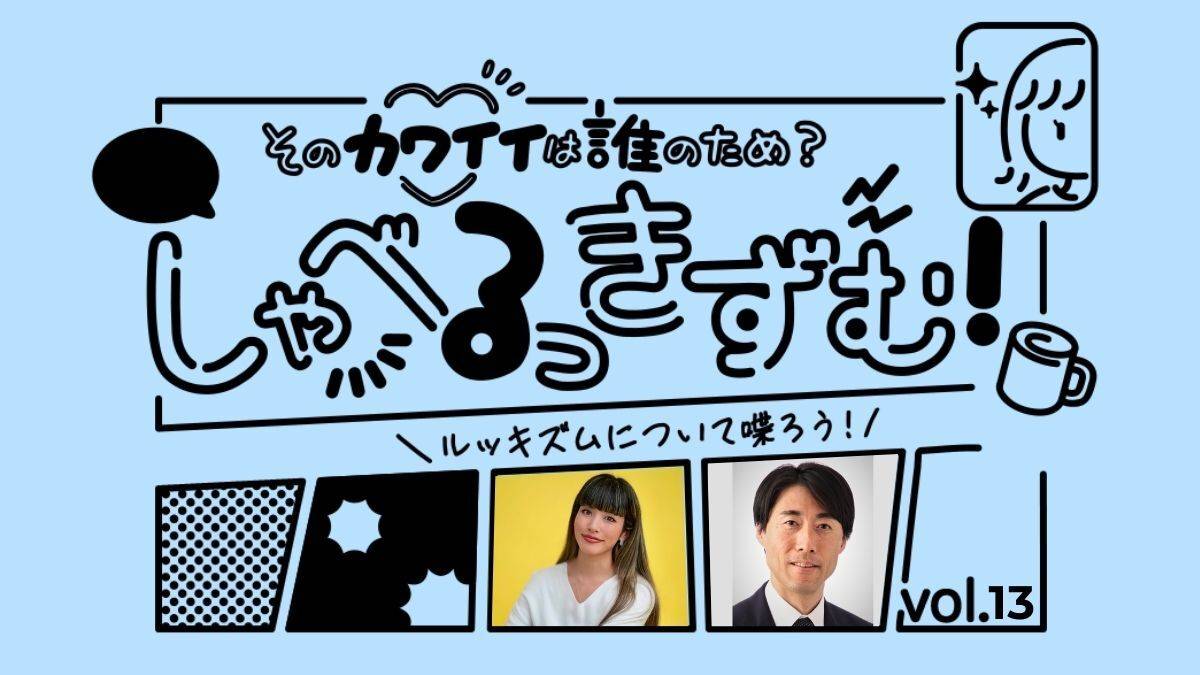痩せることを追求する女性たちへ“FUS”で伝えたいこと|前川裕奈さん×田村好史先生(1)

容姿で人を判断したり、揶揄したりする「ルッキズム(外見至上主義)」。言葉の認知が進む一方で、まだまだ理解されていないルッキズムについて、おしゃべりしてみよう!自身もルッキズムに苦しめられた経験を持ち、Yoga Journal Onlineで「ルッキズムひとり語り」を執筆する前川裕奈さんとゲストが語り合う連載が「しゃべるっきずむ!」です。
第13回目は、順天堂大学の教授である田村好史さんをゲストにお迎えしました。糖尿病や肥満について研究する一方で“痩せ問題”にも関心を持ち、自分らしく心地よい身体の選択を追求する「マイウェルボディ協議会」を立ち上げた田村先生。新たに提唱した「女性の低体重/低栄養症候群」通称「FUS(ファス)」を交えながら、“健康”や“身体”といった側面とルッキズムの関係性についておしゃべりしました。
肥満から痩せ問題に興味を持ち始めた理由
前川:田村先生の専門は肥満や糖尿病ですが、そこから「マイウェルボディ協議会」を始めとする、日本の女性の“痩せ問題”(健康を害するほどの過剰な痩せ追求)に特化した活動を始めたのはなぜだったんですか?
田村:僕自身もまったく専門外だと思っていたんですが、あるとき「痩せている人は糖尿病になりやすい」という事実を知ったんです。
前川:全然知らなかったです!増量することと糖尿病が繋がっているイメージでした。
田村:肥満の人が糖尿病になりやすいのも事実ですが、極端に痩せている人もなりやすいということを知りました。糖尿病を専門にしている研究者のなかでも、あまり知られていないことだと思います。
前川:男女関係なく、その傾向があるんですか?
田村:そうですね、男女ともにあります。ただ、調べていくうちに、日本は痩せている女性(※BMIが18.5以下)がどんどん増えていることも知りました。世界的に肥満が問題になっているなかで、日本とシンガポールの女性だけが痩せ傾向が続いている。このままでは、痩せからくる糖尿病も増えてしまうんじゃないか……と思ったのがきっかけでした。実際に100名ほどの女性を集めて糖尿病の検査をしてみたところ、痩せている人は標準体重の人の7倍近くの糖尿病リスクがあることがわかりました。
前川:そんなに!

田村:僕も「なんじゃこりゃ!」と思って、どうにか彼女たちの体重を増やさないと……と考え始めたんですが。でも、そもそも“なんで痩せてるんだろう”と調べていくと、まあご想像のとおり、日本の女性たちとダイエットの関係性が見えてきたわけです。
いつから「痩せなきゃ」になったのか
田村:日本の女性の“痩せ問題”を研究するなかで、ある学生がこれまでの女性誌の変遷を調べたんです。すると、1970年代くらいから「痩せているほうが素敵」という雰囲気の広告が出始めていることがわかります。
前川:もう50年以上も前から……根深いですね。「昔はふくよかな女性が美しいとされた時代もあった」とよく言いますが、その「昔」とは平安時代あたりを指してるので、それ以降はもうずーーーっと痩せ至上主義が長年かけて植え付けられてきたんですね。

田村:はい。1970年代も、一時「健康美」といって、少しぽっちゃり目も良い、という流れもあったのですが、70年代後半から読者モデルの身長と体重が明記されるようになり、美容広告の内容も「痩せていないのは、あなたの怠慢」といったコピーが使われるようになっていきました。
前川:最初は「ちょっと痩せてたら素敵じゃない?」だったのが、そのうち「痩せていないとだめだ」になってきたと。いまだに「太っていると怠惰だ」とか言う人もいますもんね。実際、肥満の研究をしてきた田村先生は、肥満をどう捉えていますか……?
田村:生まれつきの体質などもありますよね。食欲や食べられる量も、その人が意識的に決めているだけではなく、体質も大きく影響しています。もちろん食事の内容は大切ですけど、普通に食べて運動していればその人本来の体重になっていくはずなんです。多分それが、本人が自然に求めているという意味で「適正体重」と言えると思います。もちろん、それで太って病気になりやすい、という人もいるのですが。
「体調<痩せ」と思わせているのは社会だ
前川:それ、すごくわかります。私も、好きなものを食べて比較的運動もしているので、今が一番の適正体重なんだろうなと思います。人から見れば「運動してる割に太い」「あなたは細いね」とそれぞれですが、自分では納得感があるんです。一方で、過去に極端なダイエット沼にハマっていた経験があるからわかりますが、その当時に「身体のためにもう少し太りなさい」なんて言われても絶対に聞き入れられなかったと思います。「だって今、痩せたいんだもん!」って。
田村:そうですよね、僕もあんまり響かないだろうなと思ってます。
前川:それは女性たち自身の問題というより、社会的な問題ですよね。身体や将来を犠牲にしてまで「痩せたい」と思わされている理由は、この社会構造にあると思います。
田村:僕も公衆衛生学的なことより、もっと社会全体の体型に対する価値観を変えることが必要だなと思いました。それで、日本の「体型に対する多様な価値観に気が付くこと」を推進する「マイウェルボディ協議会」の立ち上げに至ったわけです。
あと今、糖尿病の治療薬が“抗肥満薬/痩せ薬”として出回っている問題があります。本来の目的ではない使用法が出回ることに日本肥満学会も警鐘を鳴らしていて、日本の女性の過剰なダイエットに歯止めをかけたいという思いから、「FUS(Female Underweight/Undernutrition Syndrome)」という概念を肥満学会の中で作りました。

前川:私も協議会には、「マイウェルボディ for Girls サポーター」として参加させていただいています。田村先生ご自身が、こういった問題に取り組むのはなぜなんでしょうか。女性の問題って女性が発信することが多いので、男性の立場からも発信されてるのはとっても良いムーブだなと思っておりまして。
田村:僕のマインドは基本的には研究者。どうすれば世の中が良くなるかを考えて、必要な研究を実施し、広めていく立場だと思っています。世界的にメジャーな研究がしたければ肥満研究をするべきですが、意外に日本特有のローカルな課題は後回しになりがちで、埋もれているけど本質的に重要な課題にこそ、取り組んでいくべきという思いがあります。
ダイエットと体調不良をつなぐ「FUS:ファス」
前川:先ほどお話ししていたFUS(Female Underweight/Undernutrition Syndrome:ファス)という新しい概念についても、もう少し詳しく教えてください。

田村:日本語だと「女性の低体重/低栄養症候群」で、基本的にはメタボの逆。「痩せすぎが体調不良につながっている」という状態を指しています。実際、低体重や低栄養になると、骨がもろくなったり貧血になったりすることがわかっていて、自覚症状として、疲れやすさや冷え、肌や髪質の悪化もあります。前川さんもダイエットしていた頃、そういうことありませんでしたか?
前川:あったかも。でも、それがダイエットのせいだとは思ってなくて「髪パサパサなのは染めすぎたから」と思っていましたね。
田村:そう、みんな体調不良とダイエットが結びついていないんですよね。それをFUSという症候群として提唱することで、「もしかしてダイエットのせいかも……」と気がついてもらえたらと期待しています。そのために作成したのが、この概念図です。今までは、月経の異常や貧血、倦怠感、肌が荒れた、、、など、それぞれ別々に原因があると考えて、別々に対処していたかもしれません。でもそれは、氷山でたとえると、ほんの一角で、その原因となる水中部分、つまりは低体重や低栄養に目を向けるべきだということが伝えられればと思っています。この図で理解すれば、氷山の水上に出ている部分をなくすには、ひとつひとつ対処するのではなく、低体重や低栄養にアプローチすれば、全部一気に解決するかもしれませんよ、ということがご理解してもらえると思っています。実際、症状がある女性たち数名の生活習慣に介入してみたのですが、1ヶ月で体調が大幅に改善しました。
前川:どんなことをしたんですか?
田村:「1日3食、ご飯とおかずを食べる」「1日8000歩、歩く」「週3回筋トレをする」「よく寝る」など。よく食べてよく動く、といった基本的なことばかりです。炭水化物や朝ごはんを抜くなどのダイエット法とは逆のアプローチで、結果的にほぼ全員の倦怠感などの体調不良が改善しました。その間、やはり体重が増えて来た人が多く、今までエネルギーが足りなかったのかもしれません。私のイメージでは、ダイエットを意識していると、元気がなくなり、また身体を動かす気力が無くなってきて、運動不足でさらに調子が悪くなっている、という人が多いのかなと感じました。
前川:たしかに炭水化物はエネルギーになるもので、食べるって大事ですよね。20代で極端なダイエットをしてた頃は、10ヶ月間炭水化物を摂らない生活をしていました。常に疲れてメンタルも不調でしたが、仕事が忙しいから……と片付けていましたね。私はもともと食べるのも寝るのも運動するのも好きなので、30歳手前からそれらを大事にし始めてからは体力もメンタルも整いましたし、思考もハッキリするようになったんですよね。
一時的なブームで終わらせないために
前川:これまで“痩せ問題”に、健康的な側面からアプローチする人は少なかったと思うのですが、なぜなんでしょうね?私自身は、セルフラブをテーマにしたアパレルブランドの経営が先にあった本業なんです。ブランドを通してルッキズムに問題提起してきましたが、アパレル以外で登壇や授業の依頼が来るのは、それだけこの問題に取り組む人がまだまだ少ないからだと感じています。
田村:たまに「痩せすぎは危険」みたいな話は出るんですが、ブームにならずに一瞬で終わってしまうんですよね。FUSを一時的なブームで終わらせないためにどうすればいいのか、と協議しています。
前川:これまでの「しゃべるっきずむ!」のなかでも、ルッキズムを助長するのはそれが売上・利益につながる人たちがいるからだ、という話が何度か出ています。「ダイエット・痩せ」はその最たるものなので、人々に「痩せたい」と思い続けてほしい企業は一定数いる。そうすると、どうしても「ルッキズムをやめよう」「痩せすぎは危険だ」という声が大きくなりにくいですよね。
田村:そうですよね。やはり需要や気づきがあって“売れる”という好循環を作らないと大きなブームにはなりにくいと考えています。FUSがランドマークとして認知されることで、今後ここに産業が生まれていけばいいなと考えています。

*次回、過度なダイエットによる低栄養の影響について話します。2本目「過度なダイエットによる後遺症……次世代に引き継がないために。」は、こちらから。
プロフィール
田村好史先生
順天堂大学医学部卒業後、カナダ・トロント大学での研究経験を経て、順天堂大学大学院医学研究科で博士号を取得。現在は、順天堂大学医学部、国際教養学部で教授を務めるほか、スポートロジーセンターのセンター長補佐としても活躍中。スポーツと医学を融合させた予防医学「スポートロジー」の分野で、特に若年女性の「やせ」に関する健康課題に取り組む。2024年には、内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の一環として設立された「マイウェルボディ協議会」の代表幹事に就任。この協議会では、「自分らしく、心地よく、健康的な体を自らの意志で選択できる社会」の実現を目指し、多岐にわたる活動を展開しています。
FUS(女性の低体重/低栄養症候群)については、こちらをご覧ください。
X(旧Twitter):@YoshifumiTamura
前川裕奈さん
慶應義塾大学法学部卒。民間企業に勤務後、早稲田大学大学院にて国際関係学の修士号を取得。独立行政法人JICAでの仕事を通してスリランカに出会う。後に外務省の専門調査員としてスリランカに駐在。2019年8月にセルフラブをテーマとした、フィットネスウェアブランド「kelluna.」を起業し代表に就任。ブランドを通して、日本のルッキズム問題を発信。現在は、日本とスリランカを行き来しながらkelluna.を運営するほか、「ジェンダー」「ルッキズム」などについて企業や学校などで講演を行う。著書に『そのカワイイは誰のため?ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話』(イカロス出版)。yoga jouranal onlineコラム「ルッキズムひとり語り」。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く