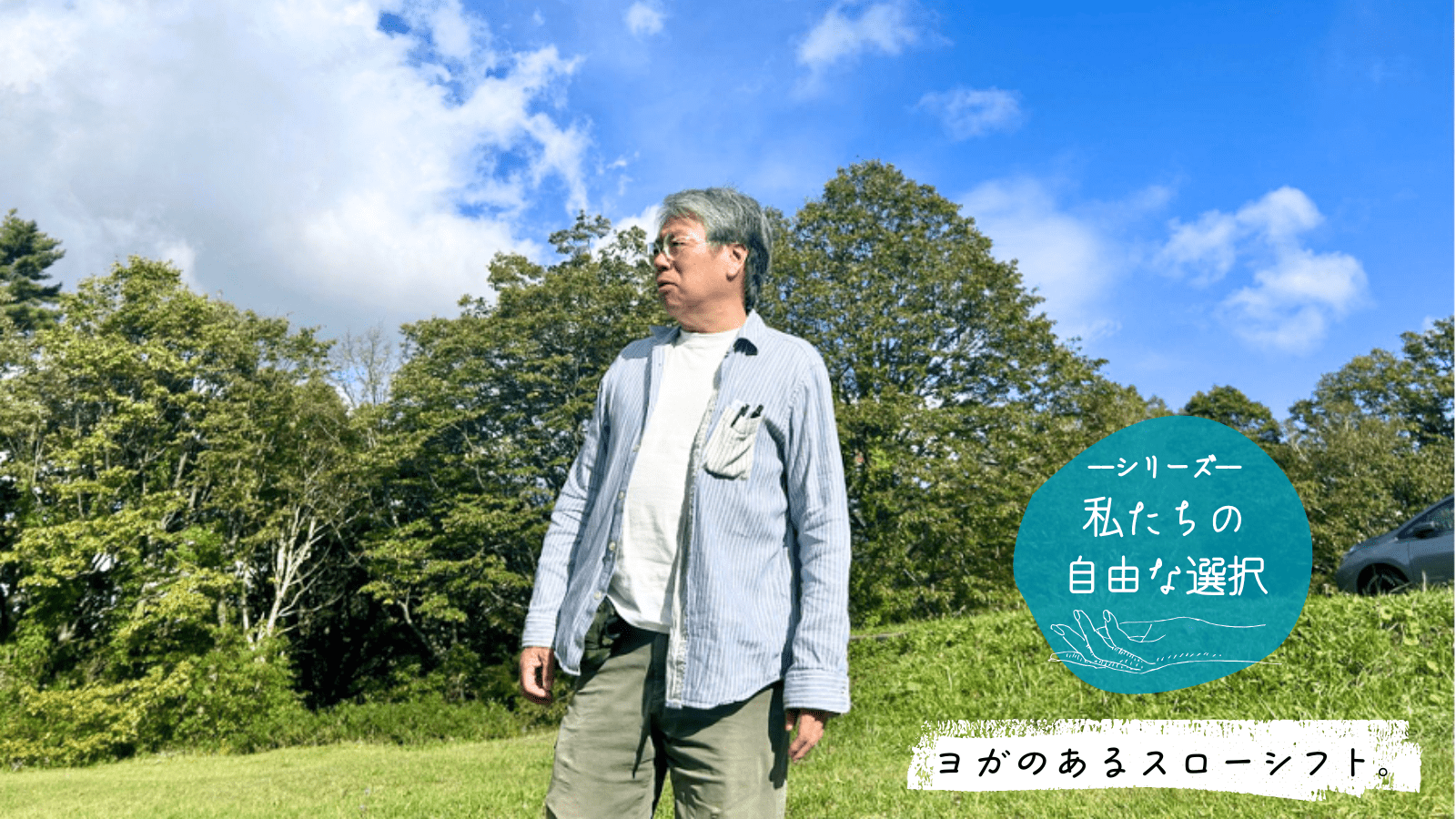自死が身近な故郷のため生きると決意。バクティヨガ指導者ヒマギリさんが今10代へ伝えたいこと


苦しみに備えるため、体づくりを始めよう。 教えてくれる人に耳を傾け、10代の経験を宝にしよう。
ーー今、生きづらさも抱えている若者たちへヒマギリさんが教えられること、アドバイスやメッセージをお願いします。
ヒマギリさん:ヨガの提案を通して教えられる、最もわかりやすいことが2つあります。1つめは「運動をしよう」ということです。
5000年前から言われていることですが、人生には3つの苦しみがあります。他者からの苦しみ、生老病死による苦しみ、天変地異による苦しみです。そんな苦しみに備えるために、私は体づくりが基本だと考えています。
ただし、体を動かす時に、仕事に害がないように、人との繋がりを断つほどや、周りに迷惑や心配をかけるほど、極端になってはいけないということは留意して伝えたいですね。
今の若者世代は全く動かないか、過度に動きすぎているか、両極端が多いなと感じています。
もっと若い、働き始める前の10代前半に向けて伝えたいことの2つ目は「聴く力」です。
ヨガの経典は「ヴェーダ」と言われますが、その別名をサンスクリット語で「聴く」という意味の「シュルティ」ともいいます。転じて、ヨガ哲学は、聴くことに始まると考えられます。
私は、自分の苦しみや悲しみを把握して人生に活かせる人、出来ない人の違いは「聴く力」にあると考えています。
とはいえ、自分のことは自分で解らないものなので、極端になってしまうこともありますが、私たちは人の話を聞き、人と関わるなかで、自分の極端な部分を認識できるものです。だから、スマートフォンの世界にとまらずに、コミュニケーションの先は目の前の人であるべきです。例えばヨガの教室の中なら、先生の言うことに耳を澄ませて体を動かせているかどうかは、気をつけて見ています。傾聴する先は、目の前の先生でも親でも「何かを教えてくれる人」。苦しみや悲しみも経験したこと全てが宝になる10代だからこそ、自分を愛してくれている人の言葉を受け入れられないと、せっかくの経験も宝にできないということです。
そうした意味で、私の指導のなかでも、若い世代の「聴く力」を伸ばしたいと思います。
取材後記
毎年3月は厚生労働省の「自殺対策強化月間」でした。ニュース経由で遠い話題と思えていたSNS上の誰かの自死や自分の環境で隣り合わせている生老病死の営みについて深く考える契機となりました。
取材では、毎日のヨガで生徒と向き合う指導者、経営者・活動家として駆けるヒマギリさんの2つの顔に迫りました。生い立ちから伺う中で、ヒマギリさんが一人のヨガインストラクターとしてではなく、ライフワークとしてヨガに奔走する動機は、故郷だからこそ思い入れが強い社会問題だと理解できました。
どうしても「苦しい」という思考から抜け出せない若い読者の方、今より強く、健康な自分になりたいと思う若い読者の方は、体の土台作り、身近な誰かの教えにヒントを得る機会を意図的に作ってみてはいかがでしょうか。
苦しみや愛することについて、当事者ごとで理解を深めるため、苦しみ・苦しいことの表現は福祉やケアに携わる竹端寛氏の出典を、愛することの考え方や親子関係の変化は、精神科医の山内道士氏の著書を参考としました。
《執筆にあたっての参考図書》
・『自分の「好き」がうつを治す』/ 山内道士(幻冬社メディアコンサルティング)
・『ケアしケアされ、生きていく』/ 竹端寛(ちくまプリマー新書)内出典
・ 『生きていく絵』/ 荒井裕樹(ちくま文庫)
Profile:瀧聖子(Ma Bhakti Hima Giri)
「藝 UeL Tokyo」を主宰。株式会社WIQOMEDIAN代表。故郷の自殺率への問題意識を機に、社会問題に特化して「バクティヨガ」を伝える。東京・蔵前や秋田で定期的にヨガイベントを開催。スタジオで毎日レッスン指導に携わる他、大学や企業でのヨガ指導、指導者育成にも力を入れる。公式サイト:マー・バクティ・ヒマギリ
Instagram: @ma_bhakti_himagiri
UeL 藝 各スタジオ @uel_tokyo @uel_akita @uel_chiba @uel_miyagi
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く