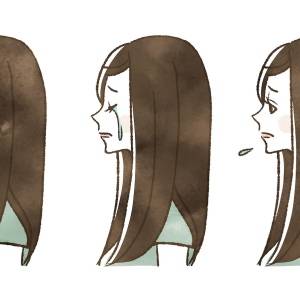「希望?一体どこにそんなものがあった?」『82年生まれ、キム・ジヨン』キャッチコピーが見落としたもの

エコーチェンバー現象や排外主義の台頭により、視野狭窄になりがちな今、広い視野で世界を見るにはーー。フェミニズムやジェンダーについて取材してきた原宿なつきさんが、今気になる本と共に注目するキーワードをピックアップし紐解いていく。
「誰かの妻で、母で、娘であるあなたに送る、共感と絶望から生まれた希望の物語」
2020年、韓国で社会現象となった小説『82年生まれ、キム・ジヨン』の映画版が日本で公開された際、このキャッチコピーが大きく打ち出されました。
しかし、この作品を読んだ人なら誰もが感じるはずです。
希望?
一体どこにそんなものがあった?
キム・ジヨンの物語が描いたもの
主人公キム・ジヨンは、1982年に韓国で生まれた平凡な女性です。幼少期から優秀な成績を収めながらも、「女の子だから」という理由で進学を弟に譲るよう求められ、就職しても職場でセクハラに遭い、結婚後は仕事を辞めて育児に専念することを期待されます。そして次第に心を病み、追い詰められていきます。
物語は淡々と綴られ、最後まで何の解決も訪れません。キム・ジヨンは精神科で治療を受けますが、彼女を病ませた社会構造は何一つ変わりません。夫はいっけん「理解ある夫」風ですが、根本的な家父長制の価値観からは抜け出せていません。物語は、絶望的なまでに無力な余韻を残して終わります。
『82年生まれ、キムジヨン』は徹底的に、容赦なく、女性に課せられる抑圧を描いた告発の書であり、そのリアリティゆえに、多くの女性から支持されたのです。
二重の欺瞞──「誰かの」と「希望」
日本版キャッチコピーは、こういった『82年生まれ、キム・ジヨン』の本質とは真逆のメッセージを発しています。
第一に、「誰かの妻で、母で、娘であるあなた」という呼びかけ。キム・ジヨンをひとりの人間ではなく「妻・母・娘」というカテゴリーに押し込めるのは、家父長制の論理そのものです。女性を男性との関係性の中でのみ定義し、個人としての存在を消去する──まさにキム・ジヨンを病ませた構造を、キャッチコピーが無自覚に再生産しているのです。
『上野さん、主婦の私の当事者研究に付き合ってください』(上野千鶴子・森田さち 晶文社)で、社会学者の上野千鶴子は、母、妻、主婦、婦人、娘、処女などの「女の呼び名」はどれも、「家父長制が女に与えた指定席」だと喝破しています。
家父長制による苦しみを描いた物語に対し、家父長制の指定席を押し付けるコピーをつけてしまうのは、作品の本質を全く理解していないと言えるでしょう。
第二に、より深刻なのが、「希望の物語」という虚偽です。
この作品のどこに希望があったでしょうか。キム・ジヨンは回復しましたか?彼女を取り巻く環境は変わりましたか?社会は変わる兆しが見えていますか?答えはすべて「NO」です。
作者チョ・ナムジュが描いたのは、出口のない閉塞感であり、変わらない現実であり、そして読者の怒りを喚起するための鏡でした。『82年生まれ、キム・ジヨン』は「仕方ないこと」「当たり前」とされてきた女性差別や女性蔑視を詳細に描くことで、女性たちに「やっぱりおかしい。怒っていいんだ」と思わせる効果があったのです。
マーケティングによる「無害化」
ところで、なぜこのような欺瞞的なキャッチコピーがつけられたのでしょうか? 答えは明白です。告発の書を「希望の物語」に変換することで、作品を無害化し、消費しやすくするためです。
「女性への抑圧を告発する映画」では「家父長制社会において観客動員が見込めないのでは?」という恐れから、「共感できる感動作」にパッケージングし直されてし待ったのでしょう。
その過程で、作品の核心は完全に骨抜きにされ、結果、誰のための、どういう話なのかがぼんやりしてしまったのです。
告発を「感動」「現状維持でいい」にすり替える暴力
より本質的な問題は、このキャッチコピーが観客に何を期待しているかです。「共感して泣いてください、そして希望を感じて帰ってください」──そんなメッセージが透けて見えます。
しかし、この作品が求めているのは涙ではなく怒りです。共感ではなく気づきです。カタルシスではなく不快感です。観客を居心地悪くさせ、考えさせ、そして何かを変えようと思わせること。それがこの作品の存在意義でしょう。
この作品に「希望」があることにしてしまったら、変化は望めません。つまり、日本版キャッチコピーは、「家父長制に与えられた女性役割」を受け入れ、変わる必要はない、と言っているようなものなのです。
もしこの作品が希望に満ちたものだと感じられるなら、それは、「家父長制を維持したい人」にとっての希望でしょう。
怒りを取り戻すために
『82年生まれ、キム・ジヨン』は希望の物語ではありません。それは、私たちが生きる社会の醜悪さを映し出す鏡であり、変革を迫る告発状です。
この作品に向き合うということは、不快感を引き受けることです。「誰かの妻で、母で、娘」という役割規定の暴力性を直視し、それが今も続いている現実に怒ることです。そして、安易な「希望」や「感動」に逃げ込まず、具体的な変化のために何ができるかを考えることです。
キャッチコピーが提示した「希望」は、作品の魂を殺しました。私たちにできるのは、その欺瞞を見抜き、作品が本来持っていた鋭い刃を取り戻すことではないでしょうか。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く