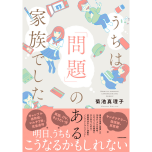子どもの問題は全て親の育て方が原因?取材を通して見えてきた家族の「本当の問題」【インタビュー】

過去作に『毒親サバイバル』などがある、菊池真理子さんの新作『うちは「問題」のある家族でした』(KADOKAWA)では、ギャンブル依存症、マルチ2世、児童虐待、貧困、DV、きょうだい児、ヤングケアラー、陰謀論、反医療の9テーマの当事者の経験がマンガで描かれています。菊池さん自身もアルコール依存の父親をケアしていた経験をお持ちです。菊池さんの過去の経験や、今回の取材で見えたことなどを伺いました。
40代まで自分の家の「問題」に気づいていなかった
——まず、菊池さんご自身の生まれた家でのご経験についてお話しいただけますか?
生まれた家は、自営業の父と専業主婦の母、私と妹の4人家族でした。 父は診断は受けていませんでしたが、おそらくというか、確実にアルコール依存症の状態で、母はある宗教の熱心な信者という環境の中で育ちました。両親の仲も悪くて、2人が仲良く過ごす姿はほとんど見たことがないですね。
父は週末になると大量に飲酒をする人で、毎週末ほとんど記憶をなくしていて。後から知ったのですが、短時間に大量のお酒を飲むことを「ビンジドリンキング」といって、厚生労働省でも啓発がされています。近所の大人を呼んで麻雀をしているので、私と妹は自分の家なのに入れない部屋があったんです。
私が中学2年生のときに母が自死をして、父子家庭となりました。年々父の飲酒が問題化していく中で、私が父の面倒を見る立場になっていきました。
私は高校卒業後に将来の目標が持てなくてフリーターになったのですが、機会があって23歳のときに漫画家になります。30歳を過ぎた頃から漫画の仕事だけで食べていけるようになったのですが、実家で父と妹と一緒に暮らし続けてはいて。私が40歳になった頃に父はアルコールが原因で体を壊し、亡くなってしまいます。
——過去の作品で、自分の家の「問題」に気づいたのは、お父さまが亡くなった後と描かれていました。それまではどういう感覚だったのでしょうか。
父の飲酒は嫌でしたが、それを「問題」だと捉える感覚がない状態で、スルースキルばかり身につけていたように思います。「問題」に気づいてからは、見ないようにしていたものが見えるようになってしまって、それでしんどくなって、メンタルが大きく落ちていた時期もありました。
父をケアしている途中で、「毒親」という言葉は出始めていたのですが、当時は私自身が自己責任論者だったので、「私が定職に就けなくて、結婚もしていないのは、自分が悪い」という感覚がずっとあって。
社会に「親は必ず子どもを愛している」「家族の絆は絶対」といった家族神話が強く根付いていましたし、毒親という言葉も、親を悪く言うことも、抵抗感を持っていました。
子どもの問題は全て親の育て方が原因?
——今回、お子さんがギャンブル依存症の方の取材をしていました。本書の中でも、家族の問題というと、親、特に母親が責められることが多い中で、子どもが依存症の親の方に取材されたのはどういった経緯があったのでしょうか。
父のアルコール依存を発信して以降、政府の依存症啓発活動やイベントに登壇する機会がありました。その関連で、ギャンブル依存症当事者の家族会の方々と関わる機会があって。
ただ、当時は自分がアダルト・チルドレン(※1)だと気づいたばかりで、知識も不十分な状態で。「子どもの抱える問題は全て親の育て方に原因がある」と考えていました。
そんな中で家族会の方々が「子どもの人生は子どもの人生。私たちはタフラブ(※2)で生きます」と話すのを聞いて、ショックを受けて。思わず「ご自身の子どもへの関わり方に問題があったとは思わないんですか」と言ってしまいました。ところがその時の空気で、私が間違っているのかなと感じて。
そのとき、ギャンブル依存症について勉強しなければと思って、本を読んで「ギャンブル依存症は脳の病気であり、育て方が原因ではない」という知識を身につけることはできたんです。ただ、実際の体験談を聞くことと、本から得る知識では、自分の中での理解度や受け止め方が大きく異なります。そのため、ずっと実際にお話を伺いたいと思っていた経緯があって、今回お話を聞かせていただくことになりました。

物理的に距離がとれなくても
——本作では、家族との距離感について、絶縁状態からほどほどの距離でうまく付き合っている人、一緒に暮らし続けている人など、色々なパターンが描かれています。菊池さんのご経験も含め、家族との距離感についてお考えのことや、今悩んでいる方にヒントをいただけますか。
私は距離感を取れずに失敗した経験があるため、可能な人は距離を取った方がよいとは思います。ただ、たとえば未成年の頃から親の介護をしていて、自分の代わりに介護をする人がいないなど、経済状況や家庭環境など、さまざまな理由で距離を取れない方もいらっしゃいますよね。「逃げるべき」というアドバイスが多いですが、距離を取りたくても取れない人にとっては、つらいんじゃないかなって思うんです。
私が尊敬する原宿カウンセリングセンターの信田さよ子先生が「同じ家の中で暮らしていても、敬語を使って心理的な距離をとるだけで、全然違ってきますよ」とおっしゃっていたんです。たとえば今までは「おはよう」と言っていたところを、「おはようございます」と完全に敬語で話すことでだいぶ楽になるそうです。
そうやって、物理的な距離が取れない場合は、心の距離を取ることが有効なのではないでしょうか。適切な助言をくれるカウンセラーを見つけることや、家庭以外の居場所を少しずつ作っていくことも大事なことだと思います。
——「こうしておけばよかった」と思うことはありますか?
そのときどきで可能な最良の選択をしてきたとは思っているので、過去のことは仕方なかったと受け止めています。そのうえで、「たられば」の話をするなら、家を出ればよかったと思う部分もあります。
すごく貧乏だったと思いますし、20代で実家を出ていたところで、メンタルの問題は全然解決していなかったので、DV・モラハラ気質のある人と結婚して悲惨な生活を送っていたかもしれませんが。
でも、20代の頃に経験していた、「日中は楽しく生活していても、父が帰ってきただけで、怒りに支配されて感情が乱される」みたいなことはなかったんじゃないかと。
もう恋愛をしない理由
——『酔うと化け物になる父がつらい』(秋田書店)では、過去の交際相手のお酒の飲み方が激しかったことと、暴力をふるってくる人であることも描かれていました。40代になって、ご自身が抱えてこられたものとも向き合って、魅力的に感じる人も変わってきたのでしょうか?
そこは今でも変わらないです。最後に付き合っていた人とは2年ほど前に別れたのですが、自分の目は腐ったままだと思うことがあって。
人を好きになるのは理性が働かない部分があると思うんです。私はどうしても「ダメな人」に惹かれてしまう傾向があることを自覚したので、もう誰かと恋愛関係になるのはやめました。
そういう人と恋愛をすると、無意識にモラハラ気質のある人に従おうとしてしまって、そうすると卑屈な自分が出てきて自分のことが嫌いになる、という悪循環に陥るんじゃないかと思うんです。
元々恋愛に積極的なわけでもなく、流れで付き合ってきたことが多くて。恋愛よりも友情の方が楽しく長続きするので、友情の方が向いているという結論になりました。
心の高揚感は恋愛以外でも得ることができますし。今までずっと推しがいなかったのですが、最近「推し」ができて、尊いという感覚も知りました(笑)。
※1:依存症や虐待など、不安定な家庭で育ち、生きづらさを抱えている人のこと
※2:「手放す愛」「見守る愛」といった意味
※後編に続きます。

【プロフィール】
菊池真理子(きくち・まりこ)
東京都生まれ。埼玉県在住。アルコール依存症の父との関係を描いた『酔うと化け物になる父がつらい』(秋田書店)、毒親から生き延びた10人を取材した『毒親サバイバル』(KADOKAWA)、宗教2世の現実を世に問うた『「神様」のいる家で育ちました ~宗教2世な私たち~』(文藝春秋)など、ノンフィクションコミックの話題作を多数手がける。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く