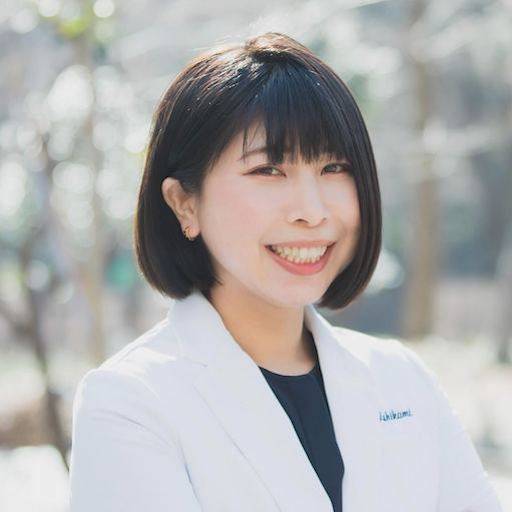起きた後も嫌な気分が続く…漠然とした、なんとなく嫌な夢ばかり見る時の対処法|心理師が解説
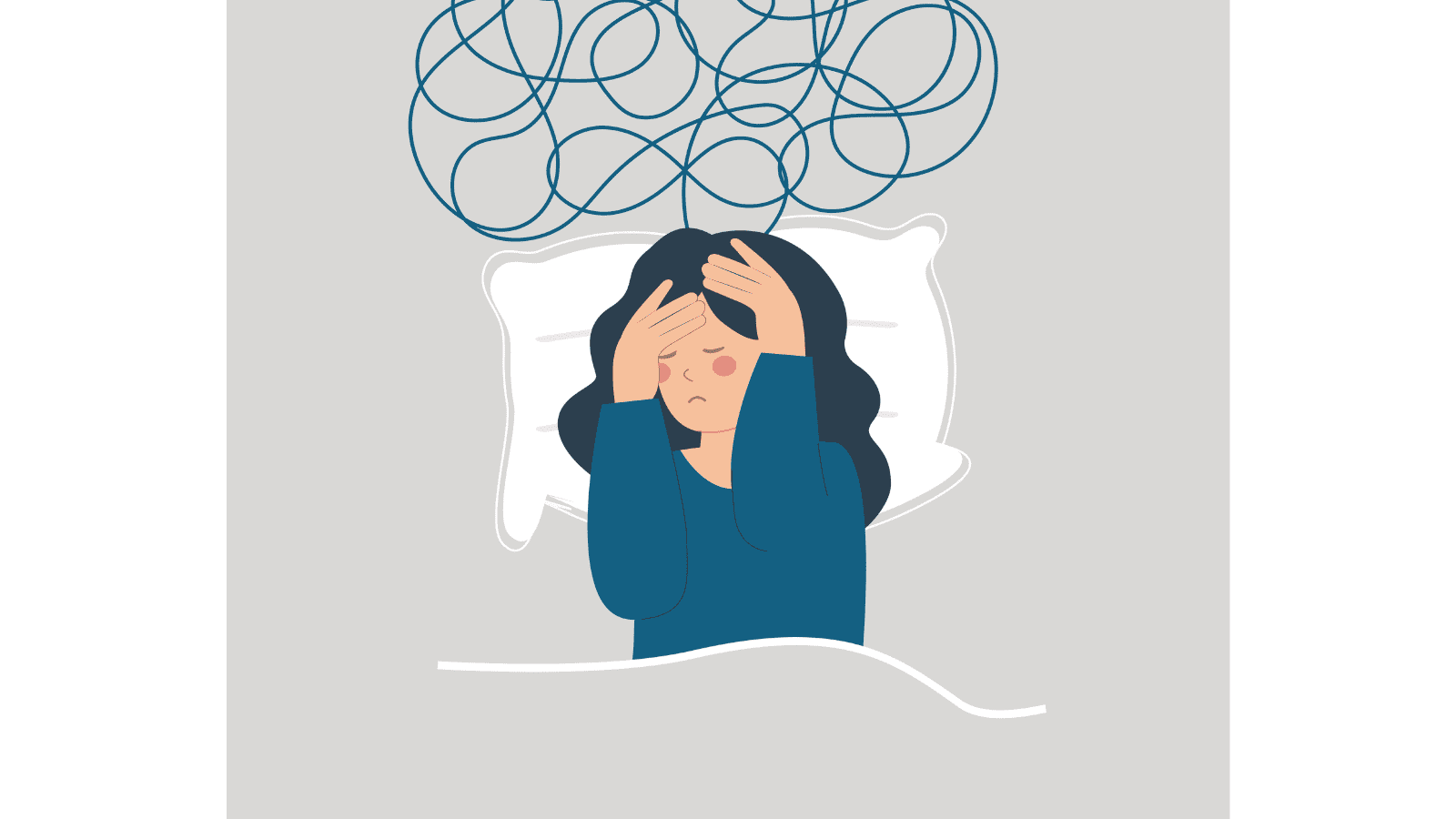
完全な悪夢とまではいかなくても、なんとなく嫌な気持ちになる夢に悩んでいませんか?嫌な夢は、起きた後も気分がすっきりしなかったり、疲れが残ったりすることが多いものです。今回は、漠然とした嫌な夢ばかり見る時の対処法を紹介します。
なぜ嫌な夢ばかり見るのか?
夢の内容は個人差があり、ポジティブな夢ばかり見る人も存在します。もちろん、ストレスや不安が多いと悪夢を見やすくなるので、リラックスする習慣を持つと、夢の質が変わる可能性があります。しかし、そもそも夢の約65%〜80%がネガティブな要素を含むと言われており、ポジティブな夢よりもネガティブな夢の方が見やすいものです。これは、人間の脳が危険に対処するために、夢を通して危険をシミュレーションし、現実世界での対応力を高める役割があるのかもしれません。
悪夢とDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)回路の関係とは?
DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)とは、脳が安静時や内省しているときに活動する神経回路のことです。主に以下のような役割を持っています。
・記憶の整理や思い出の回想
・自己意識や他者との関係性の認識
・将来のシミュレーションや問題解決の準備
私たちが夢を見ることが多いレム睡眠の間にDMNが活発になることが分かっています。脳が内省し、危険を趣味レーションしたり、問題解決をしたりしていると考えられています。そして、レム睡眠中は、感情に関わる扁桃体が活性化しやすいのですが、同時に理性を司る前頭前野の活動は覚醒時に比べて低下しています。この状態で、日中のストレスや不安、過去のトラウマが処理されると、悪夢になりやすいと考えられています。
瞑想は悪夢に効果がある?

瞑想と悪夢の直接的な研究はあまり報告されていませんが、以下の点から有効な可能性が考えられます。
DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)の活動を整える
瞑想はDMNの過剰な活動を抑え、思考の暴走を防ぐ効果があります。
扁桃体の過剰な反応を抑える
悪夢はストレスや不安を処理する過程で発生しやすく、特に扁桃体が過剰に反応すると、恐怖を伴う夢になりがちです。瞑想を習慣化すると、扁桃体の活動が落ち着き、ストレス耐性が向上すると言われています。
また、「慈悲の瞑想」という瞑想法がPTSDに有効という研究結果があります。このように瞑想が悪夢に効果的な可能性がある一方で、注意も必要です。瞑想によって無意識に押し込めていた感情やトラウマの蓋が開き、悪夢を見るようになる場合があります。過去につらい経験がある場合、今まで瞑想をしていて感情が強くなったり、ぼーっと切り離された状態になった経験がある人は、実施する前に専門家に相談しましょう。
※参考: Loving-Kindness Meditation for Posttraumatic Stress Disorder: A Pilot Study
なんとなく嫌な夢を見る時の対処法
①脳が記憶を整理するプロセスだと考える
嫌な夢を見るのは、脳が記憶を整理しようと頑張っている事です。嫌な夢ばかり見る時に、「自分はストレス管理ができていない」「過去を乗り越えられていない」と考えずに、「脳が頑張って記憶を整理しているんだ」「前に進もうとしているんだ」と捉えてみましょう。

②過去は過去と意識する
現在とは関係ない過去のつらい出来事を夢で見る場合は、日中、意識的に「あれは過去のこと。現在は安全」「今の自分とはもう関係ないこと」と切り離したり、「当時の自分はよく頑張ったな」と認めてあげたりすると、少しずつ夢に影響が出る場合があります。
③ポジティブなイメージを思い浮かべる
寝る前に楽しかった思い出や、好きなこと、安心すること等のポジティブなイメージをしましょう。想像しづらい場合は、楽しかった思い出の写真を眺めたり、好きなキャラクターや推しのグッズを眺めて、温かい気分になってから寝ることもオススメです。
④慈悲の瞑想を続ける
慈悲の瞑想(他者や自分に対して思いやりを向ける瞑想)は、ネガティブな感情を和らげ、ポジティブな感情を増やします。その結果、夢の内容もポジティブな方向に変わりやすくなると考えられます。瞑想はすぐに効果があるものではなく、続けることが大切です。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く