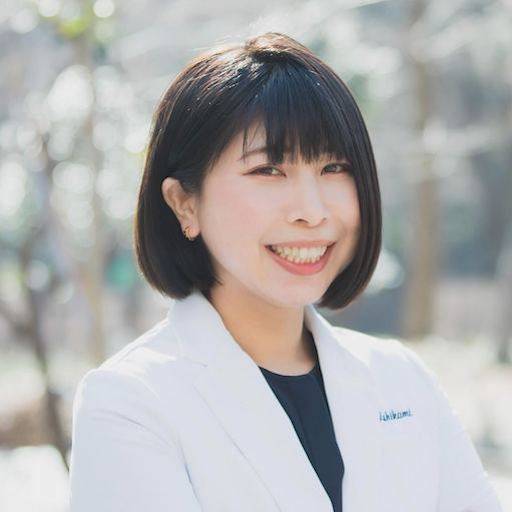パワハラ、なぜなくならない?臨床心理士が考えるパワハラが起こる原因

パワーハラスメントは、なぜ無くならないのでしょうか。パワーハラスメントに関する法律や制度が整うことで、その数は減ったかもしれません。しかし、完全に防ぎきることはなかなか難しいようです。今回は、パワーハラスメントが起こる原因について考えてみましょう。
パワーハラスメントはなぜ無くならないのか
パワーハラスメントの数は減ったとしても、完全に防ぐことは困難なようです。その理由は、人を動かしているのは法律や制度、あるいは仕組みといった環境面だけではないからです。私たちは環境面よりも、信念や価値観などの認知、感情にもとづいて行動することが多いものです。パワーハラスメントが起きづらいように環境面を整えることは大切です。しかし、それだけでは足りないのです。
自信がなくて有能な部下をパワーハラスメントしてしまったAさん
A係長は劣等感があり自信がないタイプです。しかし、自信がないことを知られてしまうと、係長としての能力がないと思われそうだと感じ、自信があるような強気な態度に出ることがあります。A係長のもとに評判のよい有能な部下が配属されました。その部下は自分よりも能力や自信がありそうに見え、その堂々とした態度を見ていると気持ちがざわざわとします。A係長は、部下の取るに足らないようなミスを見つける度に呼び出し、問い詰めるようになりました。A係長は、無意識のうちに自らのコンプレックスが刺激され、その反動としてパワハラ行為に及んでいることに気づけませんでした。
このように気が強い人がパワーハラスメントをするわけではなく、弱い一面を持っている場合があります。相手のミスを過度に指摘し攻撃することで、自分が優位に立っている感覚が得られます。弱みを見せないように心を守る防御として攻撃的な行動を取ってしまう人もいるのです。
自分なりの「正しさ」を押し付けることでパワーハラスメントしてしまったBさん
B部長は、社員は「こうあるべき」という理想がはっきりしており、業務のやり方や、マネージメントの在り方は、自分の方法が一番優れていると信じていました。自分の新人時代に、厳しい上司に育てられて成長できたという自負があり、同じように厳しく指導すると決めていました。そのため、どのような部下にも厳しい態度で接し、部下から効率的なやり方や柔軟な方法を提案されても認めず、時代の変化やそれぞれの部下に合わせた対応をしませんでした。部下が様々な提案をしても首を縦に振らず、自分なりの「正しさ」に合わないものは認めないことで、部下の仕事は進まずに職員は疲弊してしまいました。
「正しくあること」は大切なことですが、その正しさが独りよがりになっている場合があります。法律や社会のルールなど、みんなで守ることはあります。しかし、個人的な価値観を押し付けて、人をコントロールすることはできません。現在は多様性が重視される時代です。様々な価値観が認められ、それぞれに合った対応をしていく「柔軟性」が求められているのです。
怒りの感情の後ろにある気持ちに目を向ける
コンプレックスが刺激されたり、自分の思い通りにならなかったりすると、人は怒りを感じます。このような場合、怒りの背後には、別の感情が隠れている場合が多いです。例えば、「不安」「恐れ」「焦り」「劣等感」などがあるでしょう。背後に別の感情が隠れている場合は、その感情を癒さない限り、怒りは強いままです。不安や恐れなら安心させる、焦りなら落ち着かせる、劣等感なら自信を持たせることでしょうか。もし自分がパワハラをしている自覚があるのなら、背後にある気持ちに注目して自己対処することです。そうすることでイライラや怒りが小さくなるでしょう。
今回はパワーハラスメントについてお伝えしました。このように法律や制度など環境面が調整されてもパワハラはすぐになくなるわけではありません。そして、パワハラを受けている側が相手の心理や背後にある気持ちに気付いても、1人で対処することは難しい場合が多いものです。そのため、パワハラを受けていると感じたらあなたの健康が害される前に早めに相談しましょう。- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く