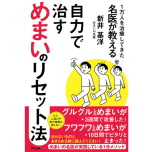1万人のめまい患者を救った名医が教える、めまい症状が悪化する〈NG食習慣〉と正しい食べ方

2022年の厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、めまいを訴える人の数は、約248万人にものぼると言われています。日本でも数少ないめまいを専門とする医師、新井基洋さんの著書『1万人を治療してきた名医が教える 自力で治すめまいのリセット法』(アスコム)より、めまいを改善・予防する食べ方を一部抜粋してご紹介します。
食事を変えると「めまい体質」は改善できる
体は食べたものでできています。体によいものを食べれば元気になるし、悪いものを食べれば不調になります。体調が悪いときにめまいは起こりますから、みなさんには、体によいものを食べることは、めまいに強い体づくりの土台と考えてほしいと思っています。たとえば、見た目が立派な家でも、土台がしっかりしていないと、安心して住むことはできませんよね。体も同じです。見た目は筋骨隆々(きんこつりゅうりゅう)で丈夫そうなのに、いつも風邪をひいたりしている人がいませんか。それは、土台となる食事に問題があることが多いのです。ですから、めまいの患者さんにも「めまいを治すためには、食事に気をつかうことが大切ですよ」と伝えるようにしています。食事の基本は、多くの種類の食べ物をバランスよく食べることです。そのうえで、 めまいの人に積極的にとっていただきたい栄養素がありますので、ご紹介します。
「カルシウム+α」の食事で骨粗しょう症を防ぐ
私の病院で、めまいが原因で入院をした50歳以上の人を対象に、骨密度を検査したところ……めまいで悩む人は、 めまいのない人よりも、 (男女とも)骨粗しょう症になる人が、2倍以上も多いことがあきらかになりました。骨を強くするのに必要な栄養素は、ご存じのとおりカルシウムです。カルシウムを含む食品を意識的にとるようにしましょう。とくに良性発作性頭位めまい症のような耳石が関わる病気の人は、しっかりカルシウムをとるようにしてください。
耳石の主成分は骨と同様、炭酸カルシウムです。つまり、耳石も骨と組成が同じで、カルシウムが不足するともろくなって、はがれ落ちやすくなるということです。しかし、カルシウムだけを大量にとればいいのかといえば、そうではありません。カルシウムはとても吸収率の低い成分で、カルシウムだけをとっても材料としてうまく使われません。そのため、カルシウムを助ける成分を一緒にとらなくてはならないのです。まずはタンパク質です。髪の毛、皮膚から体のあらゆる組織の細胞まで、材料になるタンパク質が不足していれば、骨もつくることができません。タンパク質は、体のバランスをたもつために必須の筋肉づくりにも欠かせません。筋肉が不足すると体の安定性が損なわれ、めまいのリスクが高まるため、過不足なくとることが大切です。
また、カルシウムの吸収を促し、骨の材料として効率的に使われるようにする「ビタミンD」、カルシウムの骨への沈着を促して骨をつくる細胞のはたらきを活性化する「ビタミンK」という成分も必要です。次に耳石のトラブルを防ぐうえで有効な栄養を含む食品をご紹介していますので、毎日の食卓に取り入れるようにしてください。
カルシウムを多く含む食品

牛乳、ヨーグルトなどの乳製品、しらすなどの小魚、豆腐などの大豆製品、海藻、緑黄色野菜
タンパク質を多く含む食品

牛乳、ヨーグルトなどの乳製品、肉、魚介類、豆腐などの大豆製品
ビタミンDを多く含む食品

干ししいたけ、きくらげなどのキノコ類、鮭などの魚類、卵
ビタミンKを多く含む食品

ブロッコリー、ほうれん草、モロヘイヤ、小松菜、納豆
片頭痛性めまい患者は要注意「ポリフェノール&チラミン」
「ポリフェノールが体にいい」という、なんとなくの印象を持っている人は多いと思います。しかし、片頭痛性めまいの人は、ポリフェノールを多く含むチョコレート、ぶどうジュース、赤ワイン、オリーブオイルなどは控えたほうがいいでしょう。ポリフェノールには血管を拡張させる作用があり、片頭痛を誘発しやすいためです。もうひとつ注意してほしいのがチラミンです。こちらの成分は血管を収縮させる作用があるのですが、収縮したあとに急激に血管が拡張します。そのときに片頭痛が起こるのです。チラミンを多く含む食品は、熟成チーズ (チェダーなど) 、 ワイン、 チョコレート、ビール、サラミ、燻製(くんせい)にした魚肉などです。血管を収縮させるカフェインを含む、コーヒーや緑茶などの飲み物は、片頭痛の症状を緩和させる作用があります。ただし、カフェインをとりすぎると、頭痛や睡眠の質の低下などを引き起こすため、飲みすぎは避けましょう。
めまいの大敵は「甘いものと塩」のとりすぎ
脳の障害が原因の中枢性めまいにならないようにするには、動脈硬化を防ぐことが重要です。動脈硬化を防ぐ最善策は、高血糖と高血圧にならないことです。高血糖とは、血液の中の糖の量が異常に増えてしまっている状態です。高血糖になると血糖値が高くなります。この状態が続くと、血管がもろくなって動脈硬化が進み、糖尿病のリスクが高まります。糖尿病になると、全身の血管障害が生じるため、バランスの要でもある内耳につながる動脈にも影響がでて、めまいの原因となることもあります。甘いものや、ごはんなどの炭水化物のとりすぎを避けるのは、高血糖を防ぐ基本中の基本ですが、ほかに、糖の吸収を穏やかにするため、食事のときに野菜などの食物繊維が豊富な食品を先に食べることも意識してください。
もういっぽうの高血圧の最大の予防策は、なんといっても「減塩」です。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準2020年版」における食塩摂取の目標量は、
・成人男性 1日7.5g未満
・成人女性 1日6.5g未満
日本高血圧学会では1日6g未満を推奨しています。普段から減塩調味料を使用する、塩分の多い加工食品・インスタント食品・スナック菓子などを食べすぎないことを心がけましょう。また、過剰な塩分摂取は、体内に余分な水分がたまる原因になります。そのため、内耳が水ぶくれ状態になることが原因のメニエール病の人は、減塩が必須です。

ポイント「めまい体質」を変える食事術
・多くの種類の食べ物をバランスよく食べる
・とくにカルシウム、タンパク質、ビタミンD、ビタミンKをとる
・片頭痛の人は、ポリフェノールとチラミンはNG
・甘いものと塩分は控えめに

この本の著者/新井 基洋(あらい・もとひろ)
1964年埼玉県生まれ。入院治療約1万人、外来・再診を含めると、のべ約25万人の難治性めまい患者や、「めまい難民」たちを救ってきた。これらの功績を他の医師 たちから評価され、3期連続「Best Doctors」を受賞。1989年北里大学医学部卒業。国立相模原病院、北里大学耳鼻咽喉科、横浜市立みなと赤十字病院耳鼻咽喉科部長を経て、現在めまい平衡神経科部長。日本めまい平衡医学会専門会員、代議員。1995年に「健常人OKAN(視運動性後眼振=めまい)」の研究で医学博士取得。1996年、米国ニューヨークマウントサイナイ病院において、めまいの研究を行う。北里方式をもとにオリジナルのメソッドを加えた「めまいのリハビリ」を患者に指導し、高い成果を上げている。『めまいは寝てては治らない』(中外医学社)、『最新版 薬に頼らず自分で治す! めまい・ふらつき』(宝島社)、など多数の著書がある。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く