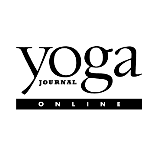ヨガの練習でけがをしないために【けがを予防する5つのウォームアップ】

ヨガジャーナルアメリカ版の人気記事を厳選紹介!ヨガが深い癒しをもたらす場合もあれば、けがを引き起こしたり、痛みを悪化させる場合もある。今も、これからも安全にヨガを練習するにはどうすればいいか、世界トップクラスのヨガティーチャーたちにたずねた。
股関節や胸を開く時の解放感や、太陽礼拝で活力がみなぎるのを感じたことがある人は、ヨガは良い気分をもたらしてくれる、と迷わず言うだろう。一方で、練習では不快感を伴うポーズもある。だがそれらは、自分自身や身体的、心理的、感情的な抵抗について理解を深める手がかりになる、と1971年からヨガを教えているジュディス・ハンソン・ラサター理学療法士は言う。「ヨガの実践で得られる恩恵は無限ですが、ある程度のリスクも伴います」
ある研究によると、45歳から64歳でヨガ関連のけがをした人は2001年から2014年の間に2倍に増え、65歳以上では8倍に達していた。おそらく高齢になるほど脊柱の疾患や、骨密度、柔軟性の低下といったけがの誘因が増えるためと考えられる。また、ヨガティーチャーの急増によって、標準化されたトレーニングが十分に行き届いていないことも一因だろうと研究者たちは述べている。
では、体を痛めずに癒しの効果を得るにはどうすべきか? それはマットを広げてからシャヴァーサナ(亡骸のポーズ)で至福を感じるまで、けがをしないという意志をもって練習を行うことだ。その方法を紹介しよう。
けがを予防する5つのウォームアップ
Tune Up Fitness Worldwideの共同創始者で『The Roll Model』の著者のジル・ミラーは、クラスのはじめに太陽礼拝を数回行っても、アーサナ練習の十分な準備にはならないだろう、と語る。「ほとんどの人は、一日中座っていた状態からヨガマットの上に立ち、体が思いどおりに動くことを期待しています。ですが筋肉や体にはかなりの負担がかかります」と彼女は言う。「それは自分でけがを招いているようなものです」
たとえば、アドームカシュヴァーナーサナ(下向きの犬のポーズ)のような一見基本的なポーズでも、一日中キーボードを打ったり電話を握っていた腕や手首や手に体重の大部分をかけることになる、とミラーは言う。
安全な練習を長く続けるには、ヨガの前に適切な準備運動を取り入れて、けがの予防や弱い部分をサポートする必要がある。今回ミラーは、特にけがが起こりやすい部分のための5分間ウォームアップを紹介してくれた。忙しくて時間がとれない?それならいちばんトラブルが起きやすい箇所を優先して行おう。

1.手首
ほとんどの人は手関節伸筋(肘から前腕裏側に沿って手首まで伸びる筋肉)が弱い。そのためダウンドッグでの45度の角度や、ウールドゥヴァムカシュヴァーナーサナ (上向きの犬のポーズ)で90度に曲げる時に手首にかかる圧力に耐えられない場合がある。
【ウォームアップ】
四つん這いになる。右手のひらの下、親指と人差し指の間に筋膜マッサージボールを置き、上から押す。30秒たったら、親指と人差し指を互いに近づけてボールに圧力をかける。必要に応じて圧力を調整する。30秒たったら、手のひらの下でボールを転がして全体をマッサージする。反対側でも繰り返す。手の筋肉を刺激することで前腕、肩、体幹の筋肉が働き、体重を支えるポーズでの手首への負担を軽減できる。
2.肩
コンピューターの前で背中を丸めたまま何時間も過ごしていると姿勢が崩れ、たとえばダウンドッグ、プランク、アップドッグと動く際に、適切なアライメントをとりづらくなる。
【ウォームアップ】
立った状態で、両腕を肩の高さから真っすぐ前に伸ばし、両手を体の幅よりやや広げてストラップをぴんと張って持つ。ストラップを頭上に上げ、快適な範囲で腕を後方に反らしたら、ストラップがゆるまないようにしながら体の前に戻す。この動きを5~10回繰り返す。この運動では、腕上部を持ち上げるときはできるだけ内旋、後方に反らせるときは外旋させて肩を活性化し、アーサナ練習で無理なく動くための準備を行う。
3.股関節
長時間座っていると臀筋がゆるんで股関節とのアライメントが崩れ、筋膜が広がってしまう。その結果、骨盤周辺の安定性が低下してけがのリスクが高まる。「変に聞こえるかもしれませんが、ヨガ練習の前にお尻をお尻の上に戻す必要があります。つまり、臀部の筋肉と筋膜を仙骨に向かって押し戻すのです」とミラーは言う。
【ウォームアップ】
筋膜リリースボールを縦に2つ並べて、右腰の肉厚な部分にボールがあたるように仰向けになる。ボールに圧を加えながら仙骨のほうに転がして、臀筋を体の中心に向かって動かす。最大5分繰り返したら、反対側でも行う。立ち上がったときに、より楽に臀筋を引き締められるはずだ。

4.背中
デスクにかがむように座っていると、背骨が大きくCの字に曲がる。これにより、脊柱起立筋(良い姿勢を保つための、脊椎に沿って走る筋肉群と腱)が過度に伸ばされてしまう。その結果、脊柱起立筋がゆるみ、ウールドゥヴァハスターサナ(手を上にあげるポーズ)やウッターナーサナ(立位前屈)のようなポーズで脊柱を曲げづらくなる。
【ウォームアップ】
マットの短い辺を壁につけて敷く。仰向けに横たわり、足の拇指球で壁を押す。両腕を体側に伸ばしたまま腰骨を胸郭のほうに傾け(骨盤後傾)、腹筋運動のように腹部を引き締める。腕を使わずに、ゆっくりと背骨を1つずつ床から浮かせていく。下りるときは腰椎から1つずつマットに下ろし、この動作を5回繰り返す。シンプルな動きによって脊柱起立筋が活性化され、ヨガ練習中も脊椎を安全に保てる。
5.膝
ほとんどのヨガティーチャーが、大腿四頭筋を働かせるように指導するのには訳がある。大腿四頭筋が力強く働いていると、膝関節を真ん中に保ちやすく、ヨガ練習中にスクワットをしたり、曲げたり、ランジをしたり、真っすぐ伸ばしたときに、適切なアライメントを維持できるからだ。
【ウォームアップ】
ダンダーサナ(杖のポーズ)の姿勢で座る。両足を広げ、股関節から脚を外側に回転させてV字に開く。右膝を完全に伸ばしきった状態で、右脚を床から数cm浮かせ、大腿四頭筋が働いているのを感じよう。10秒間ホールドしたら脚を下ろし、反対側でも繰り返す。内側広筋(膝を伸展させる内側の大腿四頭筋)がけいれんする場合は、4秒ホールドすることから始め、徐々に長くしていく。
深めるほど良いとは限らない
イメージどおりにあのポーズができるようになりたいという欲望は、ほとんどのヨギが遅かれ早かれ抱くものだ。それがけがにつながる場合が多い。現代解剖学と伝統的なヨガ哲学に基づくヴィンヤサスタイルのヨガ、SmartFLOWの創始者であるアニー・カーペンターは「ポーズでの見た目や感じ方はこうあるべきというエゴにとらわれると、体が伝えようとする知的で直感的な情報に気づけなくなります」と言う。
解決法:すべての動作は、いちばん極端な動きと逆に引き戻そうとする動きの連続だと考えてみよう。多くの人はポーズの形をとることに必死になりすぎて、ゆるめることを忘れがちだ。それがけがにつながる、とカーペンターは言う。ヨギの多くが限度を超えがちだと彼女が考える3つのポーズについて、より安定して安全に練習するためのポイントを紹介しよう。
ヴィパリータナマスカーラ(背中で合掌のポーズ)
傾向:背中で手を合わせるために上腕骨を内旋させ、胸部がへこんでしまう。
安全策:両腕を後ろに伸ばして手のひらを上に向け、肩幅の輪にしたストラップを両手首にかける。手首でストラップを外側に押しながら、上腕骨を外旋させ、肩甲骨を下げる。このとき肋骨下部が前に出ないようにする。ここまでできたら、腕を上下に動かす(数cmでもかまわない)。それができたら手の指を組んで手のひらで押し合う。最後に、背中で合掌してみよう。
その理由:上腕骨を外旋させないと肩が前に倒れて頸椎を圧迫し、胸を開くポーズの効果が薄れてしまう。
◎上腕を外旋させて、安全に胸を開く。

セツバンダサルヴァーンガーサナ(橋のポーズ)
傾向:腰を高く持ち上げるために、太腿の外側を中央に寄せすぎたり、あるいは、膝を開きすぎてしまう。
安全策:橋のポーズに入ったら、太腿の間にブロックを入れ、強く挟んでから力を抜く動作を数回繰り返す。このとき脚の内側(内転筋)が強く働いているか確認する。今度は太腿の真ん中にストラップスをかけ、ぴんと張るように脚を左右に押しだす。このとき太腿の外側(外転筋)が強く働いているか確認する。次にプロップスを使わずにポーズを試し、脚の内側と外側の筋肉を均等に働かせるようにする。
その理由:ポーズ中に微調整するには、内転筋、外転筋の感覚をそれぞれ別に確かめる必要がある。双方が均等に働くと骨盤が安定し、膝や腰を安全に保てる。
◎腰を持ち上げるときに膝を広げすぎない。

アルダチャンドラーサナ(半月のポーズ)
傾向:体を引き上げようとして、立っている脚の膝を過度に伸ばしてしまう。
安全策:マットの上に立ち、足の指先にやや体重をのせ、かかとをマットから1cmほど浮かせてから、かかとをマットにおろす。この時、ふくらはぎ上部の筋肉が前方に動いた感覚があるだろうか。その状態を維持しながら、膝頭を引きあげ脚を真っすぐにする。
その理由:立っている脚の背面全体を強く働かせると、膝が過度に伸びなくなる。
◎ふくらはぎ上部の筋肉を前方に押し、脚の背面の筋肉すべてを強く働かせる。

けが予防のためのオンラインフィットネス
オンラインフィットネスの「ペロトン」のヨガインストラクター、チェルシー・ジャクソン・ロバーツ医学博士は、インストラクターがそばにいない場合のけが防止のためのアドバイスを提供している。

エゴよりも体の声に耳を傾けよう
立位前屈でつま先に触れようとするときもヘッドスタンドでバランスをとろうとするときも、無理に自分を追い込めばけがが待ち受けている。
呼吸を観察し、すごく頑張っている状態と、あまり(あるいはまったく)無理をしていない状態の中間点を見つけよう
ポーズ中に呼吸が早くなっていたら、ポーズを少しゆるめる。逆にオンラインレッスンでヨガティーチャーに言われてウトゥカターサナ(椅子のポーズ)をホールドしながらも、ほかの部屋にいる子供と会話ができるようなら、もう少し腰を下げたほうがいいだろう。
さまざまなヨガティーチャーのクラスを試そう
いつも同じクラスを受けていると、同じタイプの動作を繰り返しすぎたり、適切な姿勢で練習する意識が薄れるために、使いすぎによるけがを引き起こす場合がある。シークエンスの組み立てやピークポーズはヨガティーチャーによってさまざまだ。異なるクラスやティーチャーを試すことによって今まで気づかなかった繊細なレベルでの気づきが得られるかもしれない。
プロップス(補助具)を利用しよう
このポーズで自分をサポートするには何が必要?と絶えず自分に問いかけよう。多くの場合、それはブロック、ストラップ、ブランケットを用いたサポートを意味する。必要なプロップスを家に揃えておこう。
アライメント神話
私は世界中でヨガを教えていますが、クラスで一般的に教える原則の中には、解剖学的な事実に即していないものがたくさんあると気づきました」と、『Yoga Myths: What You Need to Learn and Unlearn for a Safe and Healthy Yoga Practice』の著者ラサターは言う。「そういう原則は誰のためにもならないし、むしろ害をもたらす場合もあります」。ラサターの言う、すぐにやめるべき原則をここでは2つ紹介しよう。
1.「ターダーサナ(山のポーズ)で尾骨を中に入れる」
これを行うと下部脊椎の自然なカーブがゆがんで仙骨と腸骨(骨盤の左右の大きな骨)の間の仙腸関節(SI)が不安定になり、腰痛を引き起こす場合がある。また、胸骨を過度に持ち上げてバランスをとろうとすると胸椎の後弯カーブが平らになり、ニュートラルな立位姿勢としては負荷がかかりすぎてしまう。
解決法:部屋の中で、梁など角になる所を見つけ、角に背中を向けて立つ。足を腰幅よりやや広く平行に開き、尾骨、背骨の中央、後頭部を壁側の角にあてる。あごを床と平行にしたら数回呼吸をし、楽に呼吸ができているか確かめる。横隔膜は第1腰椎に付着しているため、腰椎を自然な曲線に保つと、より楽に呼吸ができるようになる。
腰椎が自然なカーブを描いているとき、仙骨は30度ほど傾いている。

2.「両腕を上に伸ばしながら、肩を背中のほうに下げる」
肩関節を理解するには、上肢の動きのカギである肩甲骨を知る必要がある。次の動作を試してみよう。立ったまま、肩甲骨の自然な動きを妨げずに片方の腕をゆっくりと横に持ち上げる。動作の始めでは肩甲骨はほとんど動かないが、腕を上げていくにつれて肩甲骨が上がって回転するのが感じられるだろう。肩甲骨のこれらの動きが肩関節の正常な屈曲動作につながり、けがの防止に役立つ。
解決法:両腕を頭上に伸ばすときは、高い棚の上にある欲しいものに手を伸ばすイメージでやってみよう。動作について頭で考えずに思いっきり伸ばすこと。すると、肩甲骨の外側や外側縁が上がることに気づくだろう。その状態で、肩関節が無理なく動く感覚を確かめよう。
正常な肩甲骨の動きを感じるには、高い棚にある物をつかむように手を伸ばす。

けがからの回復
2回目の股関節置換手術の4日後、ヨガティーチャーのシンディ・リーはベッドから起き上がり、呼吸をしながらゆっくりと体を動かしてみた。ニューヨークのOMヨガセンターの創設者は、これらのシンプルなポーズによって、ヨギとしてのアイデンティティだけでなく、身体感覚が戻ってくるのを感じた。「体を切り開かれて、ばらばらにされると、体との一体感を得にくくなります」と彼女は言う。「どんなにシンプルな動きでも、呼吸と調和させると体とマインドがまとまり、統一感が戻りやすくなります」

シンプルな腕の動きを合わせた呼吸法
ベッドか快適な椅子の端に座り、背中を真っすぐにして両足を地面につける。4カウント(快適であればさらに少ないカウント)で息を吸い、4カウントで息を吐く。呼吸を同じ長さで数回行ったら、腕の動きを加える。息を吸いながら腕を横から上げて、耳に近づける。吐きながら腕を腰の横に下ろす。これを好きなだけ繰り返す。
穏やかなサイドベンド
息を吸って左腕を横から頭の上まで持ち上げ、上腕二頭筋が耳の横にくるようにする。息を吐きながら、上体をゆっくりと右に傾けて、左の体側を伸ばす。息を吸いながら再び真っすぐに立ち、反対側でも繰り返す。この基本的な動きによって、肺、胸郭、背中が開かれる。これらの箇所は、長時間ベッドで寝ていると、硬くこわばってしまうことがある。
穏やかなねじり
ベッドか快適な椅子に座り、息を吸いながら、左腕を横から頭の上に持ち上げ、上腕二頭筋が耳の横にくるようにする。息を吐いて上体をゆっくりと右にねじり、左手は前に下ろして右の太腿にのせ、右手はベッドか椅子の後方につく。あまりねじりすぎないように注意しながら、このまま数回呼吸をする。吸う息で元の姿勢に戻り、反対側でも繰り返す。
腕の活性化
息を吸って、両腕を左右から横に持ち上げ、肩の高さに保つ。息を吐きながら、両腕を外旋させて、手のひらを天井に向ける。息を吸い、両腕を内旋させて、手のひらを床に向ける。この動作を呼吸とともに30秒から1分続ける。
シンプルなチェストオープナー
息を吸って、背中の後ろに両手を伸ばし、指を組む。この姿勢のまま、均等な長さで呼吸をする。胸を引き上げ、肩甲骨同士を近づけるように意識する。
ガルーダーサナ(ワシのポーズ)の応用
息を吸って両腕を前に、床と平行に伸ばし、肩甲骨を左右に広げる。息を吐いて右腕を左腕の上に重ねたら、両肘を曲げて前腕を床に垂直に立て、手の甲同士を合わせる。均等な長さで呼吸をし、肘を持ち上げて、指を天井に向かって伸ばす。このまま少なくとも30秒ホールド。反対側でも繰り返す。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く