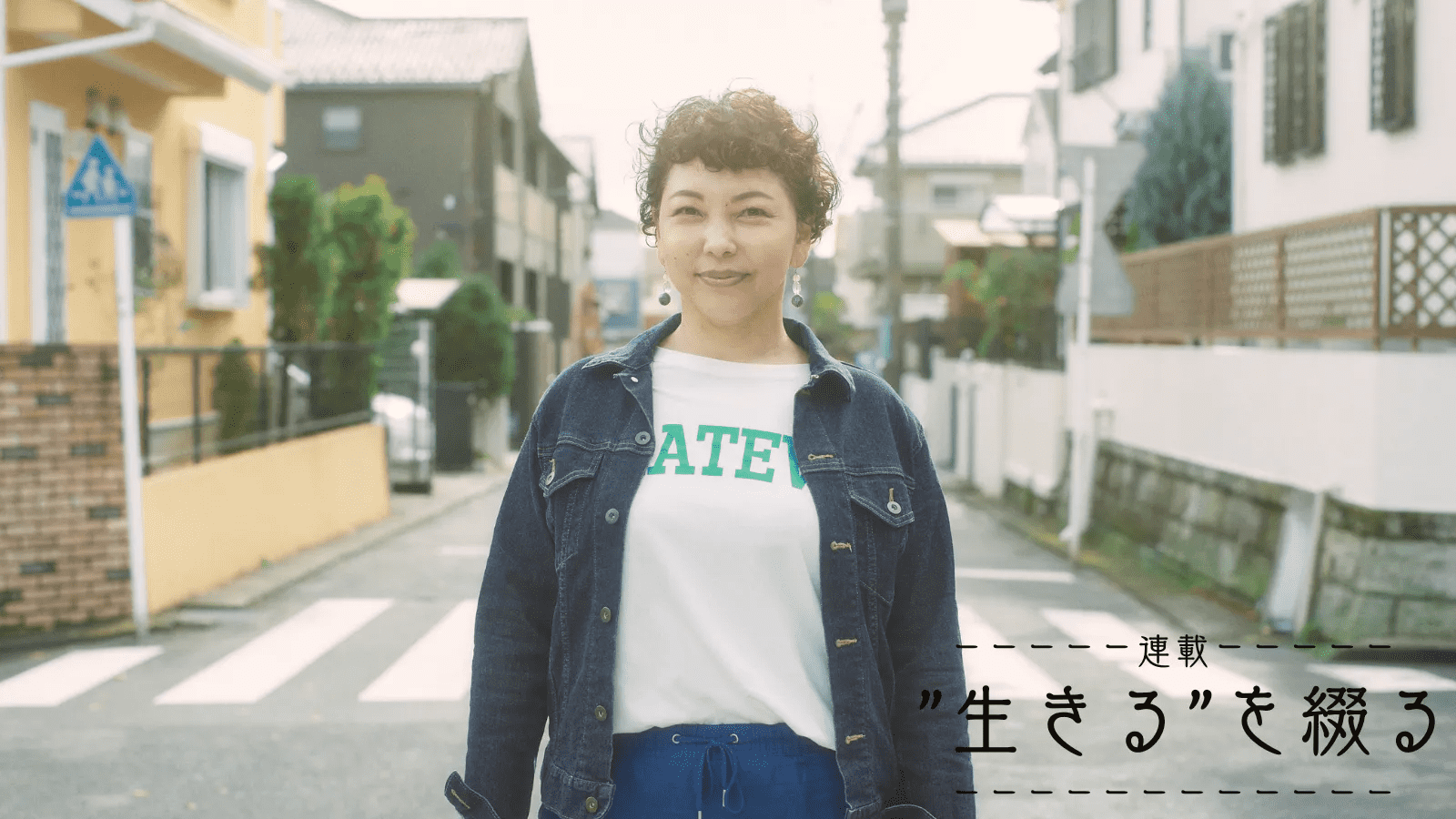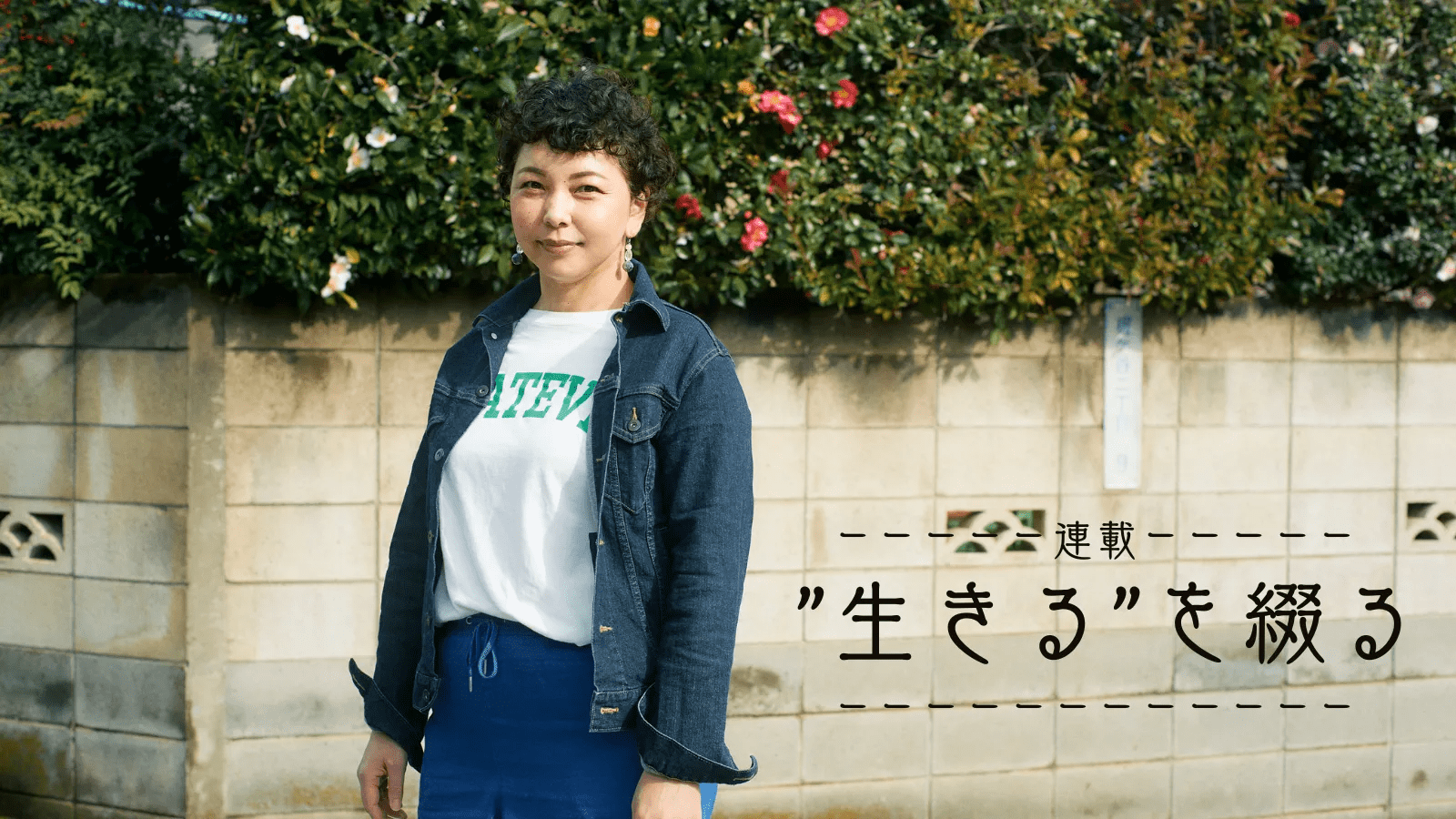ずっと「親孝行」という言葉に苦しめられてきた。わたしの介護経験を振り返って|#"生きる"を綴る

ピラティスインストラクターの宮井典子さんは、全身性エリテマトーデス(SLE)患者としてメディアで啓蒙発信しながら、心地よい暮らしと働き方を模索しています。そんな宮井さんによるエッセイ連載『"生きる"を綴る』、今回は宮井さん自身が若かりし頃に経験したご両親への介護を振り返る、後編です。
前回のエッセイを書き終えてから気づいたことがありました。
長い間忘れようとしていたのか。それとも思い出さないようにしていたのか。
なぜ"死んでもできる親孝行"がこんなにも心に突き刺さったのか。なぜ響いたのか。
自問自答していく中で、わたしは、ずっとずっと親孝行という言葉に苦しめられ、ひどく傷ついていたことを思い出しました。
母を看取ったときも、父を見送ったときも、誰からも泣くことを許されなかった。ドラマのように悲しみに浸る余裕は全くなく、やるべきことをこなしていく現実と突然襲いかかる喪失感に耐えられなくなったときもあったけど、そこにいた大人は決まってこんなふうに声を掛けてくるのです。
母のときは「泣いていないで、お父さんを支えてあげてね」。
父のときは「いつまでも泣いていたらお父さんも心配するよ」。
繰り返される大人の声をかき消すように、一心不乱になって目の前の手続きを進めることしか出来ませんでした。
それからというもの「早くお父さんとお母さんを安心させてあげて」「そろそろ供養しないとお父さんとお母さんが悲しむよ」呪文のようなそれらの言葉にまさか強いダメージを受けていたなんて、誰ひとり気付いていなかったことでしょう。
大人が言う「安心」や「供養」は「お墓を建てる」ということで、その決断は当時のわたしにとって厳しくて難しいものでした。
そこでお世話になっていた住職さんに相談し、お墓は建てないと決めて東京に移り住んだのですが、どれだけ距離をとっても、どれだけ時間が過ぎようとも、容赦なく呪文のような言葉がなくなることはありませんでした。
父でもない母でもない人に「親不孝娘」と言われてる気がして、心底つらかったのです。
お墓はないのでお墓参りという供養はできないけれど、両親それぞれの月命日と命日は忘れたことはありません。けれど親不孝のレッテルを貼られたような気がしたわたしは、親戚の誰とも連絡を取らなくなってしまいました。
長い空白期間を経て、当時を振り返り、記憶をたどり、苦しかった想いを吐き出せたのも"死んでもできる親孝行"に出会えたから。わたしにとって天から降りてきた救いの言葉です。
一節を読み上げたとき、心の奥底にある氷のような塊がパキーンと砕け散ったのを感じました。
わたしはあのとき、泣きたかったし、誰よりも叫びたかった。
親不孝なことはしてないと胸を張って言いたかった。
「助けてほしいときに助けてくれなかったのに今更そんなことを言われる筋合いはない!」と言いたかった。
ずっとずっと言いたかったのに、どれも言えませんでした。
誰ひとりとして悪意があったわけじゃないことも、両親とわたしを心配してのことだったことも、呪文のような言葉にも愛があったのだろうと今なら思えるから、これらの辛い記憶にマルをつけて、終止符を打ちたいと思います。
最後に改めて振り返る時間を作れてよかったですし、貴重な機会をいただけたことに心から感謝しています。
あの言葉が響いた理由は、ただひとつ。わたしはずっと泣きたかったし、叫びたかったんだ。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く