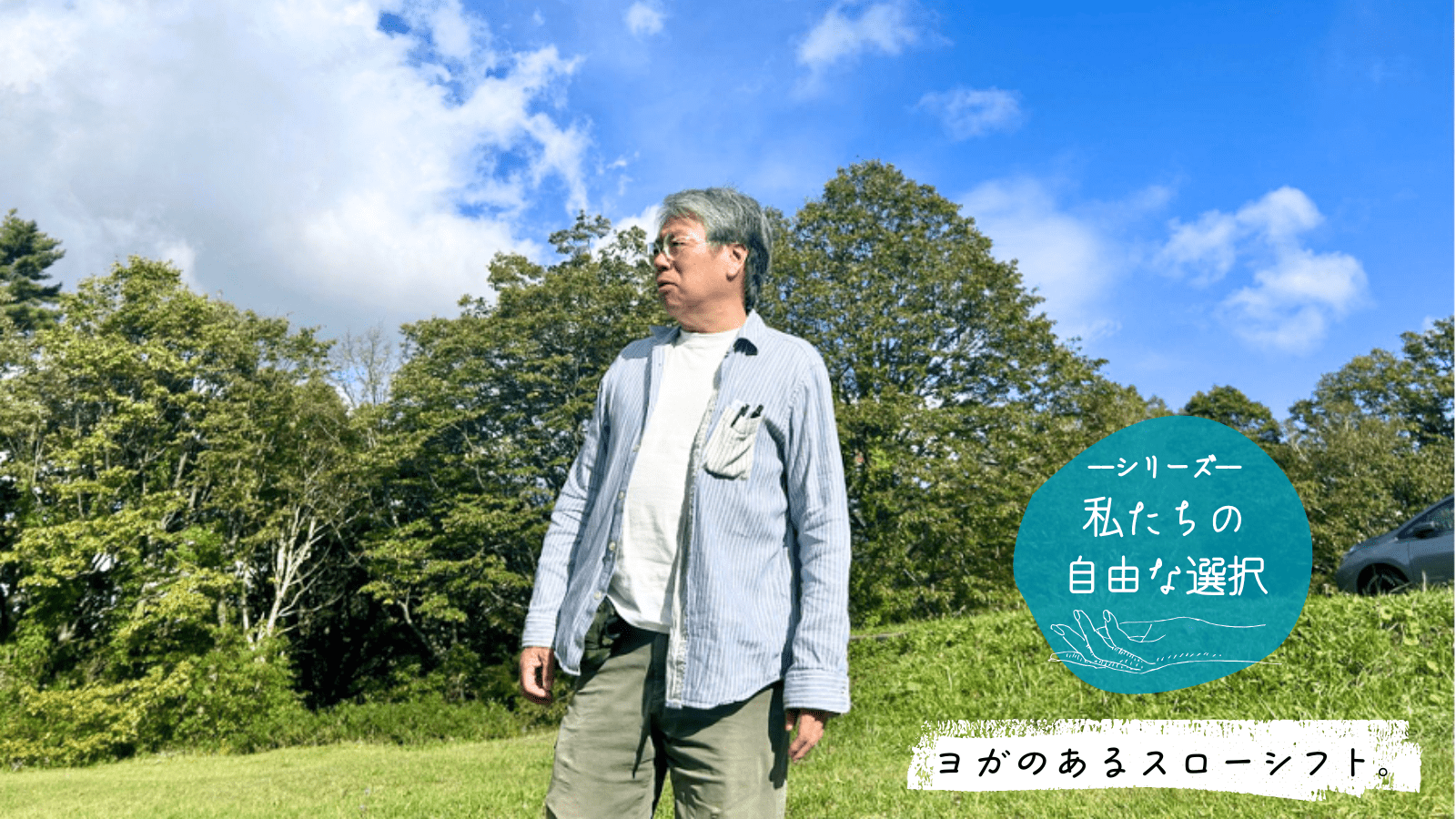デジタルオフが生み出す読み書き時間。アナウンサーを経てカレー屋の大島梢絵さんが毎日ご機嫌な理由


ーーSNSで見る梢絵さんには「読書家」という印象もあります。インスタグラムで本の発信をし始めたのはいつから、きっかけはなんだったのでしょう。
梢絵さん:はじまりは、去年の夏からですね。そもそも、私はたくさん本を読むタイプではなかったので「戦略的に本が好きになりたい」という気持ちから発信を始めました。私はNetflixなども見ないので、インプットも圧倒的に少ない気がして、読書に行き着いたんだと思います。
同時に常日頃、スマホを使い過ぎな部分を自覚していて、デジタルから離れたいという気持ちもあったと思います。「私は何故こんなにスマホを触っているのに、意義のあることを吸収できていないんだろう」って。スマホとの距離感をとりたいために、読書を始めたいと思ったのが強い動機でした。
誰かに見てもらう緊張感がないと続かないとも思ったので「毎日読書チャレンジします!」とインスタで先に(去年の8月から)宣言してしまいました。
好きが高じて「Book Lovers Club(本好きの会)」のインスタアカウントを開設し、イベントも定期で主催することになったんですよ。インスタで呼びかけてみたところ、日頃から石本商店のカレーの常連のお客様も集まってきました。
ーー最近もまた「SNSデトックス始めます!」宣言しているのを投稿で見ましたが、何か心境の変化があったのですか。
梢絵さん:はい。実は今まさに距離の取り方、また見直し中です。最近、SNS上の人を見て自分も発信しなくちゃ、と焦るような気持ちで、心が波立っていることに気づいたんです。
noteや音声メディアでの発信もしているので、発信場所が多くなってきたせいでもあると思います。私なりの解決策として、例えばインスタなら、ストーリーズを開かずに、投稿のためにだけ使ってみるなどを実践しています。
日頃から自分と向き合っていると、SNSと読書、それぞれ時間の使い方に波があるようです。SNSの時間が増えて、読書時間が減ってきたなと気づく時もあれば、ふと、また読書熱が再熱する時もある。
ーーインスタグラムでシェアする選書が情報としても魅力的ですが、梢絵さん自身が大きく影響を受けた愛読書や、これは読んでほしいという若い世代への「推し」の本は。
梢絵さん:もうずっと、糸井重里さんの『ボールのようなことば。』ですね。
10年以上前に発売された本ですが、私は23歳の時に読んで、世界が開けた!と思っているんです。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く