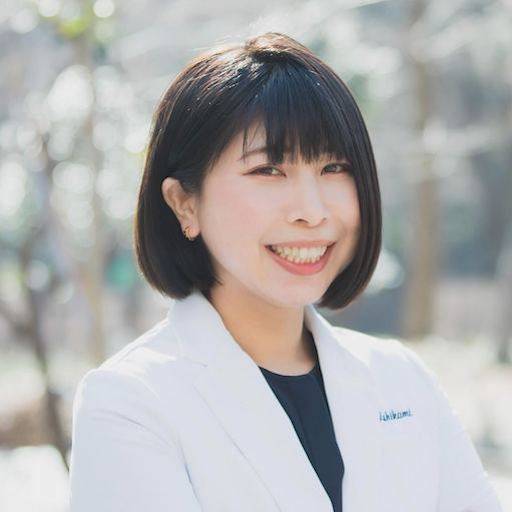「耐性の窓」を知っていますか?"心の専門家"公認心理師が教える、耐性の窓を広げる方法

「耐性の窓」という言葉を聞いたことがありますか?近年トラウマと合わせて「耐性の窓」という言葉を目にする機会が増えてきました。今回は、「耐性の窓」について詳しく解説し、「耐性の窓」を広げる方法について紹介します。
耐性の窓(Window of Tolerance)とは
「耐性の窓」とは、ダニエル・シーゲル博士によって命名されたもので、個人がストレスに対して許容できる範囲のことです。耐性の窓が広いほど、ストレスに対して対処できたり、感情のコントロールを保てたりします。神経系の話でいうと、下の図のように、交感神経系が優位になる過覚醒と、背側迷走神経系による低覚醒の間にある状態です。つまり、適切な覚醒状態にいて、安全、安心を感じていられる状態を指します。私たちはストレスに遭遇すると、緊張・興奮する過覚醒になったり、無気力・うつ状態の低覚醒になったり、上がったり下がったり波を描きます。揺らぎがあることが問題なのではなく、極端になってしまうこと、安心・安全の窓の中に戻ってくれなくなることが問題になります。

トラウマの5Fとは
とてもショックな(トラウマティックな)出来事に遭遇した時、私たちはどのような反応を起こすのでしょうか。トラウマの5Fと呼ばれる反応をご紹介します。
Friendly
まずはコミュニケーションによって友好的に対応しようとします。
Fight
「闘争」反応。脅威に対して戦う行動を取ります。自分や他者を守るための積極的な防御反応です。
Flight
「逃走」反応。危険を感じたときにその場から逃げる行動です。危険から距離を置くための反応と言えます。
Freeze
「凍りつき」反応。戦うことも逃げることも出来ないとき、小動物なら死んだふりをするでしょう。人間の場合は、動けなくなることもあれば、感情を切り離して感じなくする場合もあります。
Fawn
「迎合」反応。脅威に対して従順になることで、危険を回避しようとする行動です。特に対人関係において、攻撃者や支配者に対して従順になることで、暴力やさらなる脅威を避けようとします。
これらの反応は、トラウマやストレスに対する自然な生存本能としての反応です。それぞれの反応は、その時の状況に応じて生じ、全てがその瞬間において適応的な行動と言えます。上記の順番で必ず起こるわけでもなく、どの反応が良い・悪いというものではありません。
耐性の窓の話に戻ると、Fight (闘争)反応とFlight(逃走)反応は交感神経が優位となり、過覚醒になっている状態です。Freeze(凍りつき)反応は低覚醒の状態です。
ヨガやマインドフルネスで耐性の窓を広げる

ヨガやマインドフルネスは、トラウマから回復する上で有効なツールです。トラウマの専門家であるDavid Treleaven氏も、耐性の窓を広げるためにマインドフルネスは有効だと言います。しかし、実践する上で注意が必要です。同氏も、「用い方によっては、外傷性ストレスの症状を悪化させる可能性がある」と述べています。例えば、マインドフルネスの実践中に、耐性の窓から外れて過覚醒状態になり、不安やイライラ、落ち着かなくなること、低覚醒状態になり落ち込みや凍り付くような感じになることがあります。
よって、どのような影響があるのか理解した上で、注意をしながらヨガやマインドフルネスを実践し、耐性の窓を広げていくことが重要です。現在はトラウマに配慮したマインドフルネスやヨガがあり、トラウマセンシティブヨガ、トラウマセンシティブマインドフルネスといった名前がついています。これらはトラウマに対して配慮をしながら、実践の中で耐性の窓の中に留まるためにどうすればいいか、外れたらどうやって戻ってくるかなどを慎重におこなっていきます。興味がある方はご参考にしてください。
※トラウマを抱えており、日常生活に影響がある方はまずは医療機関や専門機関の受診をおすすめします。そして、ヨガやマインドフルネスを実践する場合は、悪化する場合があるので、必ずトラウマに対する理解のあるインストラクターの元で実践するように注意しましょう。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く