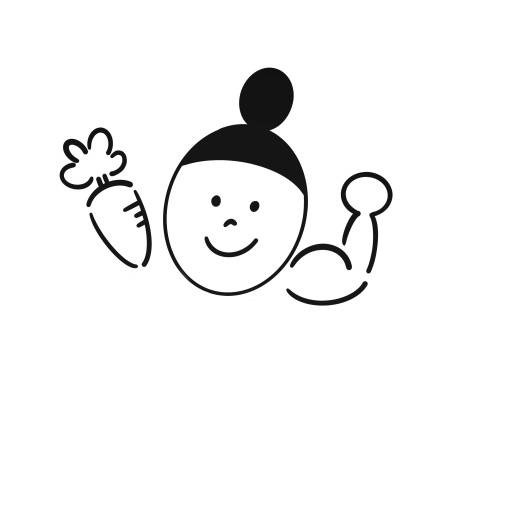実は塩分を摂りすぎる【鍋】ほんのひと工夫!ストレスなく美味しく減塩するコツを栄養士が伝授

寒い季節に大活躍する鍋!野菜がたくさん食べられて健康的なイメージがありますが、塩分量が気になる方もいるのでは?この記事では鍋料理でも塩分を控えて楽しむコツを管理栄養士が解説します。
鍋の塩分はどれぐらい?
市販の鍋の素1人前で塩分が約3~4gほど含まれています。これは鍋の種類や商品によっても大きく変化しますが、スープに塩味のある具材をプラスしたり、付けダレをつけて食べると更に塩分を摂取することになります。日本人の食事摂取基準2020年版によると、1日の塩分摂取量は男性7.5g、女性6.5g未満と設定されています。日本高血圧学会では1日6g未満、世界保健機関だと1日5g未満と各基準に差はありますが、1食で3g以上塩分を取ってしまうと1日の塩分量の半分ほどの摂取してしまうことになります。
鍋料理の塩分を控えて楽しむコツ4選

1.具材の練り物、加工食品を控える。
鍋はスープと共に具材を楽しむ食べ物です。具材の塩分量が高ければスープと合わせて塩分を摂取してしまうことになります。練り物、ウインナー、ベーコンなどの加工肉、つみれや鶏団子など味付けされたミンチの食材は塩分が高めです。またシメのうどんやラーメンなど麺類にも塩が多く使われています。これらの食材をスープで煮込むと食材からの塩分がスープに溶けて流れ出るので、量や種類が多いと塩分量が多くなります。野菜や加工されていないお肉、魚、大豆製品など自然の食品にはうま味や塩味、塩分の排出を促すカリウムなども含まれているので、加工されていない食品を使うことも塩分量を控えるコツになります。
2.うま味が出る食材を使う。
鍋にはうま味のある食材を使うと味に深みやコクが出ます。うま味は大きく分けてイノシン酸、グルタミン酸、グアニル酸の3つがありますが、グルアミン酸にイノシン酸やグアニル酸など違う種類のうま味成分を組み合わせることで相乗効果が働き、うま味を強く感じることができます。スープを手作りする時は出汁をしっかり取り、組み合わせる食材も違ううま味成分を持つものを組み合わせると、少ない調味料でもおいしさがアップします。
グルタミン酸お含む食材:昆布、玉ねぎ、長ネギ、しょうが、トマト、白菜
イノシン酸を含む食材:かつお節、煮干し、鯛、たら、牛肉、鶏肉、豚肉
グアニル酸を含む食材:干ししいたけ
3.塩分の排出を促す食材を取り入れる。
カリウムには体内にたまった余分な塩分を尿と一緒に排出する働きがあります。カリウムは水に溶ける性質があるので、最後に入れて加熱時間を短めに調理したり、薬味や付け合わせの副菜からもカリウムが多く含まれる食材を取り入れてみましょう。
カリウムを豊富に含む食材:
ひじき、のり、わかめ、えだまめ、ほうれん草、白菜、納豆、じゃがいも、大根
4.香りを楽しむ
香りには味を強める効果があると言われています。例えばレモンの香りは酸味を強め、磯の香りは塩味を強めます。味と香りはお互いに影響しあって味わいを強めているのです。よって塩味が少なくても香りをしっかり生かせば味付けが控えめでもおいしさを感じやすくなります。レモンやゆずなどの柑橘類は香りも高くさっぱりとした味わいに。ねぎ、しょうが、のりなどの薬味の後乗せも香りを感じやすく、満足感のある仕上がりになります。
まとめ
寒さが増すにつれて食卓に上がる頻度も増えてくる鍋。工夫しておいしく、健康に楽しみましょう。
〈参考文献〉
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く