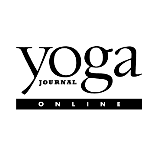大型連休明けに要注意!不安定な子どものメンタルを守る方法とは?発達神経の専門家が解説

近年増加していると言われる発達障害。その子育てに悩む親御さんも多いのではないでしょうか。子どもの神経の発達を専門とする高橋孝雄先生に、お悩み解決法と、子どもの“念のため受診”についてお聞きしました。
不登校の生徒は過去最多を更新、休み明けは不登校が急増
ゴールデンウィークや夏休み、お正月明けなど、大型連休明けは子どもが不安定になりやすい時期です。文部科学省が公表した「問題行動・不登校調査」では、全国の小中学校で2022年度に学校を30日以上欠席した不登校の児童生徒は22.1%増の29万9048人となり、過去最多を記録しました。不登校の増加は10年連続で、小学生は3.6倍、中学生は2.1倍増。要因で最も多かったのは「無気力、不安」でした。また、発達障害の可能性がある子どもは、年々増加傾向で、全国の小中学校で 8.8%、11人に1人程度いると推計されています。
発達や神経の症状など、不安になったら“念のため受診”を
「症状が曖昧な場合、軽い場合、専門医にかかるべきか迷うこともあるかも知れません。お子さんに関する心配ごとなら“何でも来い”です」と話すのは新百合ヶ丘総合病院発達神経学センターの高橋孝雄センター長。
「年齢や発達段階を踏まえて、子どもの神経全般の診療を行うのが当センターです。ネーミングから、ADHD(注意欠如多動症)や自閉スペクトラム症など、いわゆる発達障害のためのセンターだと思われる方も多いです。もちろん、発達障害(神経発達症)も守備範囲ですが、それに限らず、発達と神経に関係した問題であれば、どんな心配ごとにも広く対応しています。子どもの神経に関わる(かも知れない)症状は全て発達神経学の対象なのです。“大丈夫ですよ”の一言をもらいに来てください。」(高橋先生)
子と親の真意を“代弁”する小児診療を目指し、4万人以上の親子を診てきた子育て本のバイブルと評される自著「最高の子育て」は10万部突破!小児科では、患者(子ども)に家族が同伴することがほとんど。症状を患者自身がうまく伝えられないことも多く、家族から得る情報が診療に不可欠です。子と親が本当に伝えたいと思っていることは何か。真意を汲み取り“代弁”することが小児科医の仕事の本質であるといいます。40年以上小児医療に携わった経験にもとづく子育て論をまとめた著書「小児科医のぼくが伝えたい最高の子育て」。累計発行部数も10万部を超え、現代の育児書のバイブルとも評されています。
「親による過剰診断」が増加し、それにより家族を不幸にしてしまう場合も…
子どもの発達障害は、「早期診断、早期心配」にならないように十分な配慮が必要です。
「例えば、2歳になる子を『うちの息子は自閉症(ASD)です!』『手遅れにならないように、なんとかしてください!』といって、病院にやってくるお母さんがいるんです。ネット上などの情報を基にご自身で診断して、必要以上に慌てると、その親心、むやみな心配が、ご家族を不幸にしてしまう可能性もあります。」(高橋先生)

発達障害(神経発達症)という概念が広く知れ渡り、「正常な子」のハードルが高くなったことも患者増の一因だが、病名が不要な場合も多い
「発達障害は、最近では神経発達症と呼ばれます。障害というニュアンスではく、特質、特徴という捉え方です。症状も軽重様々です。神経発達症という概念が広く知れ渡ったこと、そして、学校や社会が子どもに求める“正常な子”のハードルが高くなってきたことで、“患者さん”が増えています。しかし、ちょっと暴れん坊さん、無口でひとりが好きな子はいるものです。そんな子どもたちに病名は不要です。一方、療育などの手助けが必要な子もいますし、薬による治療が有効な場合も時々あります。一般小児科の先生では見極めが難しいこともあり、そういうときには当センターがお力になれると思います」(高橋先生)
小さな子どもの場合、神経の症状があっても、治療が必要なケースは少数。成長とともに症状が収まることがたくさんある
「発達障害と断言できるお子さんはむしろ少ないです。圧倒的に多いのは、症状はあっても治療は必要ないというパターンです。例えば、言葉の発達が遅い子、落ち着きがなくて手に負えない子など、難しい検査や治療が必要なことは稀です。成長とともに症状が収まることがたくさんあるのです。“すぐ入院です”“早速、検査を”などというケースはほとんどありません。“心配よりは、まず受診”です。」(高橋先生)
不登校の子どもには休息が必要、学校嫌いが原因とは限らない!
不登校は学校嫌いが原因とは限りません。家庭に子どもの居場所がないという状況も少なくありません。いずれにしても、子どもは〝全部、自分が悪い〟と孤独感を味わっています。ですから、診察の対象はお子さんだけではなく、ご両親も一緒です。私はほとんどの場合、まずは“学校には行かなくていいよ”とお子さんに伝えることにしています。“当分の間、休養が必要”という診断書を書けるのは医師だけです。

高橋先生が伝えたい!悩める子育てのヒント
「早くしなさい」と言いすぎない。子どもから考える力を奪います。
大人と子どもでは時間感覚がまったく異なって当然です。「早くしなさい!」と声を荒げてしまいがちですが、子どもにしてみれば、なぜ叱られるのか、なぜママは怒っているのか、理解できないと思うのです。おかあさんが「早くしなさい」と子どもを急き立てるシーンは、実はおかあさん自身の段取り不足の結果なのです。「早くしなさい」が口ぐせのおかあさんは、きっとせっかちな性格。せっかちはあながち悪いことではありませんが、せっかちな子育ては別問題です。あまりにもこと細かに指示を出し続けると、子どもは自分でものを考える余裕がなくなるのです。
保育園に預けて、働くおかあさん。短くても濃い時間があれば大丈夫です。
子どもを育てていくなかで、絶対にしてはいけないのが「無視」。子どもに「無関心」でいることです。どんなに短い時間でも、「やっと会えたね、一緒だね」という気持ちですごせればいいのです。夜、おふろのなかででもベッドに入ってから寝るまでのほんの数分でもいいのです。今日1日あったことを聞いてあげてもいいし、好きな絵本を読み聞かせたっていい。朝のほんのひとときだって、子どもはちゃんとママの愛情を感じ取ってくれます。ハグしたり、抱っこするだけでも十分です。時間の長短ではなく、どう過ごすかだと思います。
人よりちょっと早くできるようになるだけ。早期教育はほとんど意味がありません。
子どもが育つ環境のなかでも、教育環境がとても重要であることはたしかです。だからといって、半年でも3か月でも先へ先へ、ごく早期から質の高い教育を施すことが、子どものその後の人生を左右するという考えは、基本的には間違っているように思われます。みんなよりも早くできるようにはなっても、それ以上でもそれ以下でもないのです。画面上を指でスクロールするだけで、世界中のあらゆることが“体験”できる時代です。だからこそ、リアルな体験、つまり実体験がたいせつになってきます。視て、聞いて、ふれて、なめて、においをかいで。積み重ねた実体験こそが、子どもたちの財産です。その過程を促すことが教育の基本なのです。
発達に不安があるなら、なおさら意識してほめましょう。
発達障害を持つ子どもたちへの接し方、育て方には、一般的な子どもたちの子育てにも役立つことがたくさんあります。事故や大けがにつながる危険なこと、公共の場で迷惑をかけることはきちんと叱る。そこでのコツは短いセンテンスで的確にです。日常的に叱り続けると、彼らは耳をふさぐか聞き流します。「叱る」のではなく、「教える」ことが基本です。いざというときにひとつ叱るためには9回はほめておいてください。
小学校入学は、家庭からの脱皮。先生を尊敬し、信頼して任せてください。
ぼくは小学生になるということは「家庭から社会への脱皮」だと思っています。その過程をそっと見守ってあげることが親の使命です。この大切な時期に子どもたちに寄り添い、指導する担任の先生は、第二のおかあさん、おとうさんなのです。そこでおかあさんにお願いしたいことがあります。担任の先生を尊敬しましょう。担任と仲良く力を合わせていくことが、脱皮を成功に導く秘訣です。なにか気になることがあっても「今は脱皮しているんだな」「社会に出たてなんだ」と受け止めて、ゆったりと構えていきましょう。
教えてくれたのは…高橋孝雄(たかはし・たかお)先生

新百合ヶ丘総合病院・発達神経学センター長・名誉院長
慶應義塾大学名誉教授(小児科学教室)。医学博士。専門は小児科一般と小児神経。
1982年慶應義塾大学医学部卒業。1988 年から米国マサチューセッツ総合病院小児神経科に勤務、ハーバード大学医学部の神経学講師も務める。1994年に帰国し、慶應義塾大学小児科で、医師、教授として活躍、2023年より現職。趣味はランニング。マラソンのベスト記録は2016年の東京マラソンで3時間7分。 別名“日本一足の速い小児科教授”。著書に『小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て 』(マガジンハウス)がある。
- SHARE:
- X(旧twitter)
- LINE
- noteで書く